2月28日(金)晴れ。春のような一日、3~18℃
「春の城」。石牟礼道子全集 不知火 第13巻所載を、県立図書館で借りてきて、541頁、3日がかりで一気に読んだ。
寛永14年10月25日(1637年12月11日)、島原半島の南端、口之津を中心に島原藩・松倉勝家の暴政(過酷な貢税と暴虐なキリシタン弾圧)に抗して、同様の苛政に苦しめられていた対岸、唐津藩領の天草諸島の領民が、天草四郎時貞をを盟主に起こした島原・天草の乱の発生の要因から、翌、寛永15年2月28日(1638年4月12日)一揆勢が立て籠もっていた原城が落城するまでの悲史が丁寧に描かれている。
最後、幕府軍の原城総攻撃。ここまで一人ひとり丁寧に描かれてきた登場人物が次々に殺されていく…。
強大な権力への絶望的な抵抗が無残に粉砕され皆殺しにされていく…。
そのやりきれない終局の唯一の救いは、乱後、幕府軍の鉄砲奉行を務めていた鈴木三郎九郎重成が、改易された前領主に代り天草の代官に任命され、文字通り命がけの善政をしいたことである。
彼は、現地に入り、前領主が実高2万1千石しかない藩領を4万2千石と称し、それにあわせて年貢をかけていたことを知り、幕閣に年貢半減策を懸命に上申するが、前例がないとして聞き入れられない。思い屈した鈴木重成は切腹して憤死する。驚いた幕府はその息子に父の跡をつがせ年貢半減を認める。
後にこの事実を知った天草の住民は、彼を神とし祭り今に至るという。
徳川三代、家光の時代、同じ武士階級に属する為政者官僚でも、その人柄により、被支配される領民の側からすれば、天地の差となるのだ。
このことは、今の時代も少しも変わっていないのだ。
北朝鮮の圧政、今、現在進行形のシリアの内戦、ウクライナの政権崩壊と混乱。
著者が、この小説の執筆を思い立ったのは、1971年12月6日、『今は亡き川本輝夫さんをはじめとする水俣病未認定患者とともに、チッソ東京本社に籠城したときである。…酷寒の夜、支援の学生たちと共に路上に寝ていると、プラタナスの枯葉が舞い落ちて頬にまつわることもあった。…その時、原城に立て籠もった名もなき人びとの身の上がしきりに心に浮かんだ。…』とあとがきにあった。
天草で生まれたという著者にとって、約400年近く前の島原・天草の乱はその身近な風土と共に、抗いがたい強大な権力に敢えて命を賭けて抵抗した人々のことは、決して過去の人々とは思えなかったのだろう。
その著者の思いは、飢饉のありさまを書くにも、不順な天候の雲行きから麦の穂の一粒一粒の稔りの違いまで語られていて、今、現実に自分がその畑にたたされているような現実感を受ける。
これは、著者が若き日、自ら畑を耕し、種を蒔き、下肥を天秤棒で運び、作物をそだてた生活があったからこそではないだろうか…。
そして、乱にいたるまでの平穏な日々の暮らしの中の人々の優しい心のゆきかい。これもまた、著者その人の優しさから自然に滲みでてくるのではないだろうか…。
なにはともあれ、今までこんな現実感、日常感のある時代小説は読んだことがなかったように感じた。
読み終えて気がつけば、今日、2月28日は、旧暦ではないが、「春の城」その原城が落城した日だった。あまりの偶然に驚いた。
「春の城」。石牟礼道子全集 不知火 第13巻所載を、県立図書館で借りてきて、541頁、3日がかりで一気に読んだ。
寛永14年10月25日(1637年12月11日)、島原半島の南端、口之津を中心に島原藩・松倉勝家の暴政(過酷な貢税と暴虐なキリシタン弾圧)に抗して、同様の苛政に苦しめられていた対岸、唐津藩領の天草諸島の領民が、天草四郎時貞をを盟主に起こした島原・天草の乱の発生の要因から、翌、寛永15年2月28日(1638年4月12日)一揆勢が立て籠もっていた原城が落城するまでの悲史が丁寧に描かれている。
最後、幕府軍の原城総攻撃。ここまで一人ひとり丁寧に描かれてきた登場人物が次々に殺されていく…。
強大な権力への絶望的な抵抗が無残に粉砕され皆殺しにされていく…。
そのやりきれない終局の唯一の救いは、乱後、幕府軍の鉄砲奉行を務めていた鈴木三郎九郎重成が、改易された前領主に代り天草の代官に任命され、文字通り命がけの善政をしいたことである。
彼は、現地に入り、前領主が実高2万1千石しかない藩領を4万2千石と称し、それにあわせて年貢をかけていたことを知り、幕閣に年貢半減策を懸命に上申するが、前例がないとして聞き入れられない。思い屈した鈴木重成は切腹して憤死する。驚いた幕府はその息子に父の跡をつがせ年貢半減を認める。
後にこの事実を知った天草の住民は、彼を神とし祭り今に至るという。
徳川三代、家光の時代、同じ武士階級に属する為政者官僚でも、その人柄により、被支配される領民の側からすれば、天地の差となるのだ。
このことは、今の時代も少しも変わっていないのだ。
北朝鮮の圧政、今、現在進行形のシリアの内戦、ウクライナの政権崩壊と混乱。
著者が、この小説の執筆を思い立ったのは、1971年12月6日、『今は亡き川本輝夫さんをはじめとする水俣病未認定患者とともに、チッソ東京本社に籠城したときである。…酷寒の夜、支援の学生たちと共に路上に寝ていると、プラタナスの枯葉が舞い落ちて頬にまつわることもあった。…その時、原城に立て籠もった名もなき人びとの身の上がしきりに心に浮かんだ。…』とあとがきにあった。
天草で生まれたという著者にとって、約400年近く前の島原・天草の乱はその身近な風土と共に、抗いがたい強大な権力に敢えて命を賭けて抵抗した人々のことは、決して過去の人々とは思えなかったのだろう。
その著者の思いは、飢饉のありさまを書くにも、不順な天候の雲行きから麦の穂の一粒一粒の稔りの違いまで語られていて、今、現実に自分がその畑にたたされているような現実感を受ける。
これは、著者が若き日、自ら畑を耕し、種を蒔き、下肥を天秤棒で運び、作物をそだてた生活があったからこそではないだろうか…。
そして、乱にいたるまでの平穏な日々の暮らしの中の人々の優しい心のゆきかい。これもまた、著者その人の優しさから自然に滲みでてくるのではないだろうか…。
なにはともあれ、今までこんな現実感、日常感のある時代小説は読んだことがなかったように感じた。
読み終えて気がつけば、今日、2月28日は、旧暦ではないが、「春の城」その原城が落城した日だった。あまりの偶然に驚いた。



















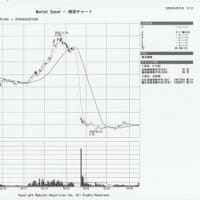
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます