第5回てつがくカフェ@ふくしまがサイトウ洋食店で開催されました。
今回はオーナーである齋藤さんのご協力のもと、初めて本格的なフレンチカフェ(レストラン?)で開催させていただくことができました。
ゆったりしたカフェ空間の中での議論はさらに充実したものになっています。
今回は12名の方々にご参加いただきました。
テーマは「〈正義〉って何だろう?」です。
いつものように参加者から自由に正義に関して思いつくことを挙げていただくところから始めました。
まずは正義は青臭く、まじめで血気盛んなイメージがあるとの意見が出されました。
あまり日常生活で用いる概念ではなく、自分の中では高い位置づけにないという意見です。
たしかに日常で私たちは正義を振りかざすことはあまりないでしょう。
すると、それはどのレベルで用いられるのかという問題が浮上します。
それに対して、正義は戦争や国家レベルで用いられる概念ではないかとの意見が出されました。
その際、正義は悪を排除するために戦うものとして用いられます。
9.11以降のアフガン攻撃やイラク戦争をふり返れば、「対テロ」や「対悪の枢軸」というアメリカの正義が喧伝されたことが思い出されます。
とはいえ、議論の中ではいじめの問題を材料として挙げられるなど、「正しさ」を問う場面が日常レベルでもありうることが示されました。
では、その際に正義/悪の基準は誰が決めるのでしょうか。
これは絶対的な位置での正義を決めることは可能かという問いを孕みます。
これに対しては、さらに正義の反対は悪なのかとの反問も出されました。
すなわち、誰かが正義を振りかざせばそれに対する正義も立ち上がるのであり、したがって究極的にいえば正義などこの世界に存在しないのではないか。
そんな過激な意見も出されました。
ふり返ってみれば、9.11以降、正義に対して私たちはずいぶんと懐疑的になったように思われます。
これについて、その発端は正義が戦争遂行の「大義名分」として用いられ、自らの行動を正当化するためだけに用いられるようになったことにあるとの意見が出されました。
しかも、その実、当の行為者はそれが正義でもなんでもないと思いながら用いているだけではないかというのです。
たしかに、政治の二枚舌がまかり通っていることへの不信が、「ニセモノの正義」という懐疑をもたらしたというのはその通りでしょう。
けれど、それは裏を返せば本来(真)の正義が存在することを示すものでもあります。
では、本来の正義とは何か?
その意見によれば、それは「自己犠牲」が発生するものだとのことです。
社会保障など観点から見ても、たしかに税金などは自己犠牲による正義の実現といえなくもありません。
しかし、正義がつねに自己犠牲を伴うものだとすれば、それは非常に重いものではないでしょうか。
何より、戦争こそは最大の自己犠牲が強いられるものです。
たとえ、それが洗脳や大義名分による嘘とわかっていたとしても、やはり国家的正義の実現を自己犠牲のもとに強いられる事態であることに変わりはないでしょう。
これに対しては、正義とはみんなが納得しなければ成立しないものではないかとの意見が関係しそうです。
たしかに自己犠牲という立派な行為が正義と結びつくことは直感的に理解できるけれども、誰しもそのような厳格な自己犠牲を強いられることには抵抗を覚えるものでしょう。
むしろ、それを前提としている運営される社会システムというのは、戦争状態がまさにそうであるように、相当破綻しかけているのではないでしょうか。
すると、問題は自己犠牲の許容範囲について共通認識が形成されているかという点が、その社会における正義の実現にとって重要であるということになります。
以上の意見や問題提起を踏まえ、まずは「普遍的な正義はありうるか」という論点から議論は深められました。
まず正義は何のために必要とされるのか。
それは誰かの平和や幸福を守るために必要とされるのだけれども、その範囲が国民という枠で語られる場合、それは国家同士の利害対立という事態を招くことになります。
そこにおいて利害対立するもの同士が共有し合える正義はないことが示されますが、果たして国家の枠組みを超える正義はありうるかという問題があります。
これに関しては、果たして正義の共通理解が可能だろうかという問題が関係します。
宗教や文化の多様性は時としてその障害になるでしょう。
そもそも個人の多様性を考えれば、その利害が一致することなどほとんどありえないというのが、普遍的正義に対する懐疑をもたらします。
けれど、戦争など悲惨な出来事は歴史上数あれど、大きい視点で見れば国家の枠を超えて国際的な差別や暴力は縮減される努力がなされてきているのだから、それは少しずつでも普遍的な正義へ向けて歴史は動いているのではないかとの意見も出されました。
たしかに、タテマエとはいえ正義を根拠に戦争を起こすという国家行為は、あからさまに私利私欲によって戦争を起こすことを国際社会が許容しないようになったことに対応するためだともいえそうです。
その意味で言えば、少しずつではあるけれど共通理解を進めながら普遍的正義は実現していっているのかもしれません。
ただし、それは常に正義を称揚することに警戒しつつ進むことに注意が払われました。
すなわち、わたしたちは正義の内実を疑い、考えながら、求め続けるべきものではないかというわけです。
これに関しては、他者の立場に身を置き換えて考えることが、正義の実現に通じていくのではないかとの意見とも符合します。
これらの意見を踏まえると、普遍的な正義とは挫折しつつも、いつか到達できるだろうと希望されるものということができそうです。
むしろ、その希望があるからこそ、人は正義へ向けて行動しようとするものともいえるでしょう。
一方、そうはいっても歴史は勝者の側に正義を独占させてきたという面があります。
国家間の戦争も勝ち残った側にこそ正義の判定が下されてきました。
テロ行為も失敗すれば犯罪者ですが、反政府行動によって政権の座を奪えば、それは正義の実現と評価されます。
また、現実の社会においては多数者の利益を優先することが社会的正義にかなっているという面も指摘されました。
社会が危機に瀕しているとき損害は最小限度にとどめるという意味では、最大多数の利益が優先されるというのは社会的正義にかなった判断だともいえます。
すると、正義とは数の多さや多数派の利益にかなうものだということになりますが、言い換えれば、それは力を持つものこそが正義をもちうるということにも通じるでしょう。
こうしてみると歴史の勝者といい社会的多数派といい、正義を称することには何か権力性を帯びるような面も浮かび上がります。
そして、そこでは「弱いものを助ける」という意味での正義の意味は後退しているようにも思われます。
これに関しては、みんな不正だと思っているにもかかわらず誰もその行為を止めないという例として、学校でのいじめの問題も論じられました。
正義なき力は暴力だが、力なき正義は無力であるということもあります。
そうなると、正義を考える上では「力」との関係を議論する必要もあるようです。
これについて、「俺が正義だ」と前もって言うことは正義とは思えないという意見は興味深いものでした。
というのも、それが正義であるか否かという判断は、実はその周囲の人々やあるいは後の時代の人々といった、実行者以外の人々ができる判断であって、その当の実行者が前もって語る瞬間に胡散臭いものになるというのです。
私たちは時として、歴史の勝者や権力者の所業について「不正である」と判断することがあります。
しかも、それは歴史の敗者や少数者の側に立ちながら、より普遍性を帯びた正義の判断を下す場合があります。
たとえば、正義を振りかざしてイラク戦争を開始したアメリカの行動に対し、国際社会の多くは不正の判断を下しました。
その意味で言えば、力の大小が必ずしも正義の判断と一致するわけではありません。
しかし、問題はそのよう不正の判断が国際社会において示されたにもかかわらず、アメリカの軍事行動をとめることはできませんでした。
すると、これは正義の無力だったのでしょうか。
これについては正義の判断は普遍的に共有される可能性があるけれども、その実践の段階になるとそのことが困難になるという面が指摘されました。
それはやはり正義には力の行使が必要とされなければならないということが確認されます。
国家であれば裁判所を中心とした司法権がそれを担わなければならないでしょう。
しかし、その反面、ここには力の行使が正義を損なうという面も指摘されます。
判断において普遍性を帯びていたものが、いざその実現に向けて行動すると不正を帯びるという問題は、やはり国際社会において紛争を中止させるために武力介入する問題において生じるでしょう。
果たして、正義の判断と実践という問題でまたもやアポリアに陥ってしまったように思われます。
今回の議論は普遍的な正義を求めつつも、しかしなぜかそれを語ることへの違和感が入り混じりながら活発に展開しました。
毎度のことですが議論はこれに尽きません。
不正を犯したことに対する正義の回復と死刑の問題、あるいは何を持って公正としての正義を実現できるのかといった問題など、まだまだ語り合うべき課題は数多く積み残したまま終了せざるを得ませんでした。
しかし、正義に関するてつがくカフェは、これを皮切りに具体的なテーマを変えながら引き続き取り組んでいきたいと考えておりますので、今後にご期待下さい。
お忙しい中、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
回を重ねるごとに議論の密度が濃くなっているように思います。
さらなる活性化を期して、ファシリテータとして技量を磨くことに邁進していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
今回はオーナーである齋藤さんのご協力のもと、初めて本格的なフレンチカフェ(レストラン?)で開催させていただくことができました。
ゆったりしたカフェ空間の中での議論はさらに充実したものになっています。
今回は12名の方々にご参加いただきました。
テーマは「〈正義〉って何だろう?」です。
いつものように参加者から自由に正義に関して思いつくことを挙げていただくところから始めました。
まずは正義は青臭く、まじめで血気盛んなイメージがあるとの意見が出されました。
あまり日常生活で用いる概念ではなく、自分の中では高い位置づけにないという意見です。
たしかに日常で私たちは正義を振りかざすことはあまりないでしょう。
すると、それはどのレベルで用いられるのかという問題が浮上します。
それに対して、正義は戦争や国家レベルで用いられる概念ではないかとの意見が出されました。
その際、正義は悪を排除するために戦うものとして用いられます。
9.11以降のアフガン攻撃やイラク戦争をふり返れば、「対テロ」や「対悪の枢軸」というアメリカの正義が喧伝されたことが思い出されます。
とはいえ、議論の中ではいじめの問題を材料として挙げられるなど、「正しさ」を問う場面が日常レベルでもありうることが示されました。
では、その際に正義/悪の基準は誰が決めるのでしょうか。
これは絶対的な位置での正義を決めることは可能かという問いを孕みます。
これに対しては、さらに正義の反対は悪なのかとの反問も出されました。
すなわち、誰かが正義を振りかざせばそれに対する正義も立ち上がるのであり、したがって究極的にいえば正義などこの世界に存在しないのではないか。
そんな過激な意見も出されました。
ふり返ってみれば、9.11以降、正義に対して私たちはずいぶんと懐疑的になったように思われます。
これについて、その発端は正義が戦争遂行の「大義名分」として用いられ、自らの行動を正当化するためだけに用いられるようになったことにあるとの意見が出されました。
しかも、その実、当の行為者はそれが正義でもなんでもないと思いながら用いているだけではないかというのです。
たしかに、政治の二枚舌がまかり通っていることへの不信が、「ニセモノの正義」という懐疑をもたらしたというのはその通りでしょう。
けれど、それは裏を返せば本来(真)の正義が存在することを示すものでもあります。
では、本来の正義とは何か?
その意見によれば、それは「自己犠牲」が発生するものだとのことです。
社会保障など観点から見ても、たしかに税金などは自己犠牲による正義の実現といえなくもありません。
しかし、正義がつねに自己犠牲を伴うものだとすれば、それは非常に重いものではないでしょうか。
何より、戦争こそは最大の自己犠牲が強いられるものです。
たとえ、それが洗脳や大義名分による嘘とわかっていたとしても、やはり国家的正義の実現を自己犠牲のもとに強いられる事態であることに変わりはないでしょう。
これに対しては、正義とはみんなが納得しなければ成立しないものではないかとの意見が関係しそうです。
たしかに自己犠牲という立派な行為が正義と結びつくことは直感的に理解できるけれども、誰しもそのような厳格な自己犠牲を強いられることには抵抗を覚えるものでしょう。
むしろ、それを前提としている運営される社会システムというのは、戦争状態がまさにそうであるように、相当破綻しかけているのではないでしょうか。
すると、問題は自己犠牲の許容範囲について共通認識が形成されているかという点が、その社会における正義の実現にとって重要であるということになります。
以上の意見や問題提起を踏まえ、まずは「普遍的な正義はありうるか」という論点から議論は深められました。
まず正義は何のために必要とされるのか。
それは誰かの平和や幸福を守るために必要とされるのだけれども、その範囲が国民という枠で語られる場合、それは国家同士の利害対立という事態を招くことになります。
そこにおいて利害対立するもの同士が共有し合える正義はないことが示されますが、果たして国家の枠組みを超える正義はありうるかという問題があります。
これに関しては、果たして正義の共通理解が可能だろうかという問題が関係します。
宗教や文化の多様性は時としてその障害になるでしょう。
そもそも個人の多様性を考えれば、その利害が一致することなどほとんどありえないというのが、普遍的正義に対する懐疑をもたらします。
けれど、戦争など悲惨な出来事は歴史上数あれど、大きい視点で見れば国家の枠を超えて国際的な差別や暴力は縮減される努力がなされてきているのだから、それは少しずつでも普遍的な正義へ向けて歴史は動いているのではないかとの意見も出されました。
たしかに、タテマエとはいえ正義を根拠に戦争を起こすという国家行為は、あからさまに私利私欲によって戦争を起こすことを国際社会が許容しないようになったことに対応するためだともいえそうです。
その意味で言えば、少しずつではあるけれど共通理解を進めながら普遍的正義は実現していっているのかもしれません。
ただし、それは常に正義を称揚することに警戒しつつ進むことに注意が払われました。
すなわち、わたしたちは正義の内実を疑い、考えながら、求め続けるべきものではないかというわけです。
これに関しては、他者の立場に身を置き換えて考えることが、正義の実現に通じていくのではないかとの意見とも符合します。
これらの意見を踏まえると、普遍的な正義とは挫折しつつも、いつか到達できるだろうと希望されるものということができそうです。
むしろ、その希望があるからこそ、人は正義へ向けて行動しようとするものともいえるでしょう。
一方、そうはいっても歴史は勝者の側に正義を独占させてきたという面があります。
国家間の戦争も勝ち残った側にこそ正義の判定が下されてきました。
テロ行為も失敗すれば犯罪者ですが、反政府行動によって政権の座を奪えば、それは正義の実現と評価されます。
また、現実の社会においては多数者の利益を優先することが社会的正義にかなっているという面も指摘されました。
社会が危機に瀕しているとき損害は最小限度にとどめるという意味では、最大多数の利益が優先されるというのは社会的正義にかなった判断だともいえます。
すると、正義とは数の多さや多数派の利益にかなうものだということになりますが、言い換えれば、それは力を持つものこそが正義をもちうるということにも通じるでしょう。
こうしてみると歴史の勝者といい社会的多数派といい、正義を称することには何か権力性を帯びるような面も浮かび上がります。
そして、そこでは「弱いものを助ける」という意味での正義の意味は後退しているようにも思われます。
これに関しては、みんな不正だと思っているにもかかわらず誰もその行為を止めないという例として、学校でのいじめの問題も論じられました。
正義なき力は暴力だが、力なき正義は無力であるということもあります。
そうなると、正義を考える上では「力」との関係を議論する必要もあるようです。
これについて、「俺が正義だ」と前もって言うことは正義とは思えないという意見は興味深いものでした。
というのも、それが正義であるか否かという判断は、実はその周囲の人々やあるいは後の時代の人々といった、実行者以外の人々ができる判断であって、その当の実行者が前もって語る瞬間に胡散臭いものになるというのです。
私たちは時として、歴史の勝者や権力者の所業について「不正である」と判断することがあります。
しかも、それは歴史の敗者や少数者の側に立ちながら、より普遍性を帯びた正義の判断を下す場合があります。
たとえば、正義を振りかざしてイラク戦争を開始したアメリカの行動に対し、国際社会の多くは不正の判断を下しました。
その意味で言えば、力の大小が必ずしも正義の判断と一致するわけではありません。
しかし、問題はそのよう不正の判断が国際社会において示されたにもかかわらず、アメリカの軍事行動をとめることはできませんでした。
すると、これは正義の無力だったのでしょうか。
これについては正義の判断は普遍的に共有される可能性があるけれども、その実践の段階になるとそのことが困難になるという面が指摘されました。
それはやはり正義には力の行使が必要とされなければならないということが確認されます。
国家であれば裁判所を中心とした司法権がそれを担わなければならないでしょう。
しかし、その反面、ここには力の行使が正義を損なうという面も指摘されます。
判断において普遍性を帯びていたものが、いざその実現に向けて行動すると不正を帯びるという問題は、やはり国際社会において紛争を中止させるために武力介入する問題において生じるでしょう。
果たして、正義の判断と実践という問題でまたもやアポリアに陥ってしまったように思われます。
今回の議論は普遍的な正義を求めつつも、しかしなぜかそれを語ることへの違和感が入り混じりながら活発に展開しました。
毎度のことですが議論はこれに尽きません。
不正を犯したことに対する正義の回復と死刑の問題、あるいは何を持って公正としての正義を実現できるのかといった問題など、まだまだ語り合うべき課題は数多く積み残したまま終了せざるを得ませんでした。
しかし、正義に関するてつがくカフェは、これを皮切りに具体的なテーマを変えながら引き続き取り組んでいきたいと考えておりますので、今後にご期待下さい。
お忙しい中、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
回を重ねるごとに議論の密度が濃くなっているように思います。
さらなる活性化を期して、ファシリテータとして技量を磨くことに邁進していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。











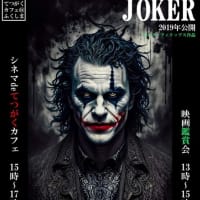






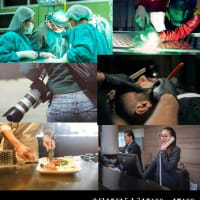

もう、サマリーができてしまいましたか。
内容をまとめるのは結構大変かと思い、自分の発言部分を書いて参考にしていただければと思いましたが、もはやその必要はなかったようですね。
あまりにも報告内容の完成度が高く、恐れ入りました。あくまで参加者の個人的な見方として一瞥をいただければ幸甚です。
正義というお題をいただいての、まず自分の率直な印象は
<正しさ>ということと同義であるとの解釈から、若さ、真面目さ、生意気、ストレート、青臭い といったものと考えておりました。
このため、自分の中で正義というものについての価値にあまり重きをおいていなかったというところが本音です。
それよりむしろ、バランスとか、ハーモニーのある世渡りのうまさとか、協調、調和のほうが自分の中で尊ぶべき上位にある価値と思っていたので、あまり今回の題には個人的に興味を魅かれなかったとお話ししました。
ところが、自己犠牲の有無、公平や平等観、国家的対立とまで話しが大きくなってしまってとても面くらいました。
あくまで、身近な現実問題の解決が主な関心事である私には、そうやすやすと手出しできない領域に踏み込んだ感があり、皆さんのお話しを自分の中の解釈に落とし込んで理解につなげようという作業を繰り返しておりました。
途中、Sさんに正義の対義語は悪ですかと聞きましたが、私のなかでの答えは
正義の対義語は、それと異なる正義であろうととらえています。
<正義は普遍的なものか>の答えは、無いというのは言い過ぎでした。それぞれ個々人に自分の中での主義、主張としての正義はあるのだけれど万人の正義はないのではなかろうかと考えています。しかしこの部分については、Oさんの締めの部分で<普遍的なものはあると思いたい>という表現が使われていたので、自分的にはそれで異論なしです。
自分以外の方の発言では、正義は行われた後に、周囲が評価するものという話しには驚きでした。それは正しいか間違っているかは、やっている当人は決められないし、その時点では誰もが分からないものだという当たり前のようなことを言っているような気はするのですが。。。しかしここは自分の中で今一つ釈然としませんでした。新しい見方をいただいた気になりました。
他には利益を考えに入れた正義は正義じゃないとかがありました。感覚的には分かるのですが、ここももう少し考える余地があるような気がいたしました。
そんなこんなで、道徳とか倫理のような範疇にまで話題は広がっていきましたが、
私個人としては道徳と正義との関係においては、正義は道徳の一部分である気がしています。
そして、ことさら正義を尊ぶべきものとはあまり考えていないという自分の考えは一貫しています。
ここからは今回の内容から離れ、この会に臨む前に自分が考えたことで飛躍が入ってしまいますがご容赦ください。
まず自分の生き方としては、
仙人は人里離れた山奥にいるから仙人でいられるのであろう、むしろ世間にあっても仙人のような心持でいたい ということに私は憧れているところがあります。
<君子>という表現でいいのでしょうか?(和して同せず という言葉を聞いたころにはいい具合に出来上がってしまっていたので気の利いた返答が出来なくてすみませんでした)
もう一つは、Oさんのブログで紹介されたことのある 『超訳 ニーチェの言葉』から 198番が自分的には響いています。
この中に 勇気 正義 節制 智慧 という単語があります。
そして、いろいろ考えはあると思いますが、自分はこれをそのまま受け取って信じてしまっています。
そこが正義に重きをおかない自分の根拠になっています。
そして、自分的にさらに言えば 具現化された言葉や行動のうらに、考え抜かれた叡智を希求する といったことです。(好みとしてですが、直球はあまり得意ではありません)
しかし、その一方で智慧のレベルを求めながらも、まだまだそこに至っていない自分が現実の世界にいて、それこそ第二レベルの周りをうろついているのが自分のようにも思っています。だから、現実世界でうまく立ちまわれていないのでしょう。
実践というのはなかなか難しいものですね。(認識は一致できるところがあるけれど、行動まで一致できるかは、個々でかなり異なってくるものかもしれません)
感想) 言葉の定義が同業者と話すより、てつがくカフェでの方が自由度が高いのでゴチャゴチャになりますが、それがてつがくカフェの醍醐味ですね。ただ、たとえや具体例が出た際に、それを知らなかったり経験がなかったりすると話題がはっきりしなくなります。
テーマは長い方が具体的でいいのではとか、書評カフェ、シネマカフェとかのほうが同じ素養がある分だけ、スムースなのかもしれないとも思いました。
しかし同時にそれが自由度を低めてはいけないのだろうし、主催者を悩ませるところですね。
次回10月22日 原発がテーマですね。ぜひ参加したいです。