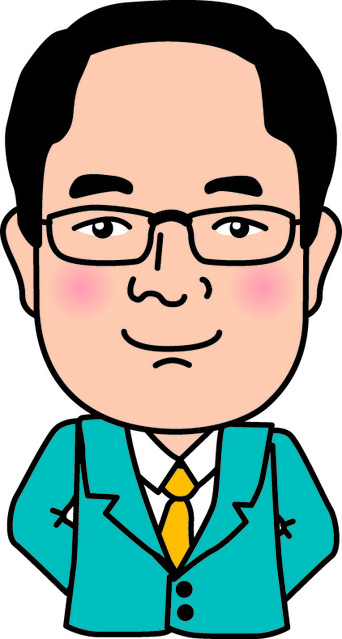そういえば前回の検定試験問題の解答を出していなかったので、興味のない方も
多いとは思いますが、出題した責任を果たすため、解答を一応掲載しておきます。
前回の問題
江戸時代の庶民の起床は、明け六つ、およそ日の出の頃でした。
ところで、「お江戸日本橋七つ立ち」といいますが、この七つとは、
今の時刻では何時ごろでしょうか?
季節によってズレがありますが、春分の日を想定してお答えください。
ア 午前4時頃
イ 午前5時頃
ウ 午前7時頃
エ 午前8時頃
解答 (ア) 午前4時頃
解説
江戸時代の時法は、不定時法といわれるものです。
時間の基本単位は一刻(およそ2時間)で、昼と夜、夏と冬では一刻の時間の
長さに違いがあります。日の出と日の入りを基本にしていたからです。
「明け六」と「暮れ六」を決めた上で、両者の時間を昼・夜それぞれ六等分し、
明け六つのあと、五つ、四つと数字が減る形で減り、正午で九つに飛び、八つ、
七つと進み、暮れ六つになります。
江戸時代と異なり現在は定時法なので一概に現在の時刻と対照できないのですが、
春分の日、秋分の日は、昼と夜の長さが同じなのでこの日で考えると、現在の
12時(昼夜)は九つ、2時は八つ、4時は七つ、6時は六つ、8時は五つ、
10時は四つとなります。
う~ん、なんのことだかよく理解できませんが、江戸文化歴史検定の解答を
見ていただくと、当時の時間を表した図が掲載されていますので、さらに知りたい
方は一度hpをご覧ください。
http://edoken.shopro.co.jp/test/a01.html
多いとは思いますが、出題した責任を果たすため、解答を一応掲載しておきます。
前回の問題
江戸時代の庶民の起床は、明け六つ、およそ日の出の頃でした。
ところで、「お江戸日本橋七つ立ち」といいますが、この七つとは、
今の時刻では何時ごろでしょうか?
季節によってズレがありますが、春分の日を想定してお答えください。
ア 午前4時頃
イ 午前5時頃
ウ 午前7時頃
エ 午前8時頃
解答 (ア) 午前4時頃
解説
江戸時代の時法は、不定時法といわれるものです。
時間の基本単位は一刻(およそ2時間)で、昼と夜、夏と冬では一刻の時間の
長さに違いがあります。日の出と日の入りを基本にしていたからです。
「明け六」と「暮れ六」を決めた上で、両者の時間を昼・夜それぞれ六等分し、
明け六つのあと、五つ、四つと数字が減る形で減り、正午で九つに飛び、八つ、
七つと進み、暮れ六つになります。
江戸時代と異なり現在は定時法なので一概に現在の時刻と対照できないのですが、
春分の日、秋分の日は、昼と夜の長さが同じなのでこの日で考えると、現在の
12時(昼夜)は九つ、2時は八つ、4時は七つ、6時は六つ、8時は五つ、
10時は四つとなります。
う~ん、なんのことだかよく理解できませんが、江戸文化歴史検定の解答を
見ていただくと、当時の時間を表した図が掲載されていますので、さらに知りたい
方は一度hpをご覧ください。
http://edoken.shopro.co.jp/test/a01.html