メインテキスト: マイケル・サンデル 鬼澤忍訳『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』(原著2009年刊 早川書房平成22年5月 同年9月87版)
最近の私はネットで本を買うばっかりで、本屋にはめったに行かなくなった。
昨年暮れ、久しぶりに立ち寄ったら、入口付近の最も目立つ棚に、ドラッカーの本などと一緒に平積みにされている白い本があった。やっぱりマネージメントか何か、そっち系の本なんだろうな、と軽く考えてふと書名を見たら『これからの「正義」の話をしよう』。え? 金儲けに「正義」が関係あるわけ? そんなのにこだわっていたら、商売の障りになるばかりじゃないか?
と不審に感じ、著者名を見たらマイケル・サンデル。え? あの? 『自由主義と正義の限界』の? それじゃあ、政治哲学だよな、どうしてそんな本がこんな、売れ筋商品を並べる場所にあるわけ? と、つられて、私は、表紙の、帯を見た。「NHK教育テレビにて放送!」「ハーバード白熱教室in東京大学(仮)」。
つまり、ハーバード大でサンデル教授の講義の人気は高く、ついにTV放送されるに及んだ、それは日本でも放映され、サンデル自身、東大へ来て出前授業をした、とのこと。
後日私は、何人もの知人がこの番組を見ていたことを知った。我が家のチャンネル権は、まず五歳の息子が握っており、次が家内、最後が私で、この序列最下位の者が好きな番組を見る機会はごく僅か。自然、TVそのものへの関心も薄くなって、私はこのような番組の存在を全く知らなかった。従って、授業者としてのサンデルの腕前のほどについては何も分からない。今後DVDか何かで、番組を見る機会はあるかも知れないが、それを自分の授業で生かせるかどうか、まあ、望みは薄い。
しかし、いくらわかりやすく書いてあって、TVの(結果としての)宣伝はあったとはいえ、このような本がベストセラーになるというのは、いまだに不思議である。これは私が世間の人をみくびり過ぎていたということか。客観的には望みは薄い、としか依然として思えないが、今後は生徒をなんとか乗せる手立てをもう一工夫してみよう。
サンデルの講義はその名も「正義」Justiceと名付けられているとのこと。この講義名は日本では考えられないだろうな。中身は、多くは実際にあった、いろいろな事例を出して、「何が正義か」を学生たちに考えさせ、議論させる、と。それはきっと面白いだろう。結論は出ないだろうし、学生たちが今後生きていくうえでどれくらい役に立つかはやや疑問だが。授業は、やらなくてはならないものなら、面白いに越したことはない。
で、ついに私は買うことにした。
この本は、講義をベースにして、新たに書き下ろされたものだ(同書「謝辞」P.347)。授業の熱気は伝わらないが、とりあえず私は、倫理、というか、「何が正しいか」の話は好きだ。英米系の哲学者が得意らしい「思考実験」(譬え話のようなものを使って、ものごとを考えさせること)も好きだ。事実、面白く読めた。これから述べるいくつかの違和感はあったが、それをも含めて。
一つ私も、サンデル先生の生徒になったつもりで、「何が正義か」について、というより、「何が正義かなんて、なかなかわからない」ことについて、になると思うが、自分の意見を述べよう。読んでくれている人の中で、御親切に、サンデル先生になりかわって、教導してくださる人がいらっしゃったら、よろしくお願い申します。
本書は第一章からして、考える材料を豊富に出している。そのうちの柱は、(1)2004年の夏、甚大な台風被害を被ったフロリダで、実際にあった話と、(2)思考実験のための譬え話としてけっこう有名らしい、「暴走する路面電車」。
コミュニタリアン(共同体主義者)として著名なサンデルは、(1)は自由主義に対する、(2)は功利主義に対する、批判のための例示にするつもりらしい、とは後からわかる。そんなのは知らなくてもいいようなものだけれど、知ってしまうと、そうとしか読めない論述になっている。本であれ講義であれ、一人の人がやる以上、その人格からあるバイアスがかかるのは、どうにも仕方がない。
(1)は、台風通過直後のフロリダで、氷や家庭用発電機や家の修理費用やモーテル代が高騰した話。もちろん便乗値上げも多く、最終的には規制されたが、経済学者の中には、そのような施策は不要である、と唱えた者もいたそうだ。
その理由の第一は原理的なもの。自由主義経済下ではものの値段は需要と供給によって決まるのであって、それは時と場所によって変動するのが当たり前。取引(売り買い)以前に「公正な価格」があるように思うのは、畢竟感情的な問題に過ぎない。
第二は現実的なもので、これによって経済活動を活性化させることができる、ということ。例えば氷が高く売れる見込みがあるなら、多くの業者が増産してフロリダまで運ぶようになるだろう。結果として、被災地の復興が早まる効果が期待できる。
後のほうは、実際にそうなったかどうか、わからないが、ここではそうだった、ということにする。そうだとしても、だから便乗値上げをした業者は正しく、その事態は放置しておくほうがいいのか、となると、少なからぬ人が首をかしげるだろう。人が困っているのにつけ込んで金儲けをする輩に対しては、なんらかの社会的な規制なり罰則が必要なのではないか、と素朴に思えてくる。
いや、罰もまた市場(売り買いの場)によって与えられるから、それ以上のことを考える必要はないのだ、とする立場もあるだろう。高い品物やサービスを売りつけられた消費者は、自由に買える日が来たら、二度とその業者からは買わないかも知れない。ところで、それは当然だ、と思うぐらいには、私たちはこのような際に便乗値上げをする業者はあこぎで、悪しき者だと考えているのだ。
即ち、自由主義が、経済的に完全なレッセフェール(放置主義)で市場万能主義をよしとするとしたら、一般にいつも正しいとはされ得ない。その通り。異論はない。
(2)のほうは少々難しい。純然たる思考実験、つまり仮定の話だ。
仮定1。あなたは路面電車の運転手だ。時速六十マイルで走行中、前方に五人の作業員が線路にいるのを発見する。ブレーキは間に合わない。ふと、右側へそれる待避線が目に入る。そこには一人だけ作業員がいる。この待避線へとハンドルを切れば、五人の命は助けられるが、一人は殺すことになる。あなたならどうするか?
仮定2。あなたは橋の上から、走行している路面電車の前方の線路に、五人の作業員がいるのを見る。あなたの隣にはとても太った男がいた。彼を橋から突き落とせば、その男は死ぬだろうが、電車は止まり、五人の命は助かる。どうするか?
(しかし、特に「仮定2」のほうは、すごい仮定だ。だいたい、ぶつかって電車を止められるほどのデブがいるものだろうか。こういうのはデブ差別ではないか、とデブの私などは思うが、もちろんそれは関係ない話)
多くの人が、「仮定1」では、電車を待避線に入れて、一人を殺して五人を助けるほうがいいと考えるだろう。しかし「仮定2」では、デブを突き落として五人助けるのがいいとは思えないだろう(そうですか?)。
しかし、何が違うのか? 両方の場合とも、一人の命を犠牲にして五人の命を救う、という点では変わらない。功利主義は、人の命も計算できるとするから、その立場からは、いつも、一人の命より五人の命のほうに、より(五倍の?)価値があることになる。「仮定1」で一人の犠牲者を出すことが正しい行為なら、「仮定2」でも正しい行為である。そうとしか言えない。
それには同意できないとすれば、功利主義はいつも、一般的に正しいとはされないことになる。う~ん、それはそうか…? でも、これでちゃんと批判したことになるか? いや、それ以前に、前提が少しおかしくないか?
どのような理由からであれ、やむを得ず一人を死なせるのと、積極的に手を下して一人を殺すのでは、やっぱり違う、とは確かに思えるかも知れない。しかしそれこそ、感情の問題ではないだろうか?
では、やっぱりどちらの行為も正しいということになるか? いや、むしろ逆ではなかろうか。「仮定1」の場合、運転手が結果として一人死なせる行為は「やむを得ないこと」として、免責されるのは当然であるとしても、積極的に推奨できる「正しい行為」とまで言えるのだろうか? 感情の問題からすると、あなたが、助かった五人とは赤の他人であり、死ぬことになった一人の友人や家族だったとしても、正しいことがなされたのだからよかったのだと、納得できるものだろうか?
ここで、そんなことを言うなら、(1)の場合だって、規制されたり罰を受けたりする業者やその身内はいやな思いをするじゃないか、と考える人がいるかも知れないので、言葉を重ねよう。このときには、特定の人々の利益や感情を損ねる結果になっても、それを無視して貫くべき「社会的正義」がある、と私は考える。なんと言っても、便上値上げは、自らの意思で行うものだ。しかし(2)は、被害者の意思は全く関係ない。「仮定1」と「仮定2」の違いは、死なせる側の積極性の度合いに過ぎない。片方を是とし、片方を非とするのは、どうにも割り切れないものが残りはしないか?
本書を最後まで読んでも、「仮定1」での結果としての殺人は正しいが「仮定2」ではそうではない、とする根拠は示されない。割り切れなさは宙ぶらりんのまま残される。さらに、それと同じような思いは、本書中のいろいろな場所で反響するのである。
最近の私はネットで本を買うばっかりで、本屋にはめったに行かなくなった。
昨年暮れ、久しぶりに立ち寄ったら、入口付近の最も目立つ棚に、ドラッカーの本などと一緒に平積みにされている白い本があった。やっぱりマネージメントか何か、そっち系の本なんだろうな、と軽く考えてふと書名を見たら『これからの「正義」の話をしよう』。え? 金儲けに「正義」が関係あるわけ? そんなのにこだわっていたら、商売の障りになるばかりじゃないか?
と不審に感じ、著者名を見たらマイケル・サンデル。え? あの? 『自由主義と正義の限界』の? それじゃあ、政治哲学だよな、どうしてそんな本がこんな、売れ筋商品を並べる場所にあるわけ? と、つられて、私は、表紙の、帯を見た。「NHK教育テレビにて放送!」「ハーバード白熱教室in東京大学(仮)」。
つまり、ハーバード大でサンデル教授の講義の人気は高く、ついにTV放送されるに及んだ、それは日本でも放映され、サンデル自身、東大へ来て出前授業をした、とのこと。
後日私は、何人もの知人がこの番組を見ていたことを知った。我が家のチャンネル権は、まず五歳の息子が握っており、次が家内、最後が私で、この序列最下位の者が好きな番組を見る機会はごく僅か。自然、TVそのものへの関心も薄くなって、私はこのような番組の存在を全く知らなかった。従って、授業者としてのサンデルの腕前のほどについては何も分からない。今後DVDか何かで、番組を見る機会はあるかも知れないが、それを自分の授業で生かせるかどうか、まあ、望みは薄い。
しかし、いくらわかりやすく書いてあって、TVの(結果としての)宣伝はあったとはいえ、このような本がベストセラーになるというのは、いまだに不思議である。これは私が世間の人をみくびり過ぎていたということか。客観的には望みは薄い、としか依然として思えないが、今後は生徒をなんとか乗せる手立てをもう一工夫してみよう。
サンデルの講義はその名も「正義」Justiceと名付けられているとのこと。この講義名は日本では考えられないだろうな。中身は、多くは実際にあった、いろいろな事例を出して、「何が正義か」を学生たちに考えさせ、議論させる、と。それはきっと面白いだろう。結論は出ないだろうし、学生たちが今後生きていくうえでどれくらい役に立つかはやや疑問だが。授業は、やらなくてはならないものなら、面白いに越したことはない。
で、ついに私は買うことにした。
この本は、講義をベースにして、新たに書き下ろされたものだ(同書「謝辞」P.347)。授業の熱気は伝わらないが、とりあえず私は、倫理、というか、「何が正しいか」の話は好きだ。英米系の哲学者が得意らしい「思考実験」(譬え話のようなものを使って、ものごとを考えさせること)も好きだ。事実、面白く読めた。これから述べるいくつかの違和感はあったが、それをも含めて。
一つ私も、サンデル先生の生徒になったつもりで、「何が正義か」について、というより、「何が正義かなんて、なかなかわからない」ことについて、になると思うが、自分の意見を述べよう。読んでくれている人の中で、御親切に、サンデル先生になりかわって、教導してくださる人がいらっしゃったら、よろしくお願い申します。
本書は第一章からして、考える材料を豊富に出している。そのうちの柱は、(1)2004年の夏、甚大な台風被害を被ったフロリダで、実際にあった話と、(2)思考実験のための譬え話としてけっこう有名らしい、「暴走する路面電車」。
コミュニタリアン(共同体主義者)として著名なサンデルは、(1)は自由主義に対する、(2)は功利主義に対する、批判のための例示にするつもりらしい、とは後からわかる。そんなのは知らなくてもいいようなものだけれど、知ってしまうと、そうとしか読めない論述になっている。本であれ講義であれ、一人の人がやる以上、その人格からあるバイアスがかかるのは、どうにも仕方がない。
(1)は、台風通過直後のフロリダで、氷や家庭用発電機や家の修理費用やモーテル代が高騰した話。もちろん便乗値上げも多く、最終的には規制されたが、経済学者の中には、そのような施策は不要である、と唱えた者もいたそうだ。
その理由の第一は原理的なもの。自由主義経済下ではものの値段は需要と供給によって決まるのであって、それは時と場所によって変動するのが当たり前。取引(売り買い)以前に「公正な価格」があるように思うのは、畢竟感情的な問題に過ぎない。
第二は現実的なもので、これによって経済活動を活性化させることができる、ということ。例えば氷が高く売れる見込みがあるなら、多くの業者が増産してフロリダまで運ぶようになるだろう。結果として、被災地の復興が早まる効果が期待できる。
後のほうは、実際にそうなったかどうか、わからないが、ここではそうだった、ということにする。そうだとしても、だから便乗値上げをした業者は正しく、その事態は放置しておくほうがいいのか、となると、少なからぬ人が首をかしげるだろう。人が困っているのにつけ込んで金儲けをする輩に対しては、なんらかの社会的な規制なり罰則が必要なのではないか、と素朴に思えてくる。
いや、罰もまた市場(売り買いの場)によって与えられるから、それ以上のことを考える必要はないのだ、とする立場もあるだろう。高い品物やサービスを売りつけられた消費者は、自由に買える日が来たら、二度とその業者からは買わないかも知れない。ところで、それは当然だ、と思うぐらいには、私たちはこのような際に便乗値上げをする業者はあこぎで、悪しき者だと考えているのだ。
即ち、自由主義が、経済的に完全なレッセフェール(放置主義)で市場万能主義をよしとするとしたら、一般にいつも正しいとはされ得ない。その通り。異論はない。
(2)のほうは少々難しい。純然たる思考実験、つまり仮定の話だ。
仮定1。あなたは路面電車の運転手だ。時速六十マイルで走行中、前方に五人の作業員が線路にいるのを発見する。ブレーキは間に合わない。ふと、右側へそれる待避線が目に入る。そこには一人だけ作業員がいる。この待避線へとハンドルを切れば、五人の命は助けられるが、一人は殺すことになる。あなたならどうするか?
仮定2。あなたは橋の上から、走行している路面電車の前方の線路に、五人の作業員がいるのを見る。あなたの隣にはとても太った男がいた。彼を橋から突き落とせば、その男は死ぬだろうが、電車は止まり、五人の命は助かる。どうするか?
(しかし、特に「仮定2」のほうは、すごい仮定だ。だいたい、ぶつかって電車を止められるほどのデブがいるものだろうか。こういうのはデブ差別ではないか、とデブの私などは思うが、もちろんそれは関係ない話)
多くの人が、「仮定1」では、電車を待避線に入れて、一人を殺して五人を助けるほうがいいと考えるだろう。しかし「仮定2」では、デブを突き落として五人助けるのがいいとは思えないだろう(そうですか?)。
しかし、何が違うのか? 両方の場合とも、一人の命を犠牲にして五人の命を救う、という点では変わらない。功利主義は、人の命も計算できるとするから、その立場からは、いつも、一人の命より五人の命のほうに、より(五倍の?)価値があることになる。「仮定1」で一人の犠牲者を出すことが正しい行為なら、「仮定2」でも正しい行為である。そうとしか言えない。
それには同意できないとすれば、功利主義はいつも、一般的に正しいとはされないことになる。う~ん、それはそうか…? でも、これでちゃんと批判したことになるか? いや、それ以前に、前提が少しおかしくないか?
どのような理由からであれ、やむを得ず一人を死なせるのと、積極的に手を下して一人を殺すのでは、やっぱり違う、とは確かに思えるかも知れない。しかしそれこそ、感情の問題ではないだろうか?
では、やっぱりどちらの行為も正しいということになるか? いや、むしろ逆ではなかろうか。「仮定1」の場合、運転手が結果として一人死なせる行為は「やむを得ないこと」として、免責されるのは当然であるとしても、積極的に推奨できる「正しい行為」とまで言えるのだろうか? 感情の問題からすると、あなたが、助かった五人とは赤の他人であり、死ぬことになった一人の友人や家族だったとしても、正しいことがなされたのだからよかったのだと、納得できるものだろうか?
ここで、そんなことを言うなら、(1)の場合だって、規制されたり罰を受けたりする業者やその身内はいやな思いをするじゃないか、と考える人がいるかも知れないので、言葉を重ねよう。このときには、特定の人々の利益や感情を損ねる結果になっても、それを無視して貫くべき「社会的正義」がある、と私は考える。なんと言っても、便上値上げは、自らの意思で行うものだ。しかし(2)は、被害者の意思は全く関係ない。「仮定1」と「仮定2」の違いは、死なせる側の積極性の度合いに過ぎない。片方を是とし、片方を非とするのは、どうにも割り切れないものが残りはしないか?
本書を最後まで読んでも、「仮定1」での結果としての殺人は正しいが「仮定2」ではそうではない、とする根拠は示されない。割り切れなさは宙ぶらりんのまま残される。さらに、それと同じような思いは、本書中のいろいろな場所で反響するのである。













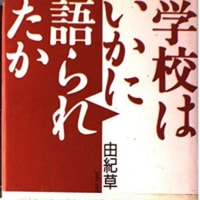
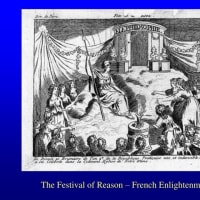










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます