メインテキスト:モーリス・パンゲ、竹内信夫訳『自死の日本史』(筑摩書房昭和61年)
サブテキスト:百田尚樹『永遠の0』(太田出版平成18年刊。講談社文庫版平成21年、平成25年第40刷)
この本は現在文庫の中で一番売れているそうだ。確かによくできた娯楽小説ではある。宮部久蔵という、現実にはまずいないスーパー・ヒーローを物語の中心に据えて、真珠湾奇襲攻撃から沖縄戦まで、日米戦争の一面がうまくまとめられ、描かれている。
宮部は名人の域にまで達した零式戦闘機、通称零戦の操縦士だが、「戦争で死にたくない。生きて妻子のもとへもどりたい」と公言するところが、旧日本軍中では際だって特異なキャラクターになっている。もっとも、よく考えてみると、私も小説や映画からくるイメージ以上のことは知らないのだが、それによると、大東亜戦争中の日本軍では、「命が惜しい」などという言葉はタブーだったようだ(違う、という情報をお持ちの方はご教示ください)。
兵隊がそんな臆病なのでは戦争に勝てないだろう、と言われかも知れないが、それとは異なる観点が示されている。小隊長としての宮部が部下を諭す言葉。
「たとえ敵機を撃ち漏らしても、生き残ることが出来れば、また敵機を撃破する機会はある。しかし―」「一度でも墜とされれば、それでもうおしまいだ」「だから、とにかく生き延びることを第一に考えろ」
戦争に勝つためには、こちらは生きて、多くの敵を殺したほうがいい、だからなるべく生き延びるように心がけるべきだ。これは正論ではないだろうか。美しくないだけに、なおさらそう感じる。山本定朝の言う「武士道と云ふは、死ぬ事と見付たり。二つ二つの場にて、早く死方(しぬかた)に片付くばかり也。別に子細なし。胸すわつて進む也」などは、むしろ平時の武士の心がけを説いたものだ。思うに、戦争とはもっと汚いものなのだ。
汚い話の実例も『永遠の0』中に書かれている。宮部は空中戦で敵機を撃ち落としたとき、向こうの操縦士がパラシュートで脱出するのを見つけたら、それをも機銃で撃った。これが彼の評判を悪くしたもう一つの要因となった。空中戦では、相手の飛行機を破壊すれば終わり、そこから脱出した兵士は、見逃すのが「武士の情け」だと思われていたから。宮部は、そんなものこそ無用な綺麗事だと言う。
「自分たちがしていることは戦争だ。戦争は敵を殺すことだ」「米国の工業力はすごい。戦闘機なんかすぐに作る。我々が殺さないといけないのは搭乗員だ」
実際、戦争の中盤以降、日本軍は武器弾薬から食料医薬品に至るまでの物資面と同じく、あるいはそれ以上に、経験豊かで優秀な戦闘員の不足に悩まされた。特に、まともに戦えるようになるまでには極めて高い練度を要する戦闘機乗りが、ミッドウェイ海戦からガダルカナル島争奪戦を経てマリアナ沖海戦までに至る過程(昭和17年4月~19年6月)で、数多く戦死したことは、太平洋で戦う帝国海軍の首をじわじわと締め付けていった。これを要件の一つとして、特別攻撃作戦、略して特攻、連合軍からはKamikaze Attackと呼ばれて恐れられた、世界の戦史上類のない戦法が実施されたのである。
最初の特攻は昭和19年10月、レイテ沖海戦での神風(当初は「しんぷう」と呼ばれた)特別攻撃隊によるものだった。この隊は20日に結成され、21日から出撃したが、悪天候のためになかなか米艦隊まで到達できず、25日になってから、空母セント・ローに激突、沈没させる、などの成果を挙げている。
当初はこれはこの時限りの、それこそ特別な攻撃だと多くの人が思ったようだが、すぐに常態化した。その経緯は、この25日、第一航空艦隊司令長官大西瀧治郎中将が、マニラ方面にいた飛行隊長以上の指揮者にした説明に、一番簡潔に示されている。森史朗『特攻とは何か』(文春新書)から引用する。
一、(前略)現在の大編隊の攻撃では、攻撃隊は目標を見る前に、敵戦闘機に迎撃され撃墜されてしまう。
二、しかし、索敵機のような単機ないし少数機ならば目標まで接近できる。現に今回敵空母を撃沈した彗星艦爆は単機毎の攻撃であった。
三、だが、現在の技倆では少数機により命中弾を得ることは極めて困難である。しかも、攻撃後の生還はほとんど望みがない。
四、どうせ死ぬならば、体当たりによって大きな損害を与えることこそ本望であろうし、そのような任務を与えることこそ慈悲であると思う。
論理的、ではありますな。この時点で帝国海軍最大の目標は、日本列島に迫り来る米艦隊をなんとか止めることになっていた。しかしそのために多数の攻撃機を行かせたのでは、敵艦隊にたどり着く前に発見されて撃ち落とされてしまう。少数ならたどり着けるが、それでも敵の援護機や艦隊からの砲撃でこれまた撃ち落とされてしまう。さらに、促成した現在の多くの搭乗員(多くは昭和18年から徴兵された学徒兵が充てられた)には、敵艦に爆弾を当てるほどの技術がない。つまり、海戦のために打つ手はもはや、ない。まだしも有効なのは、飛行機ごと艦船にぶつかり、損害を与えることだ。「どうせ死ぬならば」…。日本の兵(つわもの)が、本当に「大君の辺にこそ死なめ」を念願するなら、ここがロドスだ、さあ跳べ! と文字通り命懸けの跳躍が行われた。
言い換えると、なすすべもなくアメリカ軍に撃ち落とされるばかりなら、命と引き替えに一矢報いる道を与える、それが「慈悲」だ、と言ったとき、大西は、いや日本軍全体が、ある一線を越えた。狂瀾を既倒に廻らす方途を論理的に詰めていって、いわばそれを助走にして、倫理の壁を跳び越えたのだ。そのことを大西は自覚していたのだろうと思う。何しろ後に、これは「統率の外道」=「外道の戦法」だと漏らしたと言われているくらいだから。上の説明の最後には、「この案に反対する者は叩き斬る」と言い放ったらしいが、それもつまりは後ろめたさを感じていたからではないだろうか。自分の正しさに充分な自信があるなら、反対者を一人一人粘り強く説得しようとしただろう。
別人の例。昭和20年4月、沖縄に来襲した米軍に対する菊水作戦が始まると、第五航空艦隊長官宇垣纏(うがき まとめ)中将は旗下の全機に特攻を指示した。出撃時には可能な限りはなむけの言葉を贈ったのだが、その折一人の准士官が、「本日の攻撃において、爆弾を百パーセント命中させる自信があります。命中させた場合、生還してもよろしゅうございますか」と尋ねた。宇垣は「まかりならぬ」と、即座に大声で答えた(岩井勉『空母零戦隊』より)。
この准士官が言葉通りの技倆の持ち主だったとしたら、複数の敵艦を撃破できたかも知れない。特攻では最良で一機につき一艦撃沈のみに決まっている。戦術としてこれを見れば、この場合は明らかに損なのだ。しかし、大西や宇垣にとって、もうそういう問題ではなくなっていた。兵を、あくまで兵として、美しく死なしめること。それが戦争に勝つことより大事だった。それで初めて、全体として果たしてどれくらいの戦果があるのかを度外視して、特攻作戦を継続できる。
逆に、たいして有効ではないから、という理由でこの作戦を見直すとしたら、今までに死んだ隊員は無駄死にだ、と見えてしまうだろう。つまり、跳び越えてしまった以上、もう元にはもどれなかったのである。もっとも、特攻を推進した軍幹部の中でも、そう理解していたのはごく少数だったらしい。
大西瀧治郎は、8月16日に、腹心だった児玉誉士夫からもらった刀で割腹自殺し、宇垣纏はそれより早く15日正午の玉音放送を聞いた後で、艦上爆撃機(略して艦爆)彗星に乗って、僚機十機を従えて最後の特攻として沖縄沖へ飛び立っていった。これを責任のとりかただとすれば、「多くの若者の命を奪っておいて、老人が腹を切ったぐらいでなんだ」という意見も出るだろう。それは『永遠の0』にも書かれているが、私はむしろ、彼らは自分たちの作った美しい物語の内部に入り込んでしまっていたので、死をもってそれを完結する以外にない、そういう心境だったのだと考えている。
ただ、生身の人間が、過酷な物語の中に敢えて止まって最期を迎えるのは、いつの時代でも難しい。だからこそ、英雄は希少な存在なのだ。この二人以外の特攻指導者の多くは、けっこう戦後まで生き延びてしまっている。因みに陸軍では、この理由で自決した将官は一人もいない。
それなら、「慈悲」をかけられて、若い命を散らしていった特攻隊員達は英雄なのだろうか。そうとしか言いようがない。英霊、確かに彼らはそう呼ばれるに相応しい存在ではあった。どういう意味で? 自己犠牲の化身として。
多数とは言えなくても、価値ある何かのために自分の身を捧げる高名な、あるいは無名の英雄は、どこにでも、いつの時代でも、いる。今年我々は、猛吹雪の中、幼い娘を庇って、自分は凍死した父親のニュースを知らされた。その荘厳さに心をうたれない人は稀だろう。それでこのような物語はアメリカ映画「タイタニック」(ジェームズ・キャメロン監督)や「アルマゲドン」(マイケル・ベイ監督)など、エンターテインメントにも多数取り上げられ、見る人の涙を誘ってきた。ネタバレになるが、『永遠の0』もまた、日本軍や特攻作戦そのものは批判しながらも、主人公に自己犠牲の死を遂げさせて、ヒーロー像の画竜点睛としている。
これでもわかるように、戦争という、人命を軽んじなければならない際でも、積極的ないわゆる捨て身の働きはしばしば感動的に語られる。それも日本のお家芸ではない。ミッドウェイ海戦時、対空砲火に被弾したSB2Uヴィンディケ-ター機のリチャード・E・フレミング大尉は重巡洋艦三隅に激突した。そうしなくても死んだ可能性が高いのだろうが、そうだとしても体当たり攻撃など、なかなかできることではない。アメリカ人にとってもそうである証拠には、彼には死後に名誉勲章が贈られているそうだ。
この延長上に特攻隊員も当然位置づけられる。モーリス・パンゲはこう言っている。
敵だけでなく、平和の到来を今か今かと待っているすべての人々が、彼らのその行為が戦争を長引かせていると思って、それを狂信だと言い、狂乱だと言って非難した。だが人の心を打つのは、むしろ彼らの英知、彼らの冷静、彼らの明晰なのだ。震えるばかりに繊細な心を持ち、時代の不幸を敏感に感じとるあまり、おのれの命さえ捨ててかえり見ないこの青年たちのことを、気の触れた人間と言うのでなければ、せいぜいよくて人の言いなりになるロボットだと、われわれは考えてきた。(中略)しかし実際には、無と同じほどに透明であるがゆえに人の目には見えない、水晶のごとき自己放棄の精神をそこに見るべきであったのだ。心をひき裂くばかりに悲しいのはこの透明さだ。(P.346)
特攻隊員の遺書に折々見出すことができる不思議な清澄さを評するのに、私はこれ以上の言葉を知らない。それにまた、私のような凡庸な俗人は、この「水晶のごとき自己放棄の精神」など生涯無縁であろうと、すぐに得心できる。
そういうわけで、私などとは精神の次元を異にする英雄がいることには同意するのだが、その前提として、パンゲが、特攻隊員の死は自由意志によるものだった、と言うのには異論がある。と、言うより、それが強制されたのか自発的だったのか、などという議論には意味がないと思う。それはパンゲにもわかっていたのではないだろうか。彼はこうも言っているのだ。「太平洋戦争が何か新しい物をもたらしたとするならば、それは〈意志的な死〉の計画化というものであった――あらゆる自由を組織化することに血道をあげている現代という時代に、それはいかにも似合いの発明品であった」(P.341)
最初の時には大西が確かに彼らが志願するかどうか尋ねている。後にもそういうことはあった。志願する者は皆の前で態度を明らかにするのではなく、紙に名前を書いて提出したり、一週間以内に指揮者に個人的に申し出たケースもある。しかしいずれにせよ、特攻も何度も繰り返され、人間魚雷回天によるものなどを加えて戦死者が五千人以上にも及んだということは、この作戦がシステム化され、ルーティン化された、ということである。
特攻隊員は、システムに乗って、いわば自動的に死んだのである。作戦上の効果もそうだが、彼らの死の意味、つまりは生の意味が考慮されることなどあるべくもなかった。そこで彼ら一人ひとりがそれこそ必死で考えたことのいくつかが、遺言として残され、後の我々を粛然とさせる。
それにつけても、これはやっぱり外道の戦術であり、最悪のシステムだったと思う。『永遠の0』では、軍上層部は一般兵士など将棋のコマぐらいにしか考えていなかった、と批判されている。それは、戦争である以上、いつの時代でも、どの国でも、幾分かはそうなるだろう。アメリカも、例えば日本に上陸したら兵士の損耗(この言葉だけでも、わかりますわな)はどれくらいに及ぶか見積もった上で、原爆を投下したのだし、日露戦争時の旅順攻撃など、特攻とほとんど変わらない有様だったことは当ブログでも以前に書いた。それでも、紙一重でも、五十歩百歩でも、越えてはならない一線はあるのだと思う。
例えばこう言えばいいだろうか。九死一生の激しい戦いを生き延びた者は、英雄になることがあり、そうでなくても自軍に帰れば温かく迎えられることは期待される。十死零生では、というかそもそも作戦成功の必要条件に自分の死があるのだから、生きていることは失敗でしかない。事実、悪天候や飛行機の不調で基地に戻ってきた隊員たちは、たいへんな焦燥を感じなければならなかったようだ。生を根底から否定するようなこんな試みは許されない。それを我が国はかつてやったのだ。大東亜戦争の反省として、第一に銘記すべきことであろう。
サブテキスト:百田尚樹『永遠の0』(太田出版平成18年刊。講談社文庫版平成21年、平成25年第40刷)
この本は現在文庫の中で一番売れているそうだ。確かによくできた娯楽小説ではある。宮部久蔵という、現実にはまずいないスーパー・ヒーローを物語の中心に据えて、真珠湾奇襲攻撃から沖縄戦まで、日米戦争の一面がうまくまとめられ、描かれている。
宮部は名人の域にまで達した零式戦闘機、通称零戦の操縦士だが、「戦争で死にたくない。生きて妻子のもとへもどりたい」と公言するところが、旧日本軍中では際だって特異なキャラクターになっている。もっとも、よく考えてみると、私も小説や映画からくるイメージ以上のことは知らないのだが、それによると、大東亜戦争中の日本軍では、「命が惜しい」などという言葉はタブーだったようだ(違う、という情報をお持ちの方はご教示ください)。
兵隊がそんな臆病なのでは戦争に勝てないだろう、と言われかも知れないが、それとは異なる観点が示されている。小隊長としての宮部が部下を諭す言葉。
「たとえ敵機を撃ち漏らしても、生き残ることが出来れば、また敵機を撃破する機会はある。しかし―」「一度でも墜とされれば、それでもうおしまいだ」「だから、とにかく生き延びることを第一に考えろ」
戦争に勝つためには、こちらは生きて、多くの敵を殺したほうがいい、だからなるべく生き延びるように心がけるべきだ。これは正論ではないだろうか。美しくないだけに、なおさらそう感じる。山本定朝の言う「武士道と云ふは、死ぬ事と見付たり。二つ二つの場にて、早く死方(しぬかた)に片付くばかり也。別に子細なし。胸すわつて進む也」などは、むしろ平時の武士の心がけを説いたものだ。思うに、戦争とはもっと汚いものなのだ。
汚い話の実例も『永遠の0』中に書かれている。宮部は空中戦で敵機を撃ち落としたとき、向こうの操縦士がパラシュートで脱出するのを見つけたら、それをも機銃で撃った。これが彼の評判を悪くしたもう一つの要因となった。空中戦では、相手の飛行機を破壊すれば終わり、そこから脱出した兵士は、見逃すのが「武士の情け」だと思われていたから。宮部は、そんなものこそ無用な綺麗事だと言う。
「自分たちがしていることは戦争だ。戦争は敵を殺すことだ」「米国の工業力はすごい。戦闘機なんかすぐに作る。我々が殺さないといけないのは搭乗員だ」
実際、戦争の中盤以降、日本軍は武器弾薬から食料医薬品に至るまでの物資面と同じく、あるいはそれ以上に、経験豊かで優秀な戦闘員の不足に悩まされた。特に、まともに戦えるようになるまでには極めて高い練度を要する戦闘機乗りが、ミッドウェイ海戦からガダルカナル島争奪戦を経てマリアナ沖海戦までに至る過程(昭和17年4月~19年6月)で、数多く戦死したことは、太平洋で戦う帝国海軍の首をじわじわと締め付けていった。これを要件の一つとして、特別攻撃作戦、略して特攻、連合軍からはKamikaze Attackと呼ばれて恐れられた、世界の戦史上類のない戦法が実施されたのである。
最初の特攻は昭和19年10月、レイテ沖海戦での神風(当初は「しんぷう」と呼ばれた)特別攻撃隊によるものだった。この隊は20日に結成され、21日から出撃したが、悪天候のためになかなか米艦隊まで到達できず、25日になってから、空母セント・ローに激突、沈没させる、などの成果を挙げている。
当初はこれはこの時限りの、それこそ特別な攻撃だと多くの人が思ったようだが、すぐに常態化した。その経緯は、この25日、第一航空艦隊司令長官大西瀧治郎中将が、マニラ方面にいた飛行隊長以上の指揮者にした説明に、一番簡潔に示されている。森史朗『特攻とは何か』(文春新書)から引用する。
一、(前略)現在の大編隊の攻撃では、攻撃隊は目標を見る前に、敵戦闘機に迎撃され撃墜されてしまう。
二、しかし、索敵機のような単機ないし少数機ならば目標まで接近できる。現に今回敵空母を撃沈した彗星艦爆は単機毎の攻撃であった。
三、だが、現在の技倆では少数機により命中弾を得ることは極めて困難である。しかも、攻撃後の生還はほとんど望みがない。
四、どうせ死ぬならば、体当たりによって大きな損害を与えることこそ本望であろうし、そのような任務を与えることこそ慈悲であると思う。
論理的、ではありますな。この時点で帝国海軍最大の目標は、日本列島に迫り来る米艦隊をなんとか止めることになっていた。しかしそのために多数の攻撃機を行かせたのでは、敵艦隊にたどり着く前に発見されて撃ち落とされてしまう。少数ならたどり着けるが、それでも敵の援護機や艦隊からの砲撃でこれまた撃ち落とされてしまう。さらに、促成した現在の多くの搭乗員(多くは昭和18年から徴兵された学徒兵が充てられた)には、敵艦に爆弾を当てるほどの技術がない。つまり、海戦のために打つ手はもはや、ない。まだしも有効なのは、飛行機ごと艦船にぶつかり、損害を与えることだ。「どうせ死ぬならば」…。日本の兵(つわもの)が、本当に「大君の辺にこそ死なめ」を念願するなら、ここがロドスだ、さあ跳べ! と文字通り命懸けの跳躍が行われた。
言い換えると、なすすべもなくアメリカ軍に撃ち落とされるばかりなら、命と引き替えに一矢報いる道を与える、それが「慈悲」だ、と言ったとき、大西は、いや日本軍全体が、ある一線を越えた。狂瀾を既倒に廻らす方途を論理的に詰めていって、いわばそれを助走にして、倫理の壁を跳び越えたのだ。そのことを大西は自覚していたのだろうと思う。何しろ後に、これは「統率の外道」=「外道の戦法」だと漏らしたと言われているくらいだから。上の説明の最後には、「この案に反対する者は叩き斬る」と言い放ったらしいが、それもつまりは後ろめたさを感じていたからではないだろうか。自分の正しさに充分な自信があるなら、反対者を一人一人粘り強く説得しようとしただろう。
別人の例。昭和20年4月、沖縄に来襲した米軍に対する菊水作戦が始まると、第五航空艦隊長官宇垣纏(うがき まとめ)中将は旗下の全機に特攻を指示した。出撃時には可能な限りはなむけの言葉を贈ったのだが、その折一人の准士官が、「本日の攻撃において、爆弾を百パーセント命中させる自信があります。命中させた場合、生還してもよろしゅうございますか」と尋ねた。宇垣は「まかりならぬ」と、即座に大声で答えた(岩井勉『空母零戦隊』より)。
この准士官が言葉通りの技倆の持ち主だったとしたら、複数の敵艦を撃破できたかも知れない。特攻では最良で一機につき一艦撃沈のみに決まっている。戦術としてこれを見れば、この場合は明らかに損なのだ。しかし、大西や宇垣にとって、もうそういう問題ではなくなっていた。兵を、あくまで兵として、美しく死なしめること。それが戦争に勝つことより大事だった。それで初めて、全体として果たしてどれくらいの戦果があるのかを度外視して、特攻作戦を継続できる。
逆に、たいして有効ではないから、という理由でこの作戦を見直すとしたら、今までに死んだ隊員は無駄死にだ、と見えてしまうだろう。つまり、跳び越えてしまった以上、もう元にはもどれなかったのである。もっとも、特攻を推進した軍幹部の中でも、そう理解していたのはごく少数だったらしい。
大西瀧治郎は、8月16日に、腹心だった児玉誉士夫からもらった刀で割腹自殺し、宇垣纏はそれより早く15日正午の玉音放送を聞いた後で、艦上爆撃機(略して艦爆)彗星に乗って、僚機十機を従えて最後の特攻として沖縄沖へ飛び立っていった。これを責任のとりかただとすれば、「多くの若者の命を奪っておいて、老人が腹を切ったぐらいでなんだ」という意見も出るだろう。それは『永遠の0』にも書かれているが、私はむしろ、彼らは自分たちの作った美しい物語の内部に入り込んでしまっていたので、死をもってそれを完結する以外にない、そういう心境だったのだと考えている。
ただ、生身の人間が、過酷な物語の中に敢えて止まって最期を迎えるのは、いつの時代でも難しい。だからこそ、英雄は希少な存在なのだ。この二人以外の特攻指導者の多くは、けっこう戦後まで生き延びてしまっている。因みに陸軍では、この理由で自決した将官は一人もいない。
それなら、「慈悲」をかけられて、若い命を散らしていった特攻隊員達は英雄なのだろうか。そうとしか言いようがない。英霊、確かに彼らはそう呼ばれるに相応しい存在ではあった。どういう意味で? 自己犠牲の化身として。
多数とは言えなくても、価値ある何かのために自分の身を捧げる高名な、あるいは無名の英雄は、どこにでも、いつの時代でも、いる。今年我々は、猛吹雪の中、幼い娘を庇って、自分は凍死した父親のニュースを知らされた。その荘厳さに心をうたれない人は稀だろう。それでこのような物語はアメリカ映画「タイタニック」(ジェームズ・キャメロン監督)や「アルマゲドン」(マイケル・ベイ監督)など、エンターテインメントにも多数取り上げられ、見る人の涙を誘ってきた。ネタバレになるが、『永遠の0』もまた、日本軍や特攻作戦そのものは批判しながらも、主人公に自己犠牲の死を遂げさせて、ヒーロー像の画竜点睛としている。
これでもわかるように、戦争という、人命を軽んじなければならない際でも、積極的ないわゆる捨て身の働きはしばしば感動的に語られる。それも日本のお家芸ではない。ミッドウェイ海戦時、対空砲火に被弾したSB2Uヴィンディケ-ター機のリチャード・E・フレミング大尉は重巡洋艦三隅に激突した。そうしなくても死んだ可能性が高いのだろうが、そうだとしても体当たり攻撃など、なかなかできることではない。アメリカ人にとってもそうである証拠には、彼には死後に名誉勲章が贈られているそうだ。
この延長上に特攻隊員も当然位置づけられる。モーリス・パンゲはこう言っている。
敵だけでなく、平和の到来を今か今かと待っているすべての人々が、彼らのその行為が戦争を長引かせていると思って、それを狂信だと言い、狂乱だと言って非難した。だが人の心を打つのは、むしろ彼らの英知、彼らの冷静、彼らの明晰なのだ。震えるばかりに繊細な心を持ち、時代の不幸を敏感に感じとるあまり、おのれの命さえ捨ててかえり見ないこの青年たちのことを、気の触れた人間と言うのでなければ、せいぜいよくて人の言いなりになるロボットだと、われわれは考えてきた。(中略)しかし実際には、無と同じほどに透明であるがゆえに人の目には見えない、水晶のごとき自己放棄の精神をそこに見るべきであったのだ。心をひき裂くばかりに悲しいのはこの透明さだ。(P.346)
特攻隊員の遺書に折々見出すことができる不思議な清澄さを評するのに、私はこれ以上の言葉を知らない。それにまた、私のような凡庸な俗人は、この「水晶のごとき自己放棄の精神」など生涯無縁であろうと、すぐに得心できる。
そういうわけで、私などとは精神の次元を異にする英雄がいることには同意するのだが、その前提として、パンゲが、特攻隊員の死は自由意志によるものだった、と言うのには異論がある。と、言うより、それが強制されたのか自発的だったのか、などという議論には意味がないと思う。それはパンゲにもわかっていたのではないだろうか。彼はこうも言っているのだ。「太平洋戦争が何か新しい物をもたらしたとするならば、それは〈意志的な死〉の計画化というものであった――あらゆる自由を組織化することに血道をあげている現代という時代に、それはいかにも似合いの発明品であった」(P.341)
最初の時には大西が確かに彼らが志願するかどうか尋ねている。後にもそういうことはあった。志願する者は皆の前で態度を明らかにするのではなく、紙に名前を書いて提出したり、一週間以内に指揮者に個人的に申し出たケースもある。しかしいずれにせよ、特攻も何度も繰り返され、人間魚雷回天によるものなどを加えて戦死者が五千人以上にも及んだということは、この作戦がシステム化され、ルーティン化された、ということである。
特攻隊員は、システムに乗って、いわば自動的に死んだのである。作戦上の効果もそうだが、彼らの死の意味、つまりは生の意味が考慮されることなどあるべくもなかった。そこで彼ら一人ひとりがそれこそ必死で考えたことのいくつかが、遺言として残され、後の我々を粛然とさせる。
それにつけても、これはやっぱり外道の戦術であり、最悪のシステムだったと思う。『永遠の0』では、軍上層部は一般兵士など将棋のコマぐらいにしか考えていなかった、と批判されている。それは、戦争である以上、いつの時代でも、どの国でも、幾分かはそうなるだろう。アメリカも、例えば日本に上陸したら兵士の損耗(この言葉だけでも、わかりますわな)はどれくらいに及ぶか見積もった上で、原爆を投下したのだし、日露戦争時の旅順攻撃など、特攻とほとんど変わらない有様だったことは当ブログでも以前に書いた。それでも、紙一重でも、五十歩百歩でも、越えてはならない一線はあるのだと思う。
例えばこう言えばいいだろうか。九死一生の激しい戦いを生き延びた者は、英雄になることがあり、そうでなくても自軍に帰れば温かく迎えられることは期待される。十死零生では、というかそもそも作戦成功の必要条件に自分の死があるのだから、生きていることは失敗でしかない。事実、悪天候や飛行機の不調で基地に戻ってきた隊員たちは、たいへんな焦燥を感じなければならなかったようだ。生を根底から否定するようなこんな試みは許されない。それを我が国はかつてやったのだ。大東亜戦争の反省として、第一に銘記すべきことであろう。













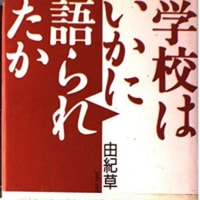
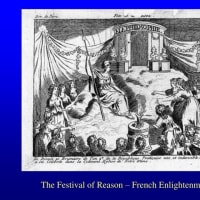










「道徳的な死のために」(その2)を読みました。そして、私の百田尚樹(ひゃくたなおき) 『永遠の0』 の読後感との比較を試みました。当初は、由紀さんとは、この本の評価において、少し衝突するかも知れないな、と思っていました。なぜなら、私のこの本への評価は高いものでなかったからです。また、私は大東亜戦争のことについて見聞きすることがあると、何か情念のようなものに襲われます。思い入れが強いのです。自制を課しているのですが、この本を読んでいても、何か、心の中にフツフツと湧いてくるものがあり、本を置くことがしばしばでした。やっとのことで読み終わり、ブログを恐る恐る読んだのですが、予想にたがい、違和を感ずることがほとんどなく、大方は納得の行くものでした。のみならず、今回のブログはとても読みやすく、質が高かったと感じます。また抑制の効いたものである気がしました。
主題である特攻に関しては、「紙一重でも、五十歩百歩でも、越えてはならない一線はあるのだと思う」「生を根底から否定するようなこんな試みは許されない。それを我が国はかつてやったのだ。大東亜戦争の反省として、第一に銘記すべきことであろう」という結論に共感を覚えます。ことに「システム化し、ルーティン化された」時点で、きわめて不愉快なものです。但だ、その死が無駄であったかというと、必ずしもそうは思わないので、特攻に対する総合的な評価は保留させてください。
同時に小浜逸郎氏の『永遠の0』に関する一連のブログも読んでみました。軽く書き流したものかも知れませんが、私が今まで読んだ氏の文章の中では、最も感銘を受けたものの一つとなりました。アニメ「風立ちぬ」に関する箇所も、とても美しい印象を私に残しました。こうした由紀さんと小浜氏の評を読んだあとに、何をか言はんという気もしますが、少々異なっているかも知れない点を述べたいと思います。
読み始めてすぐに理解したのは、スーパーヒーローである主人公、宮部久蔵がまさしく現代人であるということでした。そしてその主人公の思想は端的に言って、命と家族が大切、というものです。現代の読者に対しては、この二者さえ担保しておけば、大方の賛同は得られることでしょう。また、負けないこと、死なないことが肝要、と宮部は言います。由紀さんの引用を利用すれば、「たとえ敵機を撃ち漏らしても、生き残ることが出来れば、また敵機を撃破する機会はある。しかし─」「一度でも墜とされれば、それでもうおしまいだ」「だから、とにかく生き延びることを第一に考えよ」と語ります。そして彼の部下は、「生き残るということがいかに大切なものであるかということを百万の言葉より教えられた気がしたのです」と語り、そのお蔭で生き残ったと回顧するわけです。しかし、由紀さんが言われるように宮部の言葉は正論なのでしょうか。私には疑問が残りました。
揚げ足取りであったら指摘していただきたいし、本質を外しているなら申し訳ないのですが、「俺は死なないぞ。故郷へ帰るんだ」と内心に決意する兵は多くいたと思います。いや、ほとんど全員だったのではないか、と想像します。しかし、軍人が一般に「とにかく生き延びることを第一に考えよう」と決意したら、軍隊は成り立つまいと考えました。最初に「死」地に就くのはいったい誰なのでしょうか。今は確かに無人偵察機を飛ばして、長距離ミサイルでピンポイント攻撃をするという、とても「合理的な」戦術が生み出されています。しかし、それができない場合、最初に飛び込んでいく人間は必要だし、近代戦でも殿軍(しんがり)に相当する任務はあるでしょう。これは誰がやるのか。可能だったら避けよということか。少なくとも志願はするなということか。それとも慎重であれというだけのことなのか。単純なことですが、宮部にそれを聞いてみたい気がしました。
たとえば、南京城の城壁が目の前にあったら、誰かが先頭をきってよぢ登らなければなりません。皆で譲り合っていたら永遠に南京城は陥落しません。そこへ飛び込もうする若者がいたら、宮部は言うのでしょうか。「お前が死んだところで、戦局は変わらない。しかし──お前が死ねば、お前の妻の人生は大きく変わる」「貴様には家族がいないのか。貴様が死ぬことで悲しむ人間がいないのか。それとも貴様は天涯孤独の身の上か」「どんなに苦しくとも生き延びる努力をしろ」と。そして、若者はハッと何ものかに気づいてやめる。「自分と家族が一番大切なんだ」と頓悟するわけです。しかし、その間にも、他の部隊は「お国のために」と言って、死に「もの狂い」でとびこんで行ったことでしょう。
私は宮部久蔵の人物造形に少し無理があると考えています。よって明確なことは言えませんが、宮部が単に暴虎馮河(無謀で、命知らずな行動)を戒めている人物とは思われませんでした。本心かどうかは分かりませんが、宮部自身が「私は帝国海軍の恥さらしですね」と苦笑しています(87頁)。少なくとも宮部の臆病には、妻や子への思いが関わっているようです。国や郷土のために死ぬ、ではなくて、親や妻子のために死ねない、という戦後に生じた新しい発想です。この現代人である主人公が現代人の読者の常識に訴えながら、旧陸海軍を批判するという、この小説の結構を私は好みません。
私が、普段、祈るような気持ちをもっているのは、その時代、その瞬間の美意識に殉じた将兵たちに対してです。彼らは、ある意味で、今も私の中で生きていると言えます。それに対し、宮部は彼の愛する妻と子とに余りに強くつながっていた。ただその分、またイデオロギーの少ない分、後世の私にはほとんど無縁の死を死んだと言えるでしょう。
百田氏のこの作品は、危険をとにかく避けよう、そして家族のもとに無事に帰るのが一番だとする同世代の哲学とあまりに適合していて、その点は見事だと思いました。歴史小説、エンターテイメント、ベストセラーとはこういうものなのかと考えました。とは言いながら、この作品の最後で思わず落涙してしまったのは不覚でした。
偶々この秋、北伊勢陸軍飛行場跡にて聞きし練習生の話を思い出して
かむかぜの伊勢のあをそら飛びゆきて
遠く消ゆなるその機影はも
お答えとして、ほぼ御同感いただいた部分はよいとして、「少々異なっている」ところについて少し云々いたします。
宮部久蔵は現代人であるとのこと、これはどうでしょうか。いや、そうではない、と言うより、彼はスーパーヒーローとして、一種の理想像であって、戦前も戦中も戦後も、どこにもいない人なんじゃないでしょうか。
おっしゃるように、「生きて故郷へ帰りたい」と考えていた兵士は決して珍しくないでしょう。「妻や子のために生きて帰る(帰りたい)」という人だって、いたでしょう。そういう気持ちに戦前も戦後も変わりがあるはずはありませんし、世間的な道徳からしても、戦争でさえなければ、例えば雪山で遭難した、というような場合、「家族がたいせつだから一所懸命がんばって生還した」という人は、戦前でも賞賛されこそすれ、決して非難はされなかったのではないでしょうか。
それが命の遣り取りをする戦場ではどう働くか、というところで、命は惜しいけれど、決して逃げはしない人物が創造された。するとどうなるか。生き延びるためには敵を倒すしかない。それができるだけの技倆があったおかげで、彼は、矛盾なく優秀な軍人になるわけですね。全く矛盾がないところが、まあ作り物であるわけでして。
実際の話としても、例えば最初の特攻兵と知られている関行男大尉は、報道記者に向かって、「僕は天皇陛下のためとか、日本帝国のためとかで行くんじゃない。最愛のKA(軍隊の隠語で、妻のこと)のために行くんだ。日本が敗けたらKAがアメ公に強姦されるかもしれない。僕は彼女を護るために死ぬんだ。最愛の者のために死ぬ。どうだ、素晴らしいだろう」と言ったそうです(ウィキペディアによる)。生きていたほうが奥さんだって守れるだろうに、なんて思えるところが矛盾ですが、矛盾しているだけに現実的ですね。
それはともかく、国家より家族が大事、という観念は、この頃からあったのは間違いないでしょう。それでもちゃんと戦争はできるのです。
次の点に移ります。一口に戦場と言っても、非常に危険なところと、そうでもないところの区別があったのは本当でしょう。自分の命が一番大切な者なら、危険な場所での危険な任務はなるべく人任せにしようとするんじゃないか、と。それはその通りですし、実際にそういう者もいたでしょう。現に、部下に特攻を命じながら自分は戦後まで生き延びた多くの将校はみんなそうだと言っていい。
こういう人は臆病というより卑怯に見えるんで、とうていヒーローにはなれない。そこで宮部は、自分が護衛しながらなすところもなく敵機や敵艦隊の砲撃で死んでいく未熟な搭乗員たちを座視するに忍びない人物として描かれてもいる。で、最後は、自分をかばって死にかかった者のために、身代わりになって死ぬ。これもまた、あまりに都合よくできた、お話みたいなお話だ。まあ仕方ない、お話なんだから。
それでも、W.H.さんもそうでしょうが、命は惜しいにしても、人を犠牲にしてまで生き延びるまではできない、という人は、今でも、必ずいます。そういう人には私としても、深甚な敬意を払いますし、自分も、怪しいですけど、できればそうありたいと思う。それ以上は、少なくとも国家は、要求できないと考えています。それだけでも国家は保つんじゃないか、とも。
それで、何しろ軍隊というのは、全体として、味方の損害はなるべく減らして、敵を破ることを専一に考えるべきところでしょう。日露戦争時の旅順攻略戦で、ベトン(コンクリート)で塗り固めた要塞に白兵戦を挑んで、機関銃の一斉掃射で斃れていった日本兵を思うと、私としても自然に目頭が熱くなります。しかし、そんなことをしていたんでは戦争には勝てない。これも冷厳な事実でしょう。
やがて乃木軍も、塹壕を掘り進めてそこに身を潜めつつ攻撃する方法は学んだようですし、司馬遼太郎によるとですが、児玉源太郎が内地から取り寄せた攻城砲を使って四日で陥落させた、と。これには異論も多いようで、真実は知りませんが、何しろ、合理的に戦争に勝つことを専一に研究するのが軍隊の役割のはずです。大和魂の鼓吹なんて、他にまかせてもいい。気持ちだけで戦争に勝てるぐらいなら、最初から軍隊なんていらない道理ではないですか。
以上は拙著『軟弱者の戦争論』に書いたことの繰り返しですが、その時からして、自分の言っていることは無理があることは自覚しておりました。人間が完全に合理的にふるまえるものなら、そもそも戦争なんて起きないでしょうから。
それでも、戦争という「最も危険な事業」(クラウゼヴィッツ)を遂行するためには、心はどんなにホットであったとしても、頭は可能な限りクールでないと、無駄な犠牲ばかり大きくなってしまう、これは本当であろうと信じます。
たぶんW.H.さんと私では、上に書いたようなことで、どうしても相容れないところがあるのでしょう。それは議論しても埋まらないとしても、お互いに尊重し合って、考えを深めていくことはできると思います。今後とも宜しくお願いしたいです。