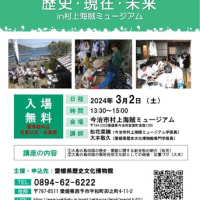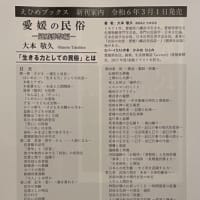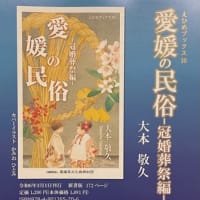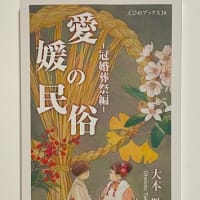明けましておめでとうございます。正月・年始めには、つい「暦」を見て、今年の運勢を知りたいと思ってしまいます。もともと暦は、語源が「日(か)読み」とも言われ、今日が何月何日ということを理解するために作られたと同時に、その日がどのような日か、吉なのか凶なのかを知ることも重要視されていました。今回は、暦に記載された吉凶判断の歴史の一端についてご紹介します。
現代の人は、暦を見て、結婚式は「大安」の日をえらんで、お葬式は「友引」の日をさけることが多いですね。これが昔からの「当たり前」だと思ったら、じつは、違うのです。江戸時代の暦(カレンダー)を見わたしても、「大安」や「仏滅」、「友引」など(これを六曜といいます。)は出てきません。暦(カレンダー)に六曜が記載されるのは、明治時代以降の民間暦であり、「大安」や「仏滅」などは近代以降に信じられるようになったものです。江戸時代以前には、百科事典のような何事にも詳しい書物には、以下のように出てきますが、一般庶民は気にしていなかったようです。
①『事林広記』(中国の宋時代)・・・大安・留連・速喜・赤口・小吉・空亡、②『和漢三才図会』(江戸時代中期)・・・大安・留連・速喜・赤口・小吉・空亡、③『天保大雑書万暦大成』(江戸時代後期)・・・先勝・友引・先負・物滅・泰安・赤口、④現在・・・先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口。
この①から④を比較してみると、「大安」は、江戸時代後期には「泰安」とも書かれます。また、「仏滅」は、江戸時代後期には「物滅(ぶつめつ)」と出てきますが、「物が滅する」と同じような意味で、江戸時代中期以前には「空亡」と呼ばれていました。現在のように「仏が滅する」ので縁起が悪いといわれるようになったのは、明治時代以降のことのようです。
さらに、「友引」は「ともびき」とも「ゆういん」とも呼びますが、これは江戸時代中期の「留連(りゅうれん)」が訛ったものです。現在のように、「友引」は災いが友人にも及ぶので、葬儀は行わないなどとは、江戸時代以前の庶民は考えることはなかったのです。
「大安」・「仏滅」・「友引」などの六曜が流行するきっかけは、明治五年十二月三日を明治六年一月一日とした「改暦」、つまり太陰太陽暦(旧暦)から太陽暦(新暦)への暦法の変更といわれています。その改暦の法令の中に、暦注(吉凶の記述)の廃止が含まれていました。それまでは、八専(はっせん)・十方暮(じっぽうぐれ)・犯土(つち)など、日々の吉凶判断が暦(カレンダー)に記載されていたのですが、明治六年以降に政府が発行する暦からは、吉凶判断は消えてしまいました。
この暦注廃止のために吉凶を知ることができなくなり、庶民は困惑してしまいます。そこで明治時代中期以降には、政府発行の暦だけではなく、吉凶判断を記載した暦が民間から発行されるようになります。その中に、江戸時代の暦には記載がなかった「大安」・「仏滅」などの六曜も記載されるようになってきます。これをきっかけに、それまで一般的でなかった六曜を、人々が日々の吉凶判断に使い始め、戦後になって定着していったのです。(ちなみに、皇室の結婚式で「大安」を選ぶようになったのも戦後の昭和三十四年からです。)このように、吉凶を知りたいという願望は、人間のごく普通の心意ではあり、それを知ることで精神的に安心できる効用もあります。ただ、吉凶知識自体、時代に伴う変化が激しいものです。その点だけはご注意を!
皆様にとって、今年も一年、良い年でありますように。
南海日日新聞 2008年1月1日付掲載
現代の人は、暦を見て、結婚式は「大安」の日をえらんで、お葬式は「友引」の日をさけることが多いですね。これが昔からの「当たり前」だと思ったら、じつは、違うのです。江戸時代の暦(カレンダー)を見わたしても、「大安」や「仏滅」、「友引」など(これを六曜といいます。)は出てきません。暦(カレンダー)に六曜が記載されるのは、明治時代以降の民間暦であり、「大安」や「仏滅」などは近代以降に信じられるようになったものです。江戸時代以前には、百科事典のような何事にも詳しい書物には、以下のように出てきますが、一般庶民は気にしていなかったようです。
①『事林広記』(中国の宋時代)・・・大安・留連・速喜・赤口・小吉・空亡、②『和漢三才図会』(江戸時代中期)・・・大安・留連・速喜・赤口・小吉・空亡、③『天保大雑書万暦大成』(江戸時代後期)・・・先勝・友引・先負・物滅・泰安・赤口、④現在・・・先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口。
この①から④を比較してみると、「大安」は、江戸時代後期には「泰安」とも書かれます。また、「仏滅」は、江戸時代後期には「物滅(ぶつめつ)」と出てきますが、「物が滅する」と同じような意味で、江戸時代中期以前には「空亡」と呼ばれていました。現在のように「仏が滅する」ので縁起が悪いといわれるようになったのは、明治時代以降のことのようです。
さらに、「友引」は「ともびき」とも「ゆういん」とも呼びますが、これは江戸時代中期の「留連(りゅうれん)」が訛ったものです。現在のように、「友引」は災いが友人にも及ぶので、葬儀は行わないなどとは、江戸時代以前の庶民は考えることはなかったのです。
「大安」・「仏滅」・「友引」などの六曜が流行するきっかけは、明治五年十二月三日を明治六年一月一日とした「改暦」、つまり太陰太陽暦(旧暦)から太陽暦(新暦)への暦法の変更といわれています。その改暦の法令の中に、暦注(吉凶の記述)の廃止が含まれていました。それまでは、八専(はっせん)・十方暮(じっぽうぐれ)・犯土(つち)など、日々の吉凶判断が暦(カレンダー)に記載されていたのですが、明治六年以降に政府が発行する暦からは、吉凶判断は消えてしまいました。
この暦注廃止のために吉凶を知ることができなくなり、庶民は困惑してしまいます。そこで明治時代中期以降には、政府発行の暦だけではなく、吉凶判断を記載した暦が民間から発行されるようになります。その中に、江戸時代の暦には記載がなかった「大安」・「仏滅」などの六曜も記載されるようになってきます。これをきっかけに、それまで一般的でなかった六曜を、人々が日々の吉凶判断に使い始め、戦後になって定着していったのです。(ちなみに、皇室の結婚式で「大安」を選ぶようになったのも戦後の昭和三十四年からです。)このように、吉凶を知りたいという願望は、人間のごく普通の心意ではあり、それを知ることで精神的に安心できる効用もあります。ただ、吉凶知識自体、時代に伴う変化が激しいものです。その点だけはご注意を!
皆様にとって、今年も一年、良い年でありますように。
南海日日新聞 2008年1月1日付掲載