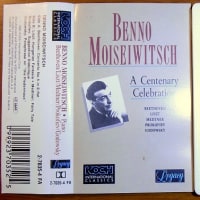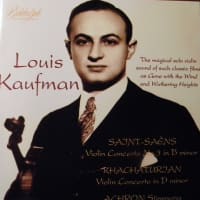今、ここにあるのはオープンリールのテープだが、小学校の頃には同じデザインの箱に入った2枚組のLPアルバムがあった。我が家では、クリスマスになるとこのレコヲドが必ずかかってゐた。
この幻想的なジャケットには、幼い頃を想い出させる様々な小物たちとその場の空気が写ってゐて、故郷を懐かしむやうな不思議な感覚に囚われる。ツリーを飾るガラス玉、キャンドル、モール、ステッキ型のキャンディーやホワイトチョコなど、すべてがロチェスターでのクリスマスの記憶を呼び起こす。米国での生活の思い出は、幼ない頃の記憶として強烈に焼きついてゐるだけでなく、僕の人格の一部を形成してゐる。そして、多くの記憶の中でも特に重要だと思はれることは、食べることやそれを排泄するといった「生」に関わる記憶である。
話は下へと落ちるが、当時の日本は池田内閣による高度経済成長の真っ只中、便所はボットン式の時代で、僕が帰国し羽田空港に降り立って発した一言目が「日本はくさいなあ」だったそうである。ブロッコリーやカリフラワー、「プツンプツン」と命名して遊んだおもちゃの「レゴ」、サーティーワンの「ラムレーズンアイス」、人気TV番組「ベン・ケーシー」などが日本に入ってくるのは、それから十年ほど後のことである。
今でこそ、ウォシュレット付き水洗トイレが当たり前になったが、当時はボットン便所が一般的だった。僕にはこの暗くて深い大穴が恐ろしくて(臭くて)、家ではアヒルの「おまる」を愛用してゐた。学校で大きい方をもよおしでもすれば一大事で、家のアヒルの「おまる」目指してまっしぐらといふことも何度かあった。なんとか家にたどり着いたが、玄関に鍵がかかってゐたため残念な結果に終わったことが一度だけあった。
田舎に遊びに行くと、最近でもボットン式を見かけることがある。この歳になっても子どもの頃の恐怖感は蘇ってくるものだ。早く用を足して外へ出たいといふ一心から、慌てて木製のサンダルを落としてしまったのである。宿の主人に謝る姿は、まるで8歳の少年だった。
新築するに当たっては、トイレの設計には殊のほか神経を使ったのは言ふまでもない。ムソルグスキーのやうに、トイレで昇天しても悔いの残らぬやう、手塚治虫氏の貴重なコミック本のコレクションを置き、壁紙、壁に掛ける絵画やフレグランスにもこだわり、家の中のどの部屋よりもくつろげる空間にした。
今日は、アンセルメの「胡桃割り人形」に触発されて、この半世紀のトイレの変遷に思いをめぐらせてゐた。

写真は、ロチェスターのツリーを飾ったガラス玉、割れずに残った最後の1個。
音源は、米国London 7インチオープンリール LCK-80027。
この幻想的なジャケットには、幼い頃を想い出させる様々な小物たちとその場の空気が写ってゐて、故郷を懐かしむやうな不思議な感覚に囚われる。ツリーを飾るガラス玉、キャンドル、モール、ステッキ型のキャンディーやホワイトチョコなど、すべてがロチェスターでのクリスマスの記憶を呼び起こす。米国での生活の思い出は、幼ない頃の記憶として強烈に焼きついてゐるだけでなく、僕の人格の一部を形成してゐる。そして、多くの記憶の中でも特に重要だと思はれることは、食べることやそれを排泄するといった「生」に関わる記憶である。
話は下へと落ちるが、当時の日本は池田内閣による高度経済成長の真っ只中、便所はボットン式の時代で、僕が帰国し羽田空港に降り立って発した一言目が「日本はくさいなあ」だったそうである。ブロッコリーやカリフラワー、「プツンプツン」と命名して遊んだおもちゃの「レゴ」、サーティーワンの「ラムレーズンアイス」、人気TV番組「ベン・ケーシー」などが日本に入ってくるのは、それから十年ほど後のことである。
今でこそ、ウォシュレット付き水洗トイレが当たり前になったが、当時はボットン便所が一般的だった。僕にはこの暗くて深い大穴が恐ろしくて(臭くて)、家ではアヒルの「おまる」を愛用してゐた。学校で大きい方をもよおしでもすれば一大事で、家のアヒルの「おまる」目指してまっしぐらといふことも何度かあった。なんとか家にたどり着いたが、玄関に鍵がかかってゐたため残念な結果に終わったことが一度だけあった。
田舎に遊びに行くと、最近でもボットン式を見かけることがある。この歳になっても子どもの頃の恐怖感は蘇ってくるものだ。早く用を足して外へ出たいといふ一心から、慌てて木製のサンダルを落としてしまったのである。宿の主人に謝る姿は、まるで8歳の少年だった。
新築するに当たっては、トイレの設計には殊のほか神経を使ったのは言ふまでもない。ムソルグスキーのやうに、トイレで昇天しても悔いの残らぬやう、手塚治虫氏の貴重なコミック本のコレクションを置き、壁紙、壁に掛ける絵画やフレグランスにもこだわり、家の中のどの部屋よりもくつろげる空間にした。
今日は、アンセルメの「胡桃割り人形」に触発されて、この半世紀のトイレの変遷に思いをめぐらせてゐた。

写真は、ロチェスターのツリーを飾ったガラス玉、割れずに残った最後の1個。
音源は、米国London 7インチオープンリール LCK-80027。