新しい時代の組織のかたちとして、スライム組織なる考え方があることは、既に述べたとおりです(「「スライム組織」のご紹介」参照)。パラダイムシフトという言葉に象徴されるように、環境や社会全体が大きく変化しようとしている時代において、組織における強みは「環境適応力」であるといっていいでしょう。
こうした観点から、既存の縦割り的な組織構造から、より横断的かつ柔軟にリソースを活用しながら組織運営を行おうという試みがなされています。プロジェクト制の導入などは、そうした試みのひとつだろうと思われます。プロジェクト制は、たとえば企業組織でいうところの「人事」、「経理」、「営業」、「技術」などの各組織にのみ拘束されず、横断的かつ柔軟に人員リソースを投入していきながら、環境に即した各プロジェクトを回していくことで、組織全体としての目標を達成していこうというものです。実際に、こうした組織運営をすることで、これまで考えられなかったような環境変化にも対応することができるようになった事例も多いだろうと思います。
ところで、これからの時代においては、これだけでは不十分である可能性があります。何故ならば、これからの時代で起こることは、パラダイムシフトであろうからです。パラダイムシフトが起こる時代においては、環境変化に対応していくこと自体が仕事なのであり、価値として認められることが予見されます。即ち、どんなに変化の連続であろうとも、それにいかに対応できるかという柔軟性が、組織には求められる時代であるということです。
状況に応じて生まれてくる複数のプロジェクトについては、新設、統合、分離、廃止、親プロジェクト化、子プロジェクト化(プロジェクトには親子のような階層関係が存在し得ます。大きなプロジェクトの下には、それを支えるように分解したかたちで子プロジェクトが存在し得ますし、さらにそれらを分解した孫プロジェクトのような概念もあり得ます)といったことが瞬時に行われなければなりません。それだけではなく、これらの各プロジェクトについての進捗状況や課題整理、アクションアイテムはもちろんのこと、各メンバーのリソース配分などについても、プロジェクトの編成に応じて、瞬時にきちんと整理され直されるような柔軟性が要求されるということです。

これまでのようなDBシステムにとって、こうしたプロジェクト管理表の作成は、大変難しいことです。例えば、RDB(リレーショナル・データベース)でプロジェクトを管理しているような場合、2つ以上のプロジェクトを統合しようとするときに生じる作業は、単に「それらを合わせる」というような簡単なものではありません。統合する各プロジェクトの複数項目(フィールド)も、それにあわせて統合させなければなりませんし、当然そのことに応じて、メンバーのリソース管理状況にも、それを反映させなければなりません。こうしたことが少なければともかく、常時、瞬時に対応していく必要があるとなると、極めて難しい問題になります。
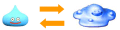
私は、こうした問題を解決するためには、新しいDBシステムが必要であろうと考えています。そこに入力される値は、従来のRDBのように、予めきちんとフィールドを定義して、設定しておくようなものではなく、非常に柔軟なかたちで運用できるという点がポイントになります。もう少し、直感的な表現するならば、従来のRDBでは、対象物を真四角の表(行と列)のようなかたちをするのに対して、この新しいDBはデコボコな3次元として、あるがままに表現することができるということです。これが、私がスライム組織を「3次元」的組織として、概念化する理由です(既に、こうしたDBシステムのコアロジックは存在しています)。
そして、こうした管理ができることで、組織は単に柔軟性を確保するだけでなく、より正確に個人の能力を評価することができるようになるのです。
2:6:2の法則なるものがあります。一般的に組織では、よく働く者、そこそこ働く者、ほとんど働かない者の比率は2:6:2であるというのです。しかし私は、この法則を組織における評価軸が、ひとつのとき(あるいは極めて限られているとき)のものであると理解しています。つまり平面的組織、あるいは画一的な評価軸では、各個人が持つ才能の多様性を捉えることができず、その軸だけで個人の才能を見ざるを得ないため、そのような比率で分類するしかないということです。
逆の言い方をすれば、組織を3次元的に捉え、そこからあらゆる断面(極めて多くの評価軸)で見ることができるようになれば、ひとつの組織のなかにおいて、個人の能力が2:6:2で発揮されている(よく発揮できる、そこそこ発揮できる、ほとんど発揮できない)ことが、映し出される可能性があるということです。つまり、2:6:2と割り切ってしまうのは、評価をする側の都合であって、個人の能力よりも、評価の軸の方が2:6:2の限界を抱えていたということでもあります。
 このことを積極的に解釈すれば、組織が多様な評価軸を持つことで、個人は必ずどこかの軸(全体の約2割)で必ず「よく働く者」に属することになることになります。スライム組織の運営によって、3次元的に組織を捉えることができることのメリットは、単に環境適応力が高いということだけではなく、このように組織を限りなく多くの断面図で捉えることができるということなのです。つまりそれは、個人の能力を多面的に評価する仕組みであるとも言えるわけです。
このことを積極的に解釈すれば、組織が多様な評価軸を持つことで、個人は必ずどこかの軸(全体の約2割)で必ず「よく働く者」に属することになることになります。スライム組織の運営によって、3次元的に組織を捉えることができることのメリットは、単に環境適応力が高いということだけではなく、このように組織を限りなく多くの断面図で捉えることができるということなのです。つまりそれは、個人の能力を多面的に評価する仕組みであるとも言えるわけです。

また各個人が、組織のなかで2:6:2の法則に基づいて、自らの能力を発揮できるということが可視化できるというのは、組織を限りなく「個人の集合体」として捉えるということと同義でもあります。「企業は人なり」などと言ったりしますが、それは単なる概念論ではなく、こうした組織哲学に基づき、確立した管理手法を用いることで、きちんと実践できるのではないかと考えます。














