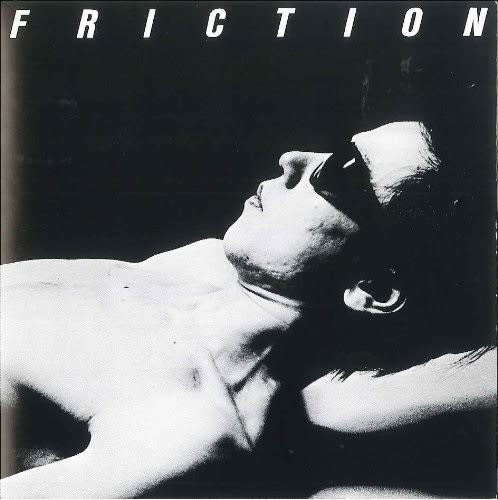月日の流れはいつも性急だが、私の意識は緩慢だろうか。時は容赦しないが私の白昼夢は止む事がない。それで良い。生活の忙しさに埋没する私は社会性という圧力の元、今日も満員電車に駆け込む。それでも白昼夢は続いている。私は現実時間に逆行する術を身につけている。それは永年の音楽時間によって確実に育ってしまった私の中の病でもあるだろうか。しかし感じるのだがそんなデイドリームは性急な時間軸があってこそ、その快楽度が増すのだ。厳しき日常とやらがあってこそ、夢想の深みは増すのである。
ロックミュージックの聖典、ヴェルベットアンダーグラウンドのファーストアルバムの一曲目「sunday morning」はその後、何十年のロックの<気分>を決定づけてしまった。
誰にでも経験があるだろう。日曜の朝だけ訪れる日溜りの中のぼんやりとした空気の暖かさを。カーテンの隙間から差し込む僅かな光の中で半眠のままの心地よさを。ベッドから半身を起こし、たおやかな時間の中で味わう煙草の旨さを。
無意識と意識的自己がせめぎ合い、行動への意欲とそれを引き留める意識のシーソーゲームが繰り返されるあの時間は日曜の朝にだけ許される快楽の時だった。
しかしヴェルベッツはこの曲を僅か三分で終わらせた。夢は終わる。確実に。
デイドリームから現実へと向かう態度。そして再び夢へ。はたまた現実へと。
これは<堕ちる>と<闘う>を交互に循環させる意識だろうか。そんな繰り返しにこそロックの生命線はあると思う。「sunday morning」の歌の本質はここにあるのではないか。
しかし「sunday morning」にある現実逃避としての側面、その表面的なムードはロックの一つの様式となり、この曲の‘気分’をロックは30年以上、大量生産してきた。
MY MORNING JACKETの『AT DAWN』は「sunday morning」の‘気分’を充満させながらも単なるムードミュージックに陥らない芯の太さを感じさせる音楽だ。いつもCDを貸してくれる廣川君から例によって何の予備知識もなしに借りたこのバンド。まるで風呂場で録音したかのようなエコーのかけ方がすごい。(これはリバーブじゃないね。ピンクフロイドやサードイヤーバンドが使っていたようなアナログエコーマシーンみたいだ)この大仰なエコーが白昼夢に誘い込むのだが、元の楽曲が良いので安っぽい感じがしない。この手のバンドサウンドはソングライティングの良し悪しが運命の別れ目だ。
アルバムタイトルの『AT DAWN』という言葉も違和感なく収まっている。
dawn = 黎明、夜明け前、兆し、薄ら灯。
そのタイトルと等しく、その<ぼんやり指数>は最上位まできている。しかしこのバンド、不思議な骨格感がある。曲に芯の太さが感じられ、重量感があるのが気に入った。全ての曲の作者であるJim James。この人は恐らくサイケデリック等は意識の範疇外で、むしろオールドなロックやR&B、ブルースやカントリーの愛好者ではなかろうか。楽曲にそれを感じるし、発声にも正統的なオールドウェイブへの愛や音楽への堅固な態度を感じさせるものがある。
表現力が追いつかず、想念ばかり先行するチープな惰眠空間はオルタナによくあるけど、MY MORNING JACKETは手練れがやる本物の‘まどろみ’を体現した。すごくいいね。
2007.6.10