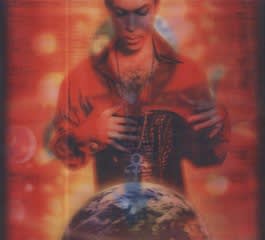シュルレアリスム運動は詩、映像、造形、絵画、パフォーマンスなど様々なジャンルでその‘超現実性’を志向したが、その絵画部門で最も同グループのコンセプト、理念を具現化したのは一般知名度で勝るダリやミロ、エルンストではなく、イブタンギーである事を同運動のリーダー、アンドレブルトンは認めている。それはイブタンギーの絵に見られる徹底された非―既視性の為だと思われる。その絵に登場する謎めいた物体は、‘何物をも想起させない事‘でその‘超現実性’を体現した。
ダリやミロ、エルンスト作品に見られる溶けた時計や山高帽子、鳥獣等はいずれも何かしらの既成物の変形や象徴化であり、デフォルメ的発想を超えていない。対し、タンギーが描くものは未知なる物質、得体の知れぬ微生物、見た事もないような鉱物。アメーバの群れといったもの等で、私達の創造の埒外に在る、‘非―既存性’そのものという感じがする。これは気色悪いほど美しく、不気味なほど魅力的な未知世界であり、‘何物をも想起させないもの’として観る者の想像力を不安にさせ、また刺激する。
突然変異的な物体が無数に飛び交う時に起こる摩擦音のシンフォニー。
オウテカの音楽を私はそんな風に捉えている。
それは極めてタンギー的なシュルレアリスム世界を音楽で現出させている。オウテカが選ぶ素材や加工された音響、または最終的にアレンジされた音楽は何れも、非―音楽的コンテキストに貫かれ、その徹底ぶりが際立っている。音のエッジがもたらす刺激性や反復ビートとポリリズムが交差するテンションがインパクトを放つのではなく、音楽が何かしらの既成物を喚起させない純正物質的なものを感じさせる、その質感がすごいのである。‘非―音楽的コンテキスト’と書いたが、それは楽器の音や物音、自然音など、我々が‘理解可能な全ての既成の音’に対する‘非’を指すと同時に人の内面や思惟、感情などを含む‘現実世界’総体に対する‘非’であると言ってもいい。‘既成物’とはデジャヴ感覚も未来志向も含めて人がその想像力の範囲で感受、批評でき得る対象の事である。オウテカが持つ‘非―音楽的コンテキスト’とは、その全てから遮断されたような音感を伝播させるものであり、それを有する事で同時代エレクトロニカはおろか、過去のエレクトロニクスミュージック全般を見ても、オウテカほどの特質は見られない。過去のノイズミュージックもそれらの多くは‘ノイズ’という‘掌握可能な音’でしかなかった。
反論もあるだろう。オウテカは明確にクラブシーンというダンスカルチャーにその表現の母体を持っているのだから。クラブシーンを抜きにオウテカを感受する事も理解する事もできないとは思う。オウテカはかなりシンプルにダンス音楽、肉体的音楽を背景に持つと断言してもよく、その‘踊れない’テクノがダンスから乖離するのではなく、逆に ‘踊る’カテゴリーに関し人々に意識変革を促す意義こそを主眼に置いていると言えなくもないのだろう。しかし私の感じ方は別のところにある。他のエレクトロニカと比べ、もっと際立つ個性がオウテカにある。
私にとってボーズオブカナダとオウテカが別格的存在なのは、両者の音楽にある物語性ゆえである。この‘物語性’こそが両者の基底にあると信じて疑わない。
即物的音響の極みを革新し続けるオウテカは、非―既存性の物性音を奏でながら、いつもアルバム全体に濃厚な物語性がある。オウテカの音の物性は一見、反物語的、脱構築的であろう。そこには初めて聴くような違和の音塊が溢れ、それこそイブタンギーのような‘未知なる物質’、‘得体の知れぬ微生物’、‘見た事もないような鉱物’、‘アメーバの群れ’の如き音達が疾走している。
電子音楽に微量なメロディを送り込んで人間味を出したり、情緒に訴える手法はよくある。それらは物語性を醸し出すのに有効だ。しかしオウテカはこれ以上ない無機質性や先述した‘非―音楽的コンテキスト’によって濃厚な物語の構築を可能にした。オウテカは無機的音響による有機的結合、自由な運動と拡散による構築美こそを目指しているのではないか。まるで不規則運動を繰り返す微生物が最終的に意志を持った秩序に至るような感触があるだろう。アルバムにはプロローグからクライマックス、エピローグへ至る確かな筋道が用意され、フリーな音響活動が計算されたような一つのフォーマットに繋がる。その完成度にこそ私の驚きがある。
オウテカにあって、その作品性は重要だ。アメーバのように不規則な偶発的運動を繰り返す音達が実は作品性という普遍性を有している。それぞれのアルバムのホームリスニングに耐えられるその完成度、内容の多彩さ、曲の進行に於ける変幻自在さこそを注目すべきなのだ。クラブのシステムで大音量で再生しないと、どうしようなくしょぼい多くのエレクトロとは訳が違う。クラブシーンに於ける一回性の美学や瞬間速度的な消費サイクルが、音楽構築ならぬ解体のラディカリズムを誇るのも良い。ただ、アーティストは残された音源の50年後の評価や未来的客観性に挑むべきでもあるだろう。オウテカはその‘作り込む’作業性が、いかなる環境においても‘聴ける’ものをつくろうとする意志に貫かれていると強く感じさせる。
物語を構成する起承転結の創造や、最高潮の無意識的構築に於いてエレクトロニカシーンの中で際立つ存在なのがオウテカである。それはプログレ的、それもジャーマンエレクトロやゴング等の音響派ではなく、ジェネシスやヴァンダーグラフジェネレーター等が持つ文学臭や幻想奇譚にも通じるという意見は私だけだろうか。バロウズ的アンドロイドやサイバーパンクも含め、あらゆる物語、それらの言葉なき音象化に繋がる音楽性を有していると私は直感する。従ってオウテカの‘踊れない’テクノもその音楽の強固な物語的発揮物がリゾーム性を伴ってダンスカルチャーへ侵食しているという見方に整合性があるのではないか。
待望の新作『QUARISTICE』。
アメーバの群生が不規則に運動するような超物質的音響が響く。相変わらず。
以前には無かったようなアンビエント風味が要素として若干、あるにはあるが、それとてチルアウト的感触には至らない。やはり強力な物質性が勝る。しかもその運動範囲の拡大が今回の新作の特徴だろう。従来の限りなく内側へ向かってこんがらがるようなリズムの応酬ではなく、無数のビートが空間をゆっくり勝手に拡散してゆくような無意識的増殖性への変化が見られる。強いて言えば音の凝縮度がやや薄まり、部分的にテンポダウンする事によって、以前よりも間は生まれている。しかしそれもアンビエント的安寧の表現ではなく、攻撃性を瞬発に捉える為のダイナミクスの表現と見た方が正確だと思われる。場面場面での速度変更が特に際立つのがこの新作『QUARISTICE』だろう。
人はダンスフロアーでオウテカを感じ、変速ビートや音の捻れに体を揺らし、対応する事で、再び感じる。‘踊れない’テクノに踊る。とまどいながらも、ステップを踏み、体位を入れ替える。感じるだけで良い。何かを。考える必要はない。しかし、そこでの感覚は概念をスルーしたのではなく、結果的に何かしらのストーリーを喚起させる体験性を意識に沈殿させるはずだ。
オウテカ来日公演。4.26クラブカーマ。チケット買った。仕事終わってから行く。11時スタートのオールナイトイベント。終了朝5時。その後、仕事。しんど。寝られへん。楽しみである。
2008.4.19