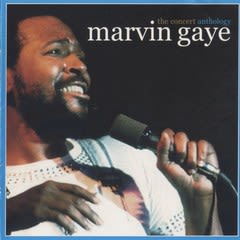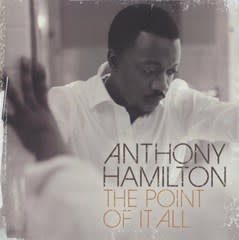以前、私はレコードコレクター誌「ロックアルバム ベスト100」でのビーチボーイズ『pet sounds』1位にケチをつけた。その後、やはり同誌が今度は「ソウル/ファンク ベスト100」を出版したが、マーヴィンゲイ『what’s going on』の1位以下、こちらはほぼ、納得の内容。と思いきや、だいぶ後になって、「そう言えばアイザックヘイズ『hot butterd soul』が入ってなかったな」と些細な事で再びケチがつき、昨年末、シールの新作『soul』で「if you don’t know me by now」を聴いて、「あっ、ハロルドメルビン&ブルーノーツのファーストも確か、なかったんじゃないか」と気がついて、本を確認したら、やっぱり入っていない。しかも、20人の選定者によるそれぞれのベスト20を隈無くチェックしたが、このグループは名前すらない。なんと。400件にも入らない。フィリーソウルの大名盤と思われるブルーノーツのファーストが完全に無視された。
『Black & Blue』は昨年、リマスターされたグループのセカンドで73年の作品である。
‘ブラック’と‘ブルー’で象徴したものは、ソウルバラッドとダンスであったか。超名曲「if you don’t know me by now」を含むファーストアルバムは大泣きのバラッド集だったが、本作では軽快なビートナンバーと重厚なソウル歌曲がバランスよく配されている。
この時点で結成20年。その容易ではなかった歩みが人生歌には勿論、ダンスナンバーにも深みを与える。ビートが深い。アッパーなリズムに歌を感じ、メッセージが顕れる。
長い不遇の時代を経てドラマーだったテディーペンターグラスが偶然にもリードシンガーとして開花し、グループの黄金時代が訪れる。主役を自認し始めたペンターグラスの脱退後はシンガーを変えながらグループは継続された。脇役に徹したリーダー、ハロルドメルビン死後も<ハロルドメルビン’ズ ブルーノーツ>とグループ名に冠されたハロルドメルビンの敬意の払われ方に、私はソウルミュージックに於けるコーラスワークの重要性が暗に示されている事を強く感じる。その存在はリードボーカルと対等である事は間違いないのだ。
「I’m comin’home tomorrow」の切実感に酔う。終盤、コーラスが離れ、ペンターグラスのソロパートになるその寂寥感も味わい深い。何かを暗示するようなその‘離れ方’に生きた人生観、ドラマ性が偶発的に盛り込まれる。ペンターグラスのバリトンボイスに力感が漲るのは、哀愁や悲哀さえ、ぎりぎりの底辺から浮上するような最後の明るさを有しているからか。「the love I lost」で歌われる愛の喪失が、スピード感に満ちたビートと高く舞い上がるようなコーラスに表されるポジティブな感性で表現される時、その相反する歌詞とビート感のアンバランスの融合感の妙を感知できる。内省的だが湿らない。前向きだが、哀愁を帯びている。そんな錯綜するような精神の複雑さをあっさりと表現するブルーノーツとは正に一種のボイスパフォーマンス集団であると私は理解する。極上のエンターティメントに酔いながらリズムの刻み方、発声の一つ一つ、コーラスの揺らぎ。そんな細部までしっかり聴きこみたい音楽。
2009.1.28