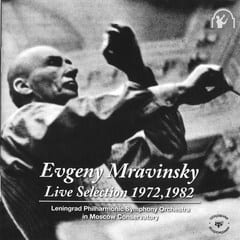「私には貧困の仕組みも、それを救う方法も考えられない」
曽野綾子著『貧困の光景』には最初のページで結論めいた事が記されている。もっとも著作の主旨が‘実態の記録’である以上、貧困地区への具体的な支援方法や処方箋の探求といった政策上の筋道を喚起させる言論を期待するものではない。ただ、その‘結論’は著者だけの感慨ではなく、もはや‘普遍的な結論’であるという事を作家は暗に示唆したのではないか。記述全体が醸し出すクールな視点や現状了解的な感覚から、援助に長年、関わった著者の実体験からくる、その如何ともしがたい変化への不可能性の実感があり、安易なヒューマニズムや理想主義を排する意味で、本書は真摯なドキュメントであると言えよう。
親父と全く同じスタイルを踏襲するシューンクティだが、決して親の七光りではない。そもそも子供が一体、何十人いたか定かでないフェラクティ。息子である事がもはや特別でない。シューンクティは独自に目覚め、アルトサックスをマスターし、強いボイスを獲得した。そして社会への問題意識を表現の契機とした。その姿はむしろ自発的、内発的なものだろう。
変わらぬ現実がある限り、変わらぬ歌が歌われる。メッセージソングとはもはや伝統芸能だ。シューンクティのアルバムは全編、アフリカの諸問題を扱う社会派のメッセージに溢れ、変革への熱い想い、怒りの表現が放たれる。その真摯な姿勢は英詞にも音楽にも顕れているが、一方で、この手の歌を一体、今までどれほど、聴いているだろう、という思いも同時にある。変革の不可能性という背景が変革への喚起を醸す歌を作る。その歌い手が時代によって入れ替わる。そんな循環システムの中で歌が内容的に進化する。シューンクティの歌の生命力に典型的なレベルミュージックを聴いた。
「african problems」という曲では‘I must try teach the people a new mentality’と歌われる。アフリカの諸問題の要因、それ即ちアフリカ人なりというメッセージを内側から貫く新展開をここにみる。フェラクティの戦闘が黒人解放、植民地主義、権力の腐敗というキーワードで表されるラディカリズムであったならシューンクティはアフリカ人の内面的病巣をより問題化し、その変化こそを変革の契機と位置付けているように感じる。外部転嫁を指弾するその視点に『貧困の光景』に通じる説得力を感じた。
EGYPT 80を襲名したアフロビートの新星.
圧倒的なグルーブを誇り、その伝統芸能を伝播する。同じくフェラクティの息子であるフェミクティがアメリカナイズされた感があったので、もはやそれを超える存在感をここに示した。と思ったらフェミクティも近々、ニューリリースがあるという。
2008.9.28