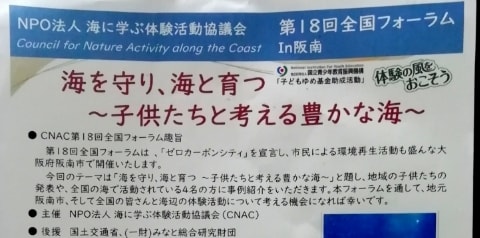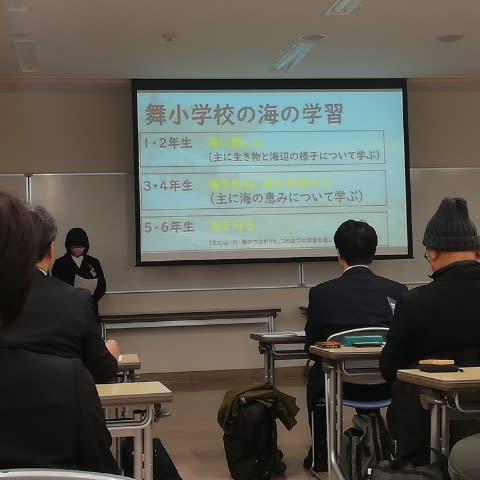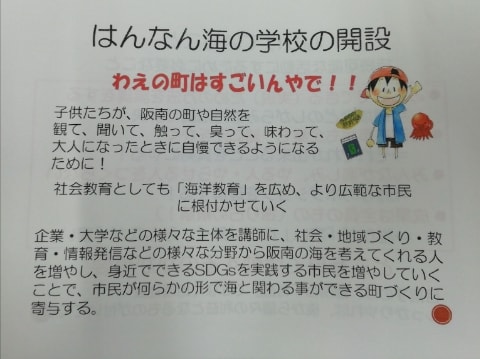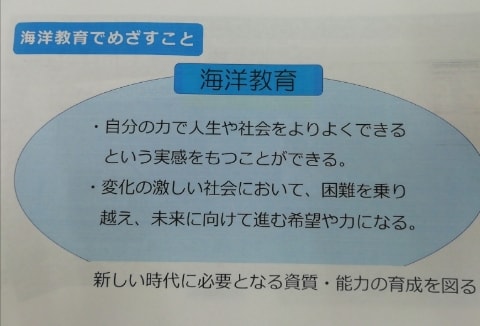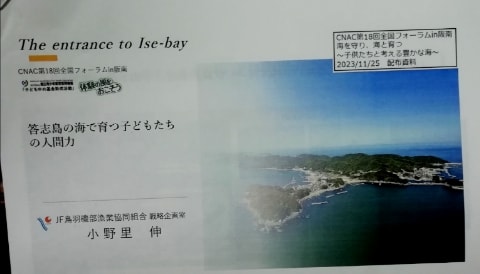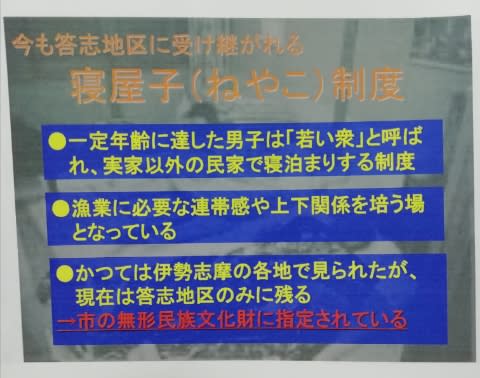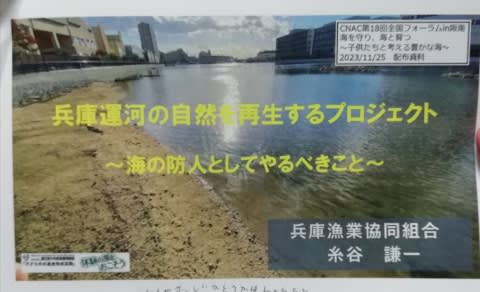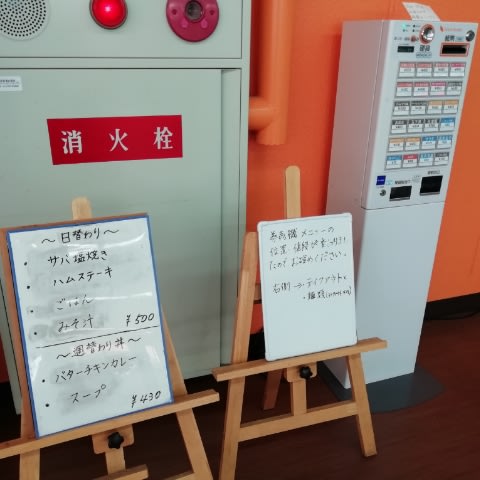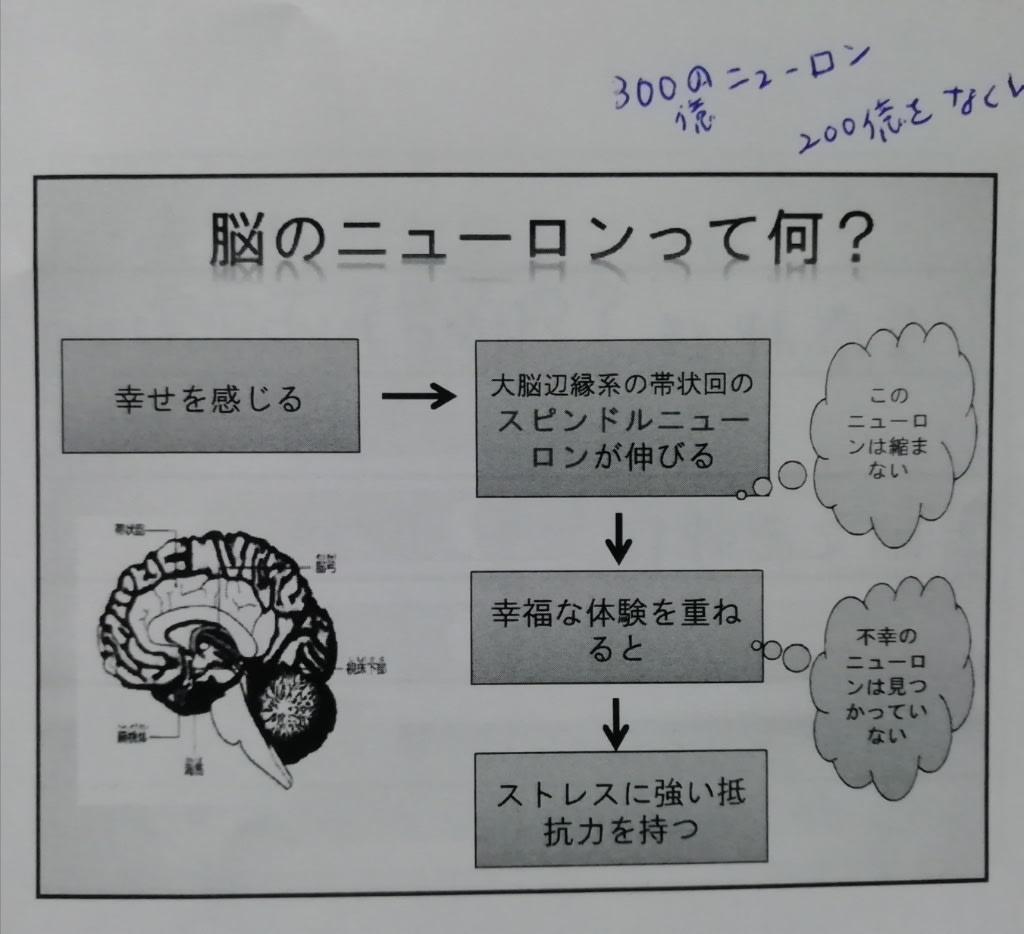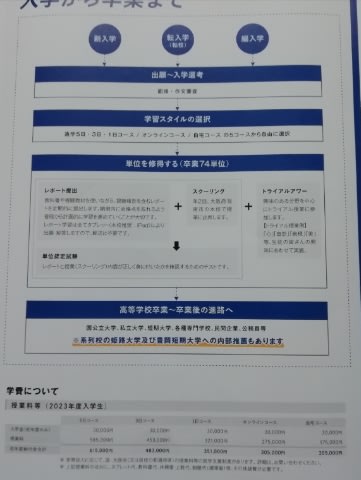昨年から、
子育て世代のお父さん、お母さんたちが、市長や教育長との懇談を申し入れて実現する機会が不定期にあり、
今日は、教育長との懇談会でした。
政党色や地域色も年齢の偏りもなく、
「誰に、どこに聞いたらいいかわからない『教育や学校、規則』などへの疑問や不安」を口にでき、
教育長も「できる、できない」ではなく、
個人としての見解を話されたり、
国の施策の話をされたり、
持ち帰って教育委員会内で共有すると言ってくださったり、
という、今子育て真っ最中のみなさんと現状を共有する時間になっていて、
その場に同席させていただいた私にも、
大切な時間になっています。
「うちの子はこう言っています」
「うちの子が通っている学校では、クラスではこうです」
という声には、
他の方から共感の声もあれば、違う状況の声があったり、
誰かの声だけが一方的に語られることがないのも、
参加したみなさんが考える機会にもなっていると感じます。
今回出た声では、
●指定管理者が変わることに対し、当事者の声をまず聴いてほしかった(たんぽぽ園に通われている方から)
●さまざまな発達の相談の場では、言われた窓口に行っても納得いく話が聴けないこともある。勇気を出して相談している。すぐでなくていいので、窓口の方は、よくわかる方に聞くなどして対応してほしい。
●小学校では、大休憩や昼休みは、雨の日だけトランプなどができるが、晴れの日は外に出るように言われ、運動の苦手な子にはつらい。運動が苦手でなくても、休憩時間は好きにあそばせてほしい。
●休憩時間で言えば、「5分前行動(着席)」は必要なのか?
●授業でも、タイマーを使って「10分で」「5分で」という行動をさせられているのが気になった。
●「教育支援センター」は、来年も同じ感じですか?変わってほしい。
●教室に入れない子どもが別室登校しているが、担当の先生がいない様子。先生が来てくれても、忙しいようすで落ち着かず、今は行っていない。
●教室に入れない子は、授業もテストも受けられないと聞いた。出席日数のためだけの登校?
●学校の中の掲示物に、子どもたちを励ます目的だと思うが「がんばろう」とか「○○チャレンジ」とかを見かけるが、つらい子もいるかもしれない。
●1週間の生活時間のアンケートのようなものを書かされるのが苦痛。
などがありました。
すぐに解決できることではないと思いますが、
気になることを伝える場があることは、大事なことだと思います。