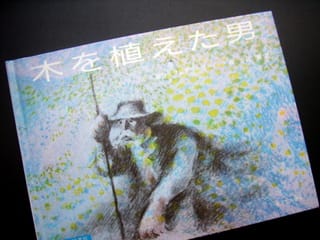仲間たちと輪読会をやっています。
場所は仲間の一人のお店、メロメロポッチというライブハウス。
いろんな活動をしている人たちが集まる場でもあります。
今、みんなで読んでいるのは「スローライフでいこう」。
インドのエクナット・イーシュワランさんが書いたこの本は
ガンジー哲学が基本になっています。
今日は第5章の“自由な心で生きる”。
最初にイギリスの詩人であり画家である
ウィリアム・ブレイクの美しい詩が引用されていました。
・・・・・・・・・・・・
快楽に執着するものは
その翼のついた生命を壊してしまう
去りゆく快楽を口づけとともに送るものは
永遠の日の出に生きることができる
・・・・・・・・・・・・
過去も未来も考えずに完全に『今、ここ』に
生きることに集中することが
無執着(とらわれない心)を実現させる秘訣だという。
生活の中で忘れそうになる大切なことを
いくつも考えさせてくるメッセージが詰まっています。
この輪読会、何故か仲間たちが一人は仕事で九州へ
二人目はやはり仕事で四国へ旅立ち、
今日集まった6人のうちの3人がもうすぐ
結婚などで東京へ旅立ちます。幸せな旅立ち!
寂しくなるけどお祝いも兼ねて
今夜はみんなで食事&飲み会をしました。
出会いがあって別れがありますが
その中で共に学び合えたことが幸せ!
今度また会えるのはいつになるのだろうね。
場所は仲間の一人のお店、メロメロポッチというライブハウス。
いろんな活動をしている人たちが集まる場でもあります。
今、みんなで読んでいるのは「スローライフでいこう」。
インドのエクナット・イーシュワランさんが書いたこの本は
ガンジー哲学が基本になっています。
今日は第5章の“自由な心で生きる”。
最初にイギリスの詩人であり画家である
ウィリアム・ブレイクの美しい詩が引用されていました。
・・・・・・・・・・・・
快楽に執着するものは
その翼のついた生命を壊してしまう
去りゆく快楽を口づけとともに送るものは
永遠の日の出に生きることができる
・・・・・・・・・・・・
過去も未来も考えずに完全に『今、ここ』に
生きることに集中することが
無執着(とらわれない心)を実現させる秘訣だという。
生活の中で忘れそうになる大切なことを
いくつも考えさせてくるメッセージが詰まっています。
この輪読会、何故か仲間たちが一人は仕事で九州へ
二人目はやはり仕事で四国へ旅立ち、
今日集まった6人のうちの3人がもうすぐ
結婚などで東京へ旅立ちます。幸せな旅立ち!
寂しくなるけどお祝いも兼ねて
今夜はみんなで食事&飲み会をしました。
出会いがあって別れがありますが
その中で共に学び合えたことが幸せ!
今度また会えるのはいつになるのだろうね。