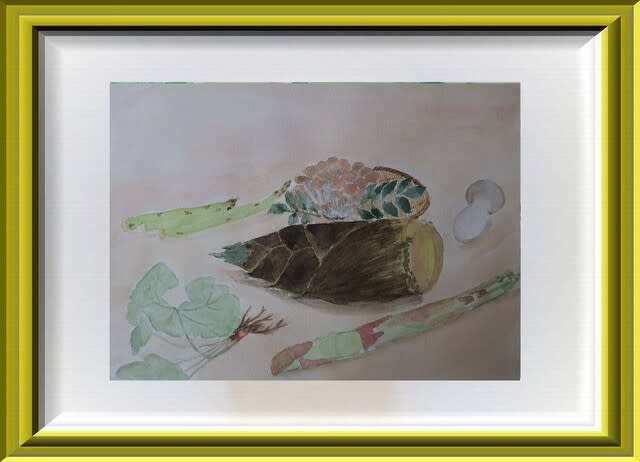◇ アジサイ寺で知られた長谷山本土寺へ

clester F8
梅雨時の写生会。前回の観音寺(柏市)はあいにくの雨で中止になった当クラブの
写生会。今回は時期的にアジサイで知られた松戸市北小金にある「本土寺」。
昨日は予報が外れたが今日も28℃と 予報も外れ。蒸し暑いが28℃には達しなかっ
た。しかし雨が降らなかっただけで良しとしなければ。
本土寺は鎌倉の明月院ほどではないが首都近郊ではアジサイ寺として名が知られて
いる。
この時期 はアジサイのほかあやめも満開とて平日なのに沢山の人が押し寄せていた。
寺はこの時期は拝観料として500円求める。障碍者と子供は300円だが高齢者だからと
言って容赦しない。
アジサイよりも菖蒲池の周りが結構な人で賑わっていた。
アジサイもあやめも絵にするとどうしても花を鮮明に浮き上がらせるにはマスキン
グが欠かせない。けっこう根気がいる仕事になる。あやめもアジサイも花の色は白、
青、ピンク、紫であるが、やや高台にある所から見ると壮観である。