先日のバラエティー番組「日曜日の初耳学」で、ドラマ「御上先生」のモデルとなった、教育界のカリスマ。
共愛学園前橋国際大学の大森学長が紹介されていました。
大森学長は「全国の学長が注目する学長」3年連続、No1の学長だそうです。
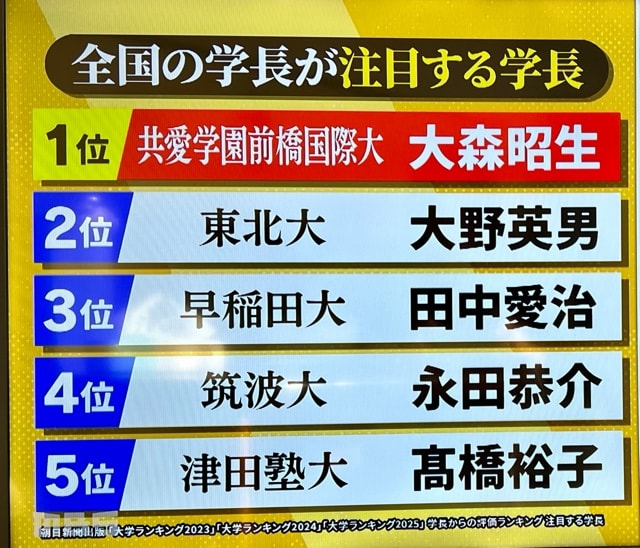
今、定員割れの私立大学は約6割あり、過去最悪の記録を更新中とのこと。
そんな中、群馬県前橋市にある小さな私立大学、共愛学園前橋国際大学では生徒数が年々増え続けているそうです。
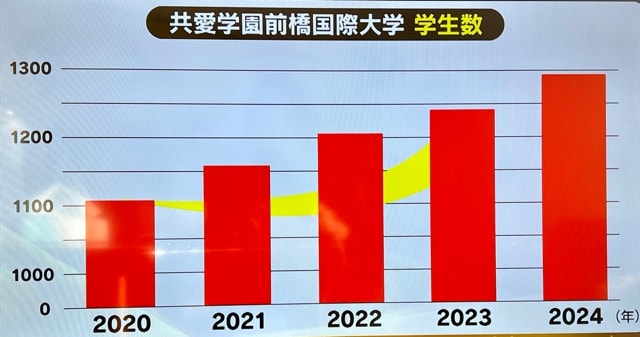
朝日新聞版「教育・研究が注目される大学ランキング2025」では、名門大学が並ぶなか、第10位にランキング。
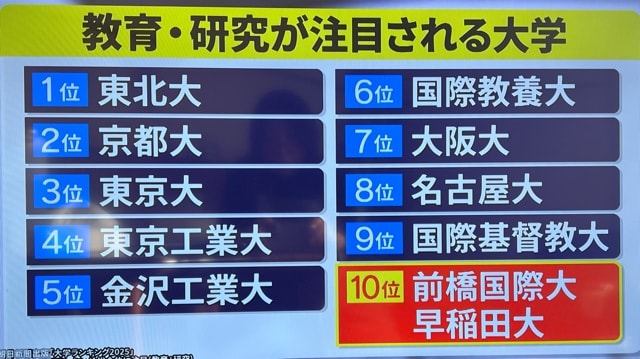
その理由を探るために、教育関係者や文科省の職員がこぞって視察に訪れているそうです。
大森学長が主張されているのは・・・
Fラン大学は日本に必要・・・であるということ。
(Fラン大学とは、偏差値が低く入学するのが簡単な大学)
昨年、東大の年間授業料が、2025年度から年10万円上げるというニュースが出た時に、
Fラン大学への補助金がもったいない。
Fラン大学を潰して補助金を東大に回すべき
というような「Fラン大学不要論」が世間で飛び交ったそうです。
ただ、大森学長は・・・
「不要な大学はない」と、不要論を真っ向から否定。
偏差値という一つの物差しで、大学を見るのは昭和的。
有名大学でトップリーダーは育つかもしれないが、トップリーダーだけでは社会は回っていかない。

トップリーダーの下に、ミドルリーダーも必要だし、しっかりと産業を支えていく地域を支える人材も必要。
そういう人材は、地方の小規模な大学で育っている。
Fラン大学が無ければ、ミドルリーダーが育たず、国力の低下に繋がる。
学力や経済面で、都心の大学に通えない若者を、地方の入りやすい大学が教育し、やがて地域を支える人材になる。
そんな学びの場を日本から無くすわけにはいかない。
これから大学を選ぶ時には、その中身を知り、何が学べて、どんな力を身に付けられるのかをみる。
大学とはなんなのかという概念をアップデートしなければならない。
かつて、共愛学園前橋国際大学はFラン大学寸前だったそうです。
「地域のリーダーを育てる」という目標をより明確に打ち出し、大学の授業を大胆に改革したことで、
全国から注目を浴びる大学と生まれ変わったとのこと。
その授業内容とは・・・
半年間、大学に来なくてもよい・・・というものも。
その半年間で何をするのかというと・・・
地元の市役所や企業で働く。
群馬にはたくさんの山間地域があるので、そこのおじいちゃん、おばあちゃんの孫になる。
そこに実際の地域課題がある。
どんどん過疎化が進む地域で、高齢者と生活を共にすると、集落が無くなるのは止められないというリアルを知る。
でも、そのリアルを全部、目に焼き付けようとする。
そんな、地域の課題に取り組む活動を授業に導入。
その期間は大学に通わずとも単位が付与される。
学長の「信念」とは・・・生徒の主体性や課題設定能力を伸ばす教育方針。
今は予測困難な時代と言われている。
知識だけでは生きていけない。
知識を使って、どうやって実践で活かしていくか。
知識と実践、教室と地域・・・それを行ったり来たりしながら学んでいる。
・・・とのことでした。
すでに時代は、「土の時代」から「風の時代」に変わっています。
物や形といった目に見えるものに価値が置かれていた時代から、
お金や財産がある人が力を持つ時代から、
固定観念や終身雇用などを重んじる時代から、
個々の自由と権利・平等を強く求められる時代。
情報や知識、コミュニケーションなど形のないものが重視される時代。
自分の好きなことや、やりたいことに素直に行動することが大切な時代・・・になっています。
親の価値観もアップデートしないといけないですね














