 達也は自分の叫び声で目を覚ました。ひどい頭痛だ。彼は頭をふって、あたりを見回した。なんとか頭痛がおさまると、やっと自分がどこにいるのか理解した。
達也は自分の叫び声で目を覚ました。ひどい頭痛だ。彼は頭をふって、あたりを見回した。なんとか頭痛がおさまると、やっと自分がどこにいるのか理解した。
この部屋の持ち主は、怪盗ブラックと名乗っていた。先月、ある美術館から名画を盗んだことで、世間から注目を集めたばかりだ。なぜ彼がここにいるのか。それは、彼こそが怪盗ブラックだから。というより、彼の中に怪盗が同居しているのだ。
達也は大きなため息をついた。自分の中にいる別の自分が、また悪事を働こうとしている。でも、それを止めることは彼にはできなかった。ふと、彼は手に握りしめている紙に目をやった。テーブルに広げてみると、それは地図と、どこかの建物の見取り図だ。地図には赤い線が引かれ、見取り図にはばつ印がつけてあった。彼は地図の赤い線の行き着く先を見て驚いた。そこは、彼のよく知っている人の屋敷だった。
「ご、ごめんなさい。こんなところへ呼び出して…」達也は落ち着かない様子で言った。
「そんな、いいんです。うれしい。達也さんから誘ってもらえるなんて」
しゃれたオープンカフェにいる二人は、誰が見ても不釣り合いなカップルに見えた。達也は時代遅れの黒縁眼鏡をかけて、何ともさえない服装をしていた。それにひきかえ彼女のほうは、清楚で気品があり良家の子女という雰囲気だ。
「今度、家でパーティがあるんです。よかったら、達也さんも…」
「いや、ぼ、僕なんか駄目ですよ。それより、綾乃さんに聞きたいことがあって…。あの、綾乃さんの家に、家宝と言えるような大切なものってありますか?」
「家宝? そう言えば、子供の頃、家にはお宝があるって聞いたことがあります」
「あの、こ、これから話すことは誰にも言わないで下さい。お願いします」彼は声をひそめた。「実は、そのお宝を盗もうとしている悪党がいるんです」
「えっ!」彼女は思わず小さく叫んだ。
その日の夜中。暗闇にまぎれて屋敷に忍び込む人影があった。身軽に塀を乗り越えて、大きな庭木をよじ登り二階のベランダに飛び移った。そして、ガラス窓をいとも簡単に開けてしまった。部屋に入ると、すぐに隠し金庫を見つけだし、ものの十数秒で開けてしまった。その手口の鮮やかなこと。怪盗は中にあった小さな木箱を取り出し、にやりと笑った。
そのとき突然、部屋の明かりがつき、大勢の警官がなだれ込んだ。怪盗は逃げる余裕すらなく、取り押さえられ観念した。手錠をかけられ連行される男。
屋敷の玄関は大勢の人であふれていた。その中に、綾乃の姿もあった。綾乃は怪盗を見て驚いた。その顔は、まぎれもなく達也の顔だった。達也は綾乃を見つけると、優しく微笑んだ。まるで、すべてのことが分かっていたみたいに。
綾乃は刑事から木箱を渡された。それは昼間、達也から本物とすり替えるようにと渡されたものだった。綾乃は達也との約束を守っていたのだ。彼女はそっと箱を開けてみた。中にはウサギの小さな置物が入っていた。綾乃はハッとした。これは子供の頃、達也にプレゼントしたものだった。添えられていたカードには、「これで終わらせることができます。僕は、綾乃さんのことは忘れません。ありがとう。幸せになって下さい」
<つぶやき>人生にはどうしようもないことってありますよ。でも、負けないで下さい。
Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。
 かすみさんがこの手紙を見つけたとき、もう僕はこの世界から消えてしまっていると思います。でも、悲しまないで下さい。僕とあなたが過ごした三十年のあいだ、楽しいことがたくさんあったから。僕は、あなたと一緒にいられて、とても幸せでした。
かすみさんがこの手紙を見つけたとき、もう僕はこの世界から消えてしまっていると思います。でも、悲しまないで下さい。僕とあなたが過ごした三十年のあいだ、楽しいことがたくさんあったから。僕は、あなたと一緒にいられて、とても幸せでした。
僕がこんなことを言うと、かすみさんは怒るかもしれませんね。だって、僕は良い夫ではなかったから。仕事にばかり夢中になって、あなたのことを一人ぼっちにしてしまった。子供たちのことも、みんなかすみさんに任せてしまっていたしね。
でも、あなたのおかげで、子供たちも無事に育ってくれました。とても感謝しています。こんなこと、面と向かっては言えなかった。ちゃんと言っておけばよかったね。
あなたはいつも家族のことを考えていてくれたよね。僕が入院したときも、毎日のように来てくれた。僕がそんなに来なくていいよって言っても、あなたは僕と一緒にいられる時間が増えたのよ、こんな幸せなことはないって笑ってくれた。僕は、あなたの笑顔がいちばん好きだったんだよ。あなたの笑顔はみんなを幸せにしてくれる。
僕がいなくなっても、笑顔を忘れないで下さい。これからは、あなたのやりたいことを好きなだけしていいんだよ。僕から、かすみさんへのご褒美です。ありがとう。
「何してるの?」押し入れの前で座り込んでいる娘に、母は声をかけた。
「ねえ、私、すごいもの見つけちゃった」興奮を抑えながら娘は古びた本を差し出した。
「これ、かあさんの…」母は懐かしそうに微笑んだ。「これは、おばあちゃんがとっても大切にしていた本よ。この本のおかげで、おじいちゃんと出会えたってよく言ってたわ」
「そうなんだ。だから…」娘は目を潤ませて、「この中に手紙がはさんであったの。おじいちゃんからのラブレターよ。それも、最後のラブレター」
娘は色あせた手紙を母に手渡した。母は手紙を読み終えると、
「こんな手紙もらってたなんて、ちっとも知らなかったわ」
「おばあちゃん、いい恋してたんだよね。こんなに愛されていたなんて…」
「あなたはどうなの。いい恋、してないの?」
「私は…。どうなんだろ、わかんなくなっちゃった」娘は投げやりに言った。
「隆さんとうまくいってないの?」
「うーん。やっぱり、遠距離って続かないのかな?」
「なに弱音吐いてるの。そんなんじゃ、おばあちゃんに笑われるわよ」
「だって…。逢いたいときに逢えないなんて、つらすぎるよ」
「おばあちゃんだったら、今ごろ飛んで行ってるでしょうね」
「私は…。ひとりでアメリカなんて行けないよ」
「もう、いつまでも子供なんだから。そんなんじゃ、何にも出来ないよ」
「わかったわよ」娘は立ち上がり、「行くわよ、行けばいいんでしょ。私だって…」
「でも、遺品の整理を済ませてからにしてよ。ひとりじゃ大変なんだから。それと、隆さんにちゃんと連絡しときなさい。向こうで、金髪の美女と鉢合わせしないようにね」
「もう、かあさん! なに言ってるのよ。そんなことあるわけないでしょ」
<つぶやき>人生の節目にあたり、心のこもった感謝のラブレターを書いてみませんか。
Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。
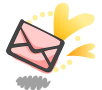 山田君へ。突然こんな手紙を書いてしまって、ごめんなさい。
山田君へ。突然こんな手紙を書いてしまって、ごめんなさい。
私が廊下で転んでプリントをばらまいてしまったとき、山田君は一緒に集めてくれたよね。あのとき、私、ちゃんとお礼も言えなくて。山田君は、そんなこともう忘れているかもしれないけど。私は、ずっと後悔してて。なんで、ちゃんとありがとうって言わなかったんだろう。ちゃんと言ってれば…。
私、山田君と同じクラスになったときから、山田君のことがずっと気になってて。でも、声をかけることが出来なくて。この手紙を書くのだって、ずっと迷ってて。友達に相談したらね、ちゃんと告白した方がいいって言われたの。それで、私、決めたの。
私、山田君のことが好きです。山田君は、他に好きな人がいるかもしれないけど、それでもいいの。私の片思いでもいい。こんな気持ちになったのは初めてで、自分でもどうしたらいいのか分からないんだ。今もドキドキしてる。でも、なんだか心の中がほわっとしてて、あったかいの。今まで悩んでいたことが、どっかへ行っちゃった。
あのときは助けてくれて、ほんとにありがとう。もし、私のこと好きじゃなかったら、好きになれなかったら、この手紙は捨ててください。
「ねえ、あなた。さっきから何やってるの。そんなんじゃ、ちっとも片付かないでしょ」
「ちょっとね、昔の手紙を見つけてさ」
「もう、今日中にやらないと、あさっての引っ越しに間に合わないでしょ」
「ごめん。でも、懐かしくてさ。きみ、これ覚えてる?」
男は女に色あせた手紙を手渡した。女はそれを手に取ると、「なに、これ?」
「何だよ。覚えてないの? ほら、学生のとき、きみが僕に…」
「知らないわよ。私、手紙なんか書いたことないし」
「えっ、そうだった?」
「もしかして、これラブレター?」女が手紙を読もうとしたので男は慌てて、
「駄目だって…」
男は女から手紙を取り上げようとするが、女は逃げまわりながら、
「ねえ、誰からもらったのよ。白状しなさい」
「だから、きみからだと…」男はなんとか手紙を取り戻して、「よっしゃ!」
「もう、子供なんだから」女は悔しそうに言うと、「ほんとに覚えてないの?」
「うん」男は手紙をかざして、「名前も書いてないし。ほんとにきみじゃないの?」
「私は知ーらない。ねえ、そんなことより、あなたのガラクタなんとかしてよ」
「ガラクタって。あれは、僕の大切なコレクションなの」
「そうですか。あなたが片付けないと、私、明日の不燃ゴミに出しちゃうわよ」
「やめてくれよ」男はそう言うと自分の部屋に駆け込んだ。
「まだ持ってたなんて…」女は男が置き忘れていった手紙を手に取ると、懐かしそうにつぶやいた。「でも、これは、私が預かりますからね」
<つぶやき>初恋は青春の思い出。心のどこかに隠れてて、時々現れては消えていく。
Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。
 その研究室は大学構内の奥まった場所にあった。そこへ行くためには、迷路のような通路を通り、いくつもの扉を抜けないとたどり着くことはできない。大学関係者ですら、この研究室にたどり着けた者は数えるほどしかいなかった。そんなわけだから、学生でこの研究室の存在を知る者など、全くと言っていいほどいなかった。
その研究室は大学構内の奥まった場所にあった。そこへ行くためには、迷路のような通路を通り、いくつもの扉を抜けないとたどり着くことはできない。大学関係者ですら、この研究室にたどり着けた者は数えるほどしかいなかった。そんなわけだから、学生でこの研究室の存在を知る者など、全くと言っていいほどいなかった。
この研究室では、ある実験が行われていた。それは、いろいろな物を掛け合わせて、新しい物を作り出すというものだ。教授はこの実験を何十年も続けていた。
ある日、教授は研究室の前まで来て驚いた。部屋の中から美味しそうな匂いが漂ってくるのだ。研究室に入ってみると、助手のかえでが机の上にたくさんの料理を並べ、昼食を取っていた。
「君は、何をしているのかね?」教授は驚いた顔で助手に尋ねた。
「すいません」かえでは申し訳なさそうに、「食堂まで行くのがめんどうなので、つい…」
かえでは偶然この研究室に迷い込んできた学生で、どういうわけか教授のことが気に入ってしまい、押しかけ助手として研究の手伝いをしていた。
「それにしても」教授は机に並んだ料理を見て、「どうやってこんなに作ったのかね?」
「ほんとに、すいません」かえでは深々と頭を下げると、「実は、あの装置を使ったんです」
「装置を?」教授は研究室の一角を占領している機械の塊を見て、「まさか君、この装置で料理を作ったのかね? 信じられない。そんな使い方ができるわけがない」
「でも、教授。それができちゃったんです」かえではそう言うと、まだ残っていたジャガイモや豚肉などの食材と調味料を容器の中に入れると、装置のボックスにセットした。
「えっと、これでパワーを弱にして…」かえでは装置のスタートボタンを押した。
装置はぶうぉーんと音を響かせて動き出した。しばらくすると、ボックスから白い煙が立ち上がった。それを合図に、かえでは装置のスイッチを切った。そして、ボックスの扉を開ける。中から出てきたものは、肉じゃがだった。
「でも、難点は…」かえでは肉じゃがを机の方に運びながら、「どんな料理になるのか、わからないことです。同じ材料を入れても、同じ料理ができるとは限らないんです」
「これは、たまげたな」教授はそう言うと、容器の中で湯気を立てている肉じゃがを、まじまじと見つめた。
「食べてみますか?」かえではそう言うと、教授に大きなスプーンを手渡した。
教授は恐る恐る口にした。その瞬間、教授の顔色が変わり、目から大粒の涙がこぼれた。かえでは教授の変わりように驚いて、急いで出来たての肉じゃがを口にしてみた。
「…まずい! 何で、これだけ。他の料理はとっても美味しいのに」
「これは、妻の味だ。私の妻は、どういうわけか、肉じゃがだけがまずくてね」
「妻って、あの、教授の、行方不明になっている…」
「そうだ。もう、二十年になる。私と一緒に研究してたんだが、この研究室で事故があってね。それ以来、行方がわからなくなっていたんだ。だが、とうとう見つけた。あいつは、この装置と同化していたんだ。ずっと、私のそばにいてくれたんだよ」
<つぶやき>愛する人のことを思い続けることができるなんて、素敵なことですね。
Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。
 「何でそんなこと言うの? 約束したじゃない! ずっと一緒にいるって」
「何でそんなこと言うの? 約束したじゃない! ずっと一緒にいるって」
涼子は電話口で声を荒らげた。電話相手の彼とは、もう三年の付き合いになる。ここ数ヶ月はお互いの仕事が忙しく、なかなか逢うことが出来なかった。それに、電話も夜遅くしか出来ないので、長話をするわけにもいかなかった。涼子は淋しい思いを我慢していた。
だから、今日はまだ早い時間なのに彼から電話がかかってきて、涼子は飛び上がらんばかりに喜んだ。それが、まさかこんな事になるなんて、夢にも思わなかった。
「どういうことよ。はっきり言ってよ」
涼子の声は震えていた。相手の話を身動きもせずに聞いていたが、
「分かんないよ! 仕事がそんなに大切なの。……そりゃ、私だって、仕事が忙しくて、急に逢えなくなったときあったけど…」涼子の目から、一筋の涙がこぼれた。
「ねえ、どうしてもだめなの。離れたくないよ。ずっと一緒にいようよ」
彼は涼子が泣いているのに気づいたのか、
「泣いてなんかいないわよ。楽しみにしてたんだから。それなのに…」
彼女は、自分が無茶なことを言っているのはわかっていた。でも、許せなかった。
「……延期?! 何でよ、あなたから言いだしたのよ。それを…。簡単に言わないで!」
涼子はしばらく、無言で彼の話を聞いていた。しかし、
「わがまま? 何それ! 私、わがままなの? 私が、この日のためにどれだけ…」
彼の方も、声を荒げて、何かしきりにしゃべりはじめた。こうなると、お互い相手の話など耳に入らない。自分のことしか、考えられなくなっていた。とうとう彼女は、
「もういいよ! 私一人で行くから。一人で泊まって、2人分、ご馳走食べてやる!」
彼女はそのまま電話を切ってしまった。本当に腹が立った。彼女は怒りをぶつけるように、そばにあったクッションを電話に投げつけた。
しばらくして、気がおさまると、今度は後悔の念が嵐のように襲いかかってきた。
「ああ…、何であんなこと言っちゃたのかな。どうしよう…」彼女は電話に手を伸ばした。でも、途中で思いとどまって、「何で、私から…。悪いのは、あの人なんだから…。大丈夫よ…。向こうからきっと電話してくるはず」
涼子は待った。五分、十分、二十分…。でも、いくら待っても電話はかかってこなかった。彼女は不安になってきた。いろいろな想像が、頭を駆けめぐる。
「もしかして、私、嫌われたの? でも、悪いのあの人よ。でも…。まさか…、他に好きな人が…。いいえ、そんなことあるわけない。でも…。違う、仕事が忙しいから会えなかったのよ。私以外の人とそんな…」
その時、突然電話が鳴り出した。涼子は、思わず電話に飛びついた。
「はい……。なんだぁ、愛子なの…」それは、涼子の親友からの電話だった。
久し振りに親友の声を聞いてほっとした涼子は、それから話し込んでしまった。電話を切ったときには、もう十二時を過ぎていた。
「あれ、私、何してたんだっけ…。あっ、もうこんな時間。早く寝なきゃ」
<つぶやき>仕事と恋の両立は難しい。どっちも大切ですから。明日、仲直りしましょう。
Copyright(C)2008- Yumenoya All Rights Reserved.文章等の引用と転載は厳禁です。
















