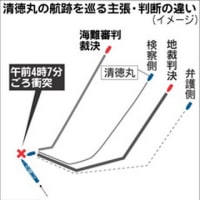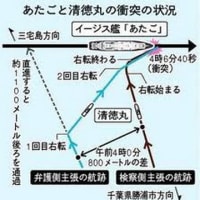「米GM、破産法を正式申請-負債総額16兆円超」とのニュースが流れた。経済のことには疎いが、これはGMの倒産と言うことなのだろう。俗な言い方では「GMが潰れた」のである。アメリカにおける自動車産業のビッグ・スリーのうち、すでにクライスラーが潰れたので残るところはフォードのみ。あまりの呆気なさに私なんかはついていけない。かっての大日本帝国の崩壊を見る思いである。
私がまだ中学生か高校生の頃であるが、父が「Collier’s」というアメリカの週刊雑誌を購読していて、そこに出てくる衣食住すべての写真に圧倒されていた覚えがある。まさによその世界の話で自分にはまったく無関係に思っていたが、父はそのなかに日本の将来を夢見ていたのかも知れない。ページ全面に大きくカラー印刷された車でBuickとかPontiacという名前を覚えたのもこの時である。敗戦国民は言うに及ばず、アメリカ人にとってもこのような車で生活をエンジョイすることが「アメリカン・ドリーム」であったのだと思う。
BuickもPontiacもGMの車であったが、GMの作る最高級車であるCadillacは、当時の占領軍の最高司令官であるダグラス・マッカーサー元帥の乗用車として日本国民にもよく知られていた。このCadillacに一度だけ思いがけないことで乗ったことがある。1960年代の初頭、私は大阪大学の大学院生だったが、大学院入試の時の試験官であった赤堀四郎先生がまもなく大阪大学の総長になられて、その公用車がCadillacだった。丸みを帯びた車体で「ウィキペディア」の「キャデラック」で見ると、戦後型として写真の出ている「シリーズ59(1948年)」のようであった。ある日のこと、どういう成り行きでそうなったのか、またどこまで行ったのかまったく記憶に残っていないが、赤堀先生に「乗りなさい」と言われてそのCadillacでどこかに連れて行かれたのである。赤堀研にいた友人と一緒であったことだけははっきりと記憶している。ただそれだけのことであるが、それにしてもこのCadillacがどういう経緯で大阪大学に迷い込んできたのだろう。かなりの年代物であったように思う。
1966年に初めて渡米して中古車を買うことになった時に、ディーラーで一台のCadillacが目に留まった。かなり年代が古いがシートが総革製で窓の開閉が電動式なのである。予算は遙かにオーバーしていたが無理をすれば手の届く範囲なので一時は迷ったが、身の程知らずにそんなことを考える自分が滑稽になって止めた。その時に買った中古のFord・Futuraがトラブル続きで、Santa BarbaraからLos Angelesに出かけた帰り道に遂に動かなくなり、再生エンジンに取り替えることになった。その際に代替車として借りた大型車(多分フォード・ギャラクシー)の性能に感激したものである。ちょっとアクセルを踏み込むだけで、それまではよたよたと上っていた101のかなりの急坂を、他車をいとも易々と追い越しながら一気に駆け上がったからである。ガソリンをがぶ飲みしての頑張りであったのだろう。
1980年代の初め、デトロイトで一夏過ごしたことがある。週末になるとレンタカーであちらこちらを飛び回ったが、GM本社のあるルネッサンス・センターにもよく出かけた。映画館が何軒もありいつも長い行列が出来ているのが印象的だった。まだアメリカ映画が元気であったのだろう。どのビルだったか覚えていないが、その上にある回転レストランで食事をした覚えがある。昨夜、テレビニュースでこの一帯の夜景が写っていたが、ルネッサンス・センターとデトロイト川対岸のカナダ・ウィンザー市の灯火の輝きに、このレストランからの展望が重なってとても懐かしかった。デトロイト川をトンネルでくぐり抜け、カナダに入ってトロント辺りまでは何遍も足を伸ばしたものである。レンタカーはアメ車だった。日本の小型自動車の対米輸出が第一次石油ショック(1973年)、第二次石油ショック(1979年)を経て大幅に増加したことがいわゆる自動車摩擦を引き起こしていた。テレビでも日本車を米国人がハンマーでたたき壊すパフォーマンスが流されたこともあり、米国人が「デトロイト不況」と呼んでいた日米間の自動車摩擦が最高潮に達していたので、わざわざ日本車を乗り回して米国人を刺激することを避けたつもりであった。その後米国景気の回復につれて自動車需要が増大したものの、この間ビッグスリーのうち、何とか持ちこたえたGMがその体質改善に積極的でなかったと言われる。そういうことが今回の破局の淵源なのだろうか。
世界的に苦境にある自動車産業の行方に私は少々冷淡である。もうそろそろ次の新しい移動手段が現れてきてもいいのではないかと思うせいかもしれない。子供の頃何回も読み返した講談社の絵本に「魔法の杖」(?)と言うのがあった。目をつむってステッキをくるくると回しながら行き先を唱えると、次の瞬間にはもうそこに着いているのである。究極の移動手段ではなかろうか。私も呪文だけはよく唱えたものだ。せいぜい動き回るだけに車のような大げさな機械・装置を人間が作るのは、まだ知能が低いレベルに留まっているせいだろう。あの小さな身体で何千キロも移動する渡り鳥の飛翔能力ひとつを考えてみても、手つかずの研究領域があるように思う。
私がまだ中学生か高校生の頃であるが、父が「Collier’s」というアメリカの週刊雑誌を購読していて、そこに出てくる衣食住すべての写真に圧倒されていた覚えがある。まさによその世界の話で自分にはまったく無関係に思っていたが、父はそのなかに日本の将来を夢見ていたのかも知れない。ページ全面に大きくカラー印刷された車でBuickとかPontiacという名前を覚えたのもこの時である。敗戦国民は言うに及ばず、アメリカ人にとってもこのような車で生活をエンジョイすることが「アメリカン・ドリーム」であったのだと思う。
BuickもPontiacもGMの車であったが、GMの作る最高級車であるCadillacは、当時の占領軍の最高司令官であるダグラス・マッカーサー元帥の乗用車として日本国民にもよく知られていた。このCadillacに一度だけ思いがけないことで乗ったことがある。1960年代の初頭、私は大阪大学の大学院生だったが、大学院入試の時の試験官であった赤堀四郎先生がまもなく大阪大学の総長になられて、その公用車がCadillacだった。丸みを帯びた車体で「ウィキペディア」の「キャデラック」で見ると、戦後型として写真の出ている「シリーズ59(1948年)」のようであった。ある日のこと、どういう成り行きでそうなったのか、またどこまで行ったのかまったく記憶に残っていないが、赤堀先生に「乗りなさい」と言われてそのCadillacでどこかに連れて行かれたのである。赤堀研にいた友人と一緒であったことだけははっきりと記憶している。ただそれだけのことであるが、それにしてもこのCadillacがどういう経緯で大阪大学に迷い込んできたのだろう。かなりの年代物であったように思う。
1966年に初めて渡米して中古車を買うことになった時に、ディーラーで一台のCadillacが目に留まった。かなり年代が古いがシートが総革製で窓の開閉が電動式なのである。予算は遙かにオーバーしていたが無理をすれば手の届く範囲なので一時は迷ったが、身の程知らずにそんなことを考える自分が滑稽になって止めた。その時に買った中古のFord・Futuraがトラブル続きで、Santa BarbaraからLos Angelesに出かけた帰り道に遂に動かなくなり、再生エンジンに取り替えることになった。その際に代替車として借りた大型車(多分フォード・ギャラクシー)の性能に感激したものである。ちょっとアクセルを踏み込むだけで、それまではよたよたと上っていた101のかなりの急坂を、他車をいとも易々と追い越しながら一気に駆け上がったからである。ガソリンをがぶ飲みしての頑張りであったのだろう。
1980年代の初め、デトロイトで一夏過ごしたことがある。週末になるとレンタカーであちらこちらを飛び回ったが、GM本社のあるルネッサンス・センターにもよく出かけた。映画館が何軒もありいつも長い行列が出来ているのが印象的だった。まだアメリカ映画が元気であったのだろう。どのビルだったか覚えていないが、その上にある回転レストランで食事をした覚えがある。昨夜、テレビニュースでこの一帯の夜景が写っていたが、ルネッサンス・センターとデトロイト川対岸のカナダ・ウィンザー市の灯火の輝きに、このレストランからの展望が重なってとても懐かしかった。デトロイト川をトンネルでくぐり抜け、カナダに入ってトロント辺りまでは何遍も足を伸ばしたものである。レンタカーはアメ車だった。日本の小型自動車の対米輸出が第一次石油ショック(1973年)、第二次石油ショック(1979年)を経て大幅に増加したことがいわゆる自動車摩擦を引き起こしていた。テレビでも日本車を米国人がハンマーでたたき壊すパフォーマンスが流されたこともあり、米国人が「デトロイト不況」と呼んでいた日米間の自動車摩擦が最高潮に達していたので、わざわざ日本車を乗り回して米国人を刺激することを避けたつもりであった。その後米国景気の回復につれて自動車需要が増大したものの、この間ビッグスリーのうち、何とか持ちこたえたGMがその体質改善に積極的でなかったと言われる。そういうことが今回の破局の淵源なのだろうか。
世界的に苦境にある自動車産業の行方に私は少々冷淡である。もうそろそろ次の新しい移動手段が現れてきてもいいのではないかと思うせいかもしれない。子供の頃何回も読み返した講談社の絵本に「魔法の杖」(?)と言うのがあった。目をつむってステッキをくるくると回しながら行き先を唱えると、次の瞬間にはもうそこに着いているのである。究極の移動手段ではなかろうか。私も呪文だけはよく唱えたものだ。せいぜい動き回るだけに車のような大げさな機械・装置を人間が作るのは、まだ知能が低いレベルに留まっているせいだろう。あの小さな身体で何千キロも移動する渡り鳥の飛翔能力ひとつを考えてみても、手つかずの研究領域があるように思う。