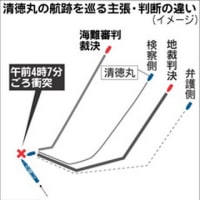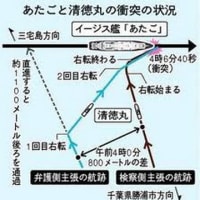夕べ(8月16日)もさんまの「恋のからさわぎ」を観ていた。この番組とは長いお付き合いで、その経緯を以前ブログに書いたことがあるが、要するに私は亜流ではあるが(男という意味で)みいはあ族なのである。番組はいつも世界的文化人の箴言を奇妙きてれつなコントで演じることから始まるが、夕べはウイリアム・ハズリットの言葉が引用されていた。私は彼の書いたものをかって目にしたことはないが、脳中にインプットされていたその名前がにわかに甦り、昔のことをあれこれ思い出してしまった。というのも私はかって彼の住んでいた家に滞在したことがあったからである。
ウイリアム・ハズリットとは研究社の新英和大辞典(第六版)に《Hazlitt, William(1778-1830) 英国の批評家・随筆家》と出ているくらいだから、かなり著名な人物なのだろう。その彼が住んでいた家を「The Time Out London Guide」は次のように紹介している。

そう、かって彼が住んでいた築300年の家がB&Bタイプのホテルになっていたのである。1990年10月、私が英国で開かれる会議に招待されたのを機に、妻をロンドンに伴うことになり、その時に少し変わったB&Bのほうが面白かろうと選んだのがこのホテルであった。会議が開かれる場所はロンドンから列車で3時間ほど離れたところにあり、そこで3泊ほどする予定になっていた。その間、妻はロンドンに残って美術館巡りをしたいと云っていたので、Sohoの中にあり、動き回るのにも便利だし周辺には各国料理のレストランが多いこのホテルを拠点とすることにして9泊10日の予約を入れた。

タクシーで辿り着きチェックインを済ませて部屋に案内された。まず驚いたのが狭い周り階段を上っていく時に身体が倒れかけるような錯覚を覚えたことである。階段のステップが水平でなかったせいである。さらに部屋のドアが明らかに傾いているのに隙間が見えない。隙間を丁寧に木切れで埋めているのである。三百年の重みで建物の中身がかなり傾いていたが、それなりの手入れが行き届いているようであった。部屋にはベッドルームに居間、それに浴室・洗面所があり、心地よく落ち着ける感じだった。ドアには部屋名のプレートがあって私のはPrussian Blueの間だったように思う。浴室の様子は上の写真とは違っているが、浴槽の設えは同じようである。

到着した夜、荷物の片付けもそこそこに食事を摂りに外出した。ところが部屋に戻ってくるとなんだか様子がおかしい。散らかして出たはずなのに部屋が綺麗に片付き、スーツケースなども納まるべき場所に納まっている。あれっと思ってスーツケースを開くとなんと空っぽなのである。泥棒がこんなに綺麗に後始末するとは思えないので、時代物のタンスの引き出しを開けてみると、下着に着替えから小物に至までものの見事にびしっと整理されている。これにはびっくり仰天した。さすが鍵をかけたままのバッグ類には手をつけていなかった。
私はそれまでにもロンドンには何度も来ており、B&Bはもちろん一般のホテルも利用している。しかしこのような経験は初めてだった。なんだか由緒ありげなホテルと云うことで選んだのであるが、まさかこのようなサーヴィスまで含まれているとは思いも寄らなかった。しかし一方では考えた。これはサーヴィスのように泊まり客に思わせて、メイドが自分の好奇心を満たすために、お遊びでこのようなことをしたのだろうか。いやいや、そう疑った客がマネージャーに文句を云ったとすると、このような行為はすぐにばれてしまう。そのようなことをメイドがするはずがない、やっぱりサーヴィスなんだろうか、とあれやこれや考えた末、結局黙ることにした。
それにしてもわが身が丸裸にされた感じだった。そういえば日本でも殿様とかお姫様とか高貴なお方は湯殿でも前を隠すなど品格を貶めるようなまねはせずに、なにごともオープンに堂々とお付きの者に世話をさせたという話を思い出した。そのお殿様お姫様扱いをして貰っているんだ、と思うことにしたのである。あれがサーヴィスだったのかからかわれたのか、いまだに分からない。
ホテルのパンとコーヒが美味しかった。地下の調理場で焼き上げたパンと熱いコーヒを毎朝メイドが三階の部屋までコトコトと足音を立てながら持ってきてくれる。肉厚のコーヒカップがよかった。私が家で愛用している砥部焼とその頑丈な実用性が共通していたからである。底を見ると「APILCO FRANCE」と記されていた。英国製ではなくてフランス製だった。

Shaftesbury Avenueだったと思うが、偶然APILCOの製品を山積みにしていた厨房器具店で同じカップを見つけたので何点か買った帰った。気に入ったのでその後、別の機会に一式を買い求めて別送したことである。面白いことに先日佐渡裕プロデュースのメリーウイドウが西宮の芸文センターで公演された時に、テレビで佐渡さんの日常生活が紹介されて、そのなかにパリのカフェでコーヒを飲んでいるシーンがあった。よく見るとカップがこのAPILCOなのである。それにつられてわが家でもAPILCOにコーヒを入れた。

私が三、四日ロンドンを離れて会議に出席していた間、妻はこのホテルを根城に美術館を中心にあちらこちら行き廻ったようである。食事、とくに夕食をどうしたのか、聞いたような気がするがまったく覚えていない。考えてみるともう18年前の話である。今でもHazlitt’s Hotelは健在なのだろうか。また訪れたい気がする。
ウイリアム・ハズリットとは研究社の新英和大辞典(第六版)に《Hazlitt, William(1778-1830) 英国の批評家・随筆家》と出ているくらいだから、かなり著名な人物なのだろう。その彼が住んでいた家を「The Time Out London Guide」は次のように紹介している。

そう、かって彼が住んでいた築300年の家がB&Bタイプのホテルになっていたのである。1990年10月、私が英国で開かれる会議に招待されたのを機に、妻をロンドンに伴うことになり、その時に少し変わったB&Bのほうが面白かろうと選んだのがこのホテルであった。会議が開かれる場所はロンドンから列車で3時間ほど離れたところにあり、そこで3泊ほどする予定になっていた。その間、妻はロンドンに残って美術館巡りをしたいと云っていたので、Sohoの中にあり、動き回るのにも便利だし周辺には各国料理のレストランが多いこのホテルを拠点とすることにして9泊10日の予約を入れた。

タクシーで辿り着きチェックインを済ませて部屋に案内された。まず驚いたのが狭い周り階段を上っていく時に身体が倒れかけるような錯覚を覚えたことである。階段のステップが水平でなかったせいである。さらに部屋のドアが明らかに傾いているのに隙間が見えない。隙間を丁寧に木切れで埋めているのである。三百年の重みで建物の中身がかなり傾いていたが、それなりの手入れが行き届いているようであった。部屋にはベッドルームに居間、それに浴室・洗面所があり、心地よく落ち着ける感じだった。ドアには部屋名のプレートがあって私のはPrussian Blueの間だったように思う。浴室の様子は上の写真とは違っているが、浴槽の設えは同じようである。

到着した夜、荷物の片付けもそこそこに食事を摂りに外出した。ところが部屋に戻ってくるとなんだか様子がおかしい。散らかして出たはずなのに部屋が綺麗に片付き、スーツケースなども納まるべき場所に納まっている。あれっと思ってスーツケースを開くとなんと空っぽなのである。泥棒がこんなに綺麗に後始末するとは思えないので、時代物のタンスの引き出しを開けてみると、下着に着替えから小物に至までものの見事にびしっと整理されている。これにはびっくり仰天した。さすが鍵をかけたままのバッグ類には手をつけていなかった。
私はそれまでにもロンドンには何度も来ており、B&Bはもちろん一般のホテルも利用している。しかしこのような経験は初めてだった。なんだか由緒ありげなホテルと云うことで選んだのであるが、まさかこのようなサーヴィスまで含まれているとは思いも寄らなかった。しかし一方では考えた。これはサーヴィスのように泊まり客に思わせて、メイドが自分の好奇心を満たすために、お遊びでこのようなことをしたのだろうか。いやいや、そう疑った客がマネージャーに文句を云ったとすると、このような行為はすぐにばれてしまう。そのようなことをメイドがするはずがない、やっぱりサーヴィスなんだろうか、とあれやこれや考えた末、結局黙ることにした。
それにしてもわが身が丸裸にされた感じだった。そういえば日本でも殿様とかお姫様とか高貴なお方は湯殿でも前を隠すなど品格を貶めるようなまねはせずに、なにごともオープンに堂々とお付きの者に世話をさせたという話を思い出した。そのお殿様お姫様扱いをして貰っているんだ、と思うことにしたのである。あれがサーヴィスだったのかからかわれたのか、いまだに分からない。
ホテルのパンとコーヒが美味しかった。地下の調理場で焼き上げたパンと熱いコーヒを毎朝メイドが三階の部屋までコトコトと足音を立てながら持ってきてくれる。肉厚のコーヒカップがよかった。私が家で愛用している砥部焼とその頑丈な実用性が共通していたからである。底を見ると「APILCO FRANCE」と記されていた。英国製ではなくてフランス製だった。

Shaftesbury Avenueだったと思うが、偶然APILCOの製品を山積みにしていた厨房器具店で同じカップを見つけたので何点か買った帰った。気に入ったのでその後、別の機会に一式を買い求めて別送したことである。面白いことに先日佐渡裕プロデュースのメリーウイドウが西宮の芸文センターで公演された時に、テレビで佐渡さんの日常生活が紹介されて、そのなかにパリのカフェでコーヒを飲んでいるシーンがあった。よく見るとカップがこのAPILCOなのである。それにつられてわが家でもAPILCOにコーヒを入れた。

私が三、四日ロンドンを離れて会議に出席していた間、妻はこのホテルを根城に美術館を中心にあちらこちら行き廻ったようである。食事、とくに夕食をどうしたのか、聞いたような気がするがまったく覚えていない。考えてみるともう18年前の話である。今でもHazlitt’s Hotelは健在なのだろうか。また訪れたい気がする。