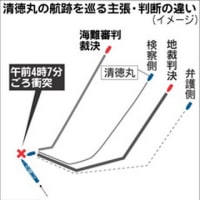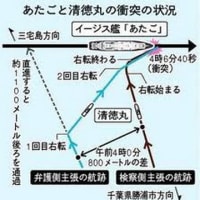先週の「箏の名曲はキリシタン音楽」という「題名のない音学会」はなかなか楽しかった。箏曲「六段」がグレゴリオ聖歌「クレド」に似ているということから、「六段」のもとになったのが「クレド」ではなかろうかと話が展開し、また舞台の上で実際に「クレド」と「六段」が合奏された。両者がよく調和していたというか、違和感なく渾然一体となっていることに驚いた。箏の旋律が聖歌のメロディーから外れているところも琴歌のようであったが、「六段」にもともと詞はない。その理由も説明されていたが、いずれにせよこの日演奏された皆川達夫指揮の中せ音楽合唱団と野坂操壽による箏合奏のCDが出ていることが分かったので、さっそくアマゾンで取り寄せた。

和文46ページ、英文42ページ、計88ページの懇切な解説から、当日話された内容を改めて学ぶことが出来た。以下はそのまとめである。
箏曲「六段」は義務教育で鑑賞曲に取り上げられているとのことで、だから耳にされた方も多いのであろうが、残念ながら私はこれまでまともに聞いたことがなく、今回、このCDで聞いたのが始めてである。その教科書には「八橋検校作曲」と記されているようであるが、他にも北島検校や倉橋検校、さらには築紫箏曲の賢順作曲の説まであるようである。この冊子にある久保田敏子さんの解説によると、
とのことである。八橋検校が江戸幕府がキリスト教を禁止したその翌年に生まれているので、彼の生きていた当時、ヨーロッパ音楽のすべての楽譜・楽器は廃棄されていたのである。
この「六段」について皆川さんはすでにその著書「中世・ルネッサンスの音楽」(講談社現代新書、1977)で
と述べている。皆川さんはさらに論考をすすめ、
に至ったのである。そしてラテン語聖歌「クレド」が400年前のキリシタン期に日本で歌われていたのかと検証をすすめ、1600年印刷の「おらしょ翻訳」の解読にもとづき、当時のキリシタンにとって「クレド」を暗記して唱え歌うことは必須不可欠のものと結論した。そしてこのように話を進める。
長い引用になってしまったが、これで「クレド」からどのような経緯で歌詞をもたない器楽曲「六段」が生まれたのか、簡にして要を得た説明となっている。「六段」の一段を百四拍に決めたことで、「クレド」と「六段」の寸法がピッタリと合うのである。
これに付けたりを加えると、皆川さんは触れていないが、吉川英史著「日本音楽の歴史」(創元社、1965年)に次のような注目すべき記事がある。
皆川さんのその意味では傍証を固められたのである。またさきほどの久保田敏子さんの解説の中に次のようなくだりがあった。
奔放な発想で私などは共感を覚えるが、それよりもこの大西善明先生が、奇しくも私の一弦琴の師、大西一叡先生のご夫君とは不思議な因縁である。一叡先生は箏曲山田流からご夫君の勧めに従い一弦琴に入られた方で、当然ご夫君は「六段」の調べに折に触れて耳を傾けられたことであろうと推察する。もしかして一叡先生は学会での発表のいきさつなど、ご存じなのかも知れない。
ついでに言うと徳弘太著「清虚洞一絃琴譜」には、おそらくは太師の採譜によると思われる「六段」が収められている。歌を伴わない一弦琴は私の主義に反するが、折りを見てチャレンジする気になった。

和文46ページ、英文42ページ、計88ページの懇切な解説から、当日話された内容を改めて学ぶことが出来た。以下はそのまとめである。
箏曲「六段」は義務教育で鑑賞曲に取り上げられているとのことで、だから耳にされた方も多いのであろうが、残念ながら私はこれまでまともに聞いたことがなく、今回、このCDで聞いたのが始めてである。その教科書には「八橋検校作曲」と記されているようであるが、他にも北島検校や倉橋検校、さらには築紫箏曲の賢順作曲の説まであるようである。この冊子にある久保田敏子さんの解説によると、
《六段》の曲名が初めて文献に登場するのは、八橋検校(1614-85)の没後70年目にあたる宝暦5(1755)年に出た箏組歌の楽譜集『撫箏楽譜集』で、《六段之調子》とある。
とのことである。八橋検校が江戸幕府がキリスト教を禁止したその翌年に生まれているので、彼の生きていた当時、ヨーロッパ音楽のすべての楽譜・楽器は廃棄されていたのである。
この「六段」について皆川さんはすでにその著書「中世・ルネッサンスの音楽」(講談社現代新書、1977)で
ところで日本の箏曲の開祖八橋検校の作に<六段の調べ>という曲があり、日本伝統音楽には珍しく純器楽的な発想をみせ、しかも「主題と五つの変奏曲」とでもよぶべき変奏曲の形式―日本音楽には異例の形式によっている。これを十六世紀スペインふうによべば「六つのディフェレンシアス」―すなわち「六段」である。
と述べている。皆川さんはさらに論考をすすめ、
本CDは、それよりさらに踏みこんで、箏曲『六段』の成立にあたりラテン語聖歌『クレド(信仰宣言)』の影響が決定的に大きかったという問題を提起する。
に至ったのである。そしてラテン語聖歌「クレド」が400年前のキリシタン期に日本で歌われていたのかと検証をすすめ、1600年印刷の「おらしょ翻訳」の解読にもとづき、当時のキリシタンにとって「クレド」を暗記して唱え歌うことは必須不可欠のものと結論した。そしてこのように話を進める。
キリシタン時代の日本の典礼においてラテン語聖歌、その中でもとくに重視された「クレド」は楽器の伴奏付で歌われていた。
この事柄をさらに推しすすめると、当時のキリスト教教会や修道院の典礼において楽器演奏を担当した日本人の奏者が、練習のため、自らの楽しみのため、あるいは自己の心情の表明、さらにはキリスト教の信仰表白のために、自分が担当したヴィオラ・ダルゴなど、また時には彼が得意とした日本の伝統楽器の箏や琵琶などを取り上げて、聖歌のメロディ、なかでも重要視されていた「クレド」をパラフレーズしつつ独奏しようと思い立ち、実際にそれを試みた可能性は十二分にありえた状況であった。
「クレド」のメロディを箏で弾いてみようと思い立ったというこのアイディアに最初に気付いたのは、九州大牟田市ご在住の箏曲家坪井光枝様であった。その件を示唆された筆者は「クレド」と「六段」との楽譜対照表を作成し、されにキリシタン時代の日本において「クレド」が占めていた重要性、また当時のキリスト教典礼において聖歌歌唱を楽器で伴奏し補強するのが普通であったとする記録類を検証してきた。
この事柄をさらに推しすすめると、当時のキリスト教教会や修道院の典礼において楽器演奏を担当した日本人の奏者が、練習のため、自らの楽しみのため、あるいは自己の心情の表明、さらにはキリスト教の信仰表白のために、自分が担当したヴィオラ・ダルゴなど、また時には彼が得意とした日本の伝統楽器の箏や琵琶などを取り上げて、聖歌のメロディ、なかでも重要視されていた「クレド」をパラフレーズしつつ独奏しようと思い立ち、実際にそれを試みた可能性は十二分にありえた状況であった。
「クレド」のメロディを箏で弾いてみようと思い立ったというこのアイディアに最初に気付いたのは、九州大牟田市ご在住の箏曲家坪井光枝様であった。その件を示唆された筆者は「クレド」と「六段」との楽譜対照表を作成し、されにキリシタン時代の日本において「クレド」が占めていた重要性、また当時のキリスト教典礼において聖歌歌唱を楽器で伴奏し補強するのが普通であったとする記録類を検証してきた。
このああたりで、おぼろげながら一人の人物の姿がのほ見えてきたように思われる。その彼は、箏の名手として令名をはせていた。彼がキリスト教の信仰を宣言するラテン語聖歌「クレド」のメロディに、どこで出合ったかは定かでない。たまたま訪問したキリスト教教会で聞き知ったのか。あるいは、その彼はキリスト教信徒として洗礼を受け、自ら楽器を取ってミサ典礼における「クレド」歌唱の伴奏をしていたのか。それもあきらかではないが、当時の検校には少なからぬキリスト教信徒がいたといわれる。
その名前がなんであれ、名手であった彼は箏の上でラテン語聖歌「クレド」メロディの幻想的なパラフレーズ、「ディフェレンシアス」ふうの変奏を試み、それが契機となって新曲「六段」が成立したと思われる。
その曲が声楽曲であれば、キリスト教的な歌詞が歌われるために弾圧時代に破棄されてしまったことであろう。場合によっては、作者であるその彼の生命にも拘わる一大事が起こりえたかもしれない。しかし、曲が純器楽曲であり、歌詞を一切もたないことろから弾圧をかいくぐり抜け、現代まで生命を保ち継承されてきた。
その曲が声楽曲であれば、キリスト教的な歌詞が歌われるために弾圧時代に破棄されてしまったことであろう。場合によっては、作者であるその彼の生命にも拘わる一大事が起こりえたかもしれない。しかし、曲が純器楽曲であり、歌詞を一切もたないことろから弾圧をかいくぐり抜け、現代まで生命を保ち継承されてきた。
長い引用になってしまったが、これで「クレド」からどのような経緯で歌詞をもたない器楽曲「六段」が生まれたのか、簡にして要を得た説明となっている。「六段」の一段を百四拍に決めたことで、「クレド」と「六段」の寸法がピッタリと合うのである。
これに付けたりを加えると、皆川さんは触れていないが、吉川英史著「日本音楽の歴史」(創元社、1965年)に次のような注目すべき記事がある。
ただここに興味のあることは、「箏曲に現在も残っている”六段の調べ”などの器楽曲は、当時輸入した洋楽の器楽曲の影響を受けて作曲されたものであろう」という仮説を田辺尚雄(1883年8月16日 - 1984年3月5日、日本の音楽学者、文化功労者)先生からしばしば聞くのであるが、傍証がない限り、私にはまだ信じられない。(177ページ)
皆川さんのその意味では傍証を固められたのである。またさきほどの久保田敏子さんの解説の中に次のようなくだりがあった。
今はもう故人であるが同志社高校の大西善明先生が、かって東洋音楽学会で、「《六段》の六は南無阿弥陀仏の六字の御名に拠ったものではないか」と発表され、会場で失笑が聞こえたことがあったが、その命名もあるいは、キリシタン音楽の出所を煙に巻く弁明の一つだったのかもしれない。
奔放な発想で私などは共感を覚えるが、それよりもこの大西善明先生が、奇しくも私の一弦琴の師、大西一叡先生のご夫君とは不思議な因縁である。一叡先生は箏曲山田流からご夫君の勧めに従い一弦琴に入られた方で、当然ご夫君は「六段」の調べに折に触れて耳を傾けられたことであろうと推察する。もしかして一叡先生は学会での発表のいきさつなど、ご存じなのかも知れない。
ついでに言うと徳弘太著「清虚洞一絃琴譜」には、おそらくは太師の採譜によると思われる「六段」が収められている。歌を伴わない一弦琴は私の主義に反するが、折りを見てチャレンジする気になった。