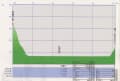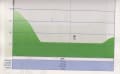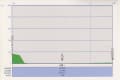トムラウシ山遭難事故
2009年7月16日、トムラウシ登山者15名、添乗員3名の内、9名が低体温症で死亡した事件。
参加者15名の性別は男性5人、女性10人。その年齢は、50~60才。
一行は、天人峡温泉から旭岳を経て大雪山系の主稜線を縦走し、トムラウシ温泉へ下山する2泊3日の登山予定でした。
行動予定は下の地図赤線です。

そのおおよその日程は次の通りです。
登山1日目(7月14日 ):
旭岳温泉 - (旭岳ロープウェイ) - 姿見平駅 - 旭岳 - 間宮岳 - 北海岳 - 白雲岳避難小屋 - 白雲岳 - 白雲岳避難小屋(泊)
登山2日目(7月15日):
白雲岳避難小屋 - 高根ヶ原 - 中別岳 - 五色岳 - 化雲岳 - ヒサゴ沼避難小屋(泊)
登山3日目(7月16日):
ヒサゴ沼避難小屋 - 日本庭園 - 北沼 - トムラウシ山 - トムラウシ公園 - 南沼 - 前トム平 - トムラウシ温泉
最初の二日間は、大体予定通り進みましたが、
次の7月16日からが台風の中の強行軍のようでした。
報告書の要旨では
「7月16日
午前3時半起床。午前5時の出発予定であったが、天候悪化のため雨と風が強く、待機。
ガイドらはラジオで十勝地方の予報『曇り、昼過ぎから晴れ』と聞き、
午後から天候は好転すると見越して出発を決定。


一行は午前5時半頃に避難小屋を出発。
ヒサゴ沼の窪地から稜線に出ると風速20~25m(90Km/h)の強風をモロに受けて転ぶ人が続出。先頭のガイドの声が最後尾まで届かない状況。
ガイドからは『風が強く吹いたらとにかくしゃがんで』と繰り返し指示。
通常なら3時間のところを6時間近くかけて山頂下の北沼に到着。
しかし大雨で沼から溢れた水が大きな川(幅約2m、水深は膝ぐらいまで)となり登山道を横切って居た。
川の中に立ったガイドの助けを借り何とか渡りきるが、ここで多くの人がずぶ濡れになった。(実際はガイドだけがずぶぬれで、他はそうでもなかった様子)
午前10時半頃、北沼の川を渡ったすぐ先の分岐手前で女性1人が低体温症のため歩行困難となった。
一行はガイドの指示によりその場で1時間半待機させられた。
座り込んだ人を囲んで風よけを作ったり、『寒い、寒い』と叫び声を上げる女性客も居た。
結局パーティはツエルト(小型のテント)を設営しガイド(リーダー)を残して先に進んだ。
前設営地から距離を置かずして別の女性客1人が意識不明に陥った。
ここで岩陰を探してテントを設営。
この女性に加えて歩行困難になった女性客2人と付き添いの男性客1人、ガイド(メインガイド)の計5人がこの場でビバーグ(緊急野営)することとなった。
登山客と付き添いのガイド(添乗員)はトムラウシ山頂を迂回し西側の平坦なコースで下山を続行した。
この時ガイドは遅れた人を待つことなく大急ぎで進んだため列が伸びて全員を確認できなくなったという。・・・
この時点(午後三時ごろ)で霧や雲で視界は悪いが雨や風は弱まっていたという。・・・」
遭難事故にまでならなくて済ンだでしょうに、
残念でしたね。(他のパーティーはOKのようでした。)
その原因を後でたどってみましたが、
1) 天候判断のミス、そして早めに引き返す決断のミス、
2) にわかづくりのチーム、現場での協議不足、
3) 「安全優先」が実際には「経済優先」、
4) ツアー参加希望者の選定(経済優先)、
5) 着用すべき防寒着の指示・確認不足、
6) 「低体温症」に対する認識不足
等々の要因が重なって起きた事故のようです。
後ではなんとでも言えますが・・・。