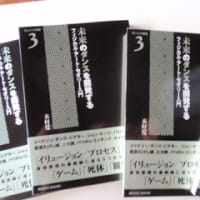多摩美での講義。3回目。まだ全然慣れない。1月になっても慣れない気がする。235名の単位登録者のいる階段教室で、一体どう緊張しないで話ができるというのだろう!階段教室の下の方で深海魚の気分。アンコウみたいに自分で自分に光をともしてしゃべる。どこみて話したらいいか分からないので、うろうろと、ときどきうえのほおーに顔を向ければ突然、太陽のような何かで眩しい!と、見ればプロジェクターの光源だったりして。ただ、考えてみるとこんな機会、今後そうないことなのかもしれない。毎週、200人ほどの観客の前でソロ・ライヴをやっているパフォーマーはそうは多くないのでは。それを一年で30回くらいするのだ。そのときそのときの気分を記しておくと、「シアター」について考えている自分のためにちょっとはなるのではないだろうか(そう、最近、ダンス批評と言うより、シアター批評とでも言うべきものをやっているのでは、自分は、という気分になっている)。
今日は、狩生くんのDVDを見せようと思って用意していたのだが、まだ機材になれず音声がでなくて流せなかった。残念。今日は、狩生くんの「国ドットコム」はもっていったのに、「キャンプ」の例として見せようとしたマーサ・グラハムは忘れてしまった。「キャンプ的な目が認めるのは、その人物の統一性であり力である。年老いたマーサ・グラハムは、一挙手一投足においてマーサ・グラハムを演じているといった風だ」(ソンタグ「キャンプについてのノート」より)。ソンタグ曰くキャンプは「経験の演劇化」ということで、シアトリカリティ(アンチシアトリカリティ)の話の延長で、キャンプをとりあげた。何も用意せず観客の前に立ち困るという狩生くんのパフォーマンスもぼくにとっては「シアトリカル」な状況の大事なサンプル(そのもっとも裸出的な!)なのだった。
ただし、今日のメインは「アヴィニヨンの娘たち」を論じるレオ・スタインバーグの議論だった。アンチシアトリカルであろうとする閉じたモダニズム(フリード的)的絵画とは対照的な開いた絵画とでもいうべきシアトリカルな絵画としてスタインバーグは、「娘」を取り上げ、そしてモダニズムの偏狭さから離れ、絵画と見る者とが交わす自由でダイナミックな空間をそこに見て取る。
「「ラス・メニナス」のように、「アヴィニヨンの娘たち」において、どの二人をとってみても、われわれ見る者を無視してお互いに交流し合っている人物はいない。そして中央の三人は、見る者に直接にどんどん語りかけてくる。彼らは能動的でも受動的でもなく、ただ警戒しているのであり、われわれが彼らに注ぐ注視にこたえている。ここには物語的で客観的な行動から、見る者に中心をおいた経験への移行があらわれている。見る者が誘われて構成要素となるのだから、この絵は自存的な抽象絵画ではない。そして「アヴィニヨンの娘たち」の構成を封じ込められた絵画構成と分析するならば、それは作品を十分に直視していないからである。この絵は女性の攻撃性の高波であり、人はこの絵を攻撃として経験するか、あるいは受けつけないかどちらかなのである。しかし、見る者に対する攻撃は行動の半分にすぎない、というのは、この絵が画面のこちら側の見る者に包みかけようとするので、見る者も同じやり方でお返しをするからである。」(スタインバーグ)
講義後に、リヒターの作風の内にはアンチシアトリカルな要素があるように思う、と質問というか意見をしてくれた学生がいて、刺激になった。本当は、あらゆる絵画、というよりもあらゆるパフォーマンスを「シアトリカル」の視点からみていくといいし、それをしてはじめてこの議論はファンクショナルになるはずだ。
今日は、狩生くんのDVDを見せようと思って用意していたのだが、まだ機材になれず音声がでなくて流せなかった。残念。今日は、狩生くんの「国ドットコム」はもっていったのに、「キャンプ」の例として見せようとしたマーサ・グラハムは忘れてしまった。「キャンプ的な目が認めるのは、その人物の統一性であり力である。年老いたマーサ・グラハムは、一挙手一投足においてマーサ・グラハムを演じているといった風だ」(ソンタグ「キャンプについてのノート」より)。ソンタグ曰くキャンプは「経験の演劇化」ということで、シアトリカリティ(アンチシアトリカリティ)の話の延長で、キャンプをとりあげた。何も用意せず観客の前に立ち困るという狩生くんのパフォーマンスもぼくにとっては「シアトリカル」な状況の大事なサンプル(そのもっとも裸出的な!)なのだった。
ただし、今日のメインは「アヴィニヨンの娘たち」を論じるレオ・スタインバーグの議論だった。アンチシアトリカルであろうとする閉じたモダニズム(フリード的)的絵画とは対照的な開いた絵画とでもいうべきシアトリカルな絵画としてスタインバーグは、「娘」を取り上げ、そしてモダニズムの偏狭さから離れ、絵画と見る者とが交わす自由でダイナミックな空間をそこに見て取る。
「「ラス・メニナス」のように、「アヴィニヨンの娘たち」において、どの二人をとってみても、われわれ見る者を無視してお互いに交流し合っている人物はいない。そして中央の三人は、見る者に直接にどんどん語りかけてくる。彼らは能動的でも受動的でもなく、ただ警戒しているのであり、われわれが彼らに注ぐ注視にこたえている。ここには物語的で客観的な行動から、見る者に中心をおいた経験への移行があらわれている。見る者が誘われて構成要素となるのだから、この絵は自存的な抽象絵画ではない。そして「アヴィニヨンの娘たち」の構成を封じ込められた絵画構成と分析するならば、それは作品を十分に直視していないからである。この絵は女性の攻撃性の高波であり、人はこの絵を攻撃として経験するか、あるいは受けつけないかどちらかなのである。しかし、見る者に対する攻撃は行動の半分にすぎない、というのは、この絵が画面のこちら側の見る者に包みかけようとするので、見る者も同じやり方でお返しをするからである。」(スタインバーグ)
講義後に、リヒターの作風の内にはアンチシアトリカルな要素があるように思う、と質問というか意見をしてくれた学生がいて、刺激になった。本当は、あらゆる絵画、というよりもあらゆるパフォーマンスを「シアトリカル」の視点からみていくといいし、それをしてはじめてこの議論はファンクショナルになるはずだ。