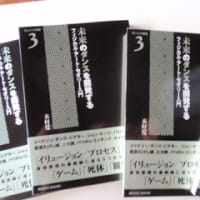もう少しブログ更新のペースを速めたいなあと心で思いつつ、まったく実行できず。8月は論文書くのにからだぼろぼろになりました(あまりよくない感じのできものとか顔に出来たりして)。
artscapeの八月分がアップされました
8月は月末に体調を悪くしたりして、大事な二本を来月回しにしてしまいました。Chim↑Pomの「Imagine」とロロの「ボーイ・ミーツ・ガール」です。あと、プレビューを提出し忘れました!しばしお待ちを。
ところで、快快がチューリッヒの演劇フェスティバルで賞をとったそうです。おめでとう!
9/2-3に青森旅行に行ってきました。
十和田市現代美術館と青森県立美術館をはじめて見てきました。しかし、1日目、なんと十和田は、メンテナンスのために臨時休館してまして、なかに入れなかった(泣)のですが、それでも、ガラス張りの建物の構造故に、なかに入らずしてかなりの作品を(なんとなくですが)見ることが出来ました。窓越しのロン・ミュエクおばさんetc.。道を隔てた向かいの公園には、草間彌生の作品がジャングルジムや動物の乗り物のように展示してあって、美術館が日常へと広がってゆく感じがとても面白く、なるほどこうやって現代美術を活用する方法があるのかと思いました。2日目の青森県立美術館も、現代美術の今日的なあり方について考えさせられる展示でした。奈良美智の展示。よかった。奈良の強さをすごく感じた。美術史的文脈から自由に、躍動する子供たち。とくに今回は、音楽との関係が気になった。ギターを下げた子供の絵の下に「1.2.3.4」と数字が書いてある。どうみても、これは曲のはじまるときのかけ声だ。見ていると、かけ声が聞こえてくる。それはきっと「パンク」ミュージックを聞いたことのある者ならば誰の頭からも聞こえてくる声だろう。そこに理屈はない、誰もが感じられる躍動だけがある。あと、そうした情熱の絵画化と関連するのだけれど、奈良には宗教性がある(キェルケゴール曰く「信仰は人間にとって最高の情熱」)。村上隆には、こうした側面が希薄だ。奈良にしかできないこと。ここに、なにやら興味深い秘密が隠されているように思われる。
Iは「嵐を呼ぶ男」で、退院する日も、妻の実家から引っ越す日も嵐のような天気だったが、今回も1日目の夕方、突如、台風上陸のニュースが入って驚かされた。2日目の午前中、八甲田山を登って降りる間、嵐に見舞われた。
なんとかキェルケゴール論文脱稿。「國學院雑誌」に掲載予定。キェルケゴールのことを考える機会にはなったけれど、ドゥルーズのこと(主に「生成変化」や「シネマ」のミュージカル映画論)とミュージカル映画(ジーン・ケリー論)のことまで展開できなかった。そのあたりについて、もう一本、夏休み中に書きたい。
とかいって、目下のところ、課題は泉太郎論。秋に彼の個展があり、それに向けて書いてます。
それと、室伏鴻について論考を依頼されているので、それもやらねば(8月のsnacで突如上演された「常闇形」はよかったっすよ~~~)。
あと、アウトサイダーアートについても考えたくて、実は今一番勉強したいのがこれで、さてそんなあれこれ考えているとまたからだがあちこち凝ってきた、でも「アート・アフター・アート」(「アート」が終わった後のアート)について本気で考えなきゃな感じが益々高まっている、そんな気がしてしょうがないのですよ。
artscapeの八月分がアップされました
8月は月末に体調を悪くしたりして、大事な二本を来月回しにしてしまいました。Chim↑Pomの「Imagine」とロロの「ボーイ・ミーツ・ガール」です。あと、プレビューを提出し忘れました!しばしお待ちを。
ところで、快快がチューリッヒの演劇フェスティバルで賞をとったそうです。おめでとう!
9/2-3に青森旅行に行ってきました。
十和田市現代美術館と青森県立美術館をはじめて見てきました。しかし、1日目、なんと十和田は、メンテナンスのために臨時休館してまして、なかに入れなかった(泣)のですが、それでも、ガラス張りの建物の構造故に、なかに入らずしてかなりの作品を(なんとなくですが)見ることが出来ました。窓越しのロン・ミュエクおばさんetc.。道を隔てた向かいの公園には、草間彌生の作品がジャングルジムや動物の乗り物のように展示してあって、美術館が日常へと広がってゆく感じがとても面白く、なるほどこうやって現代美術を活用する方法があるのかと思いました。2日目の青森県立美術館も、現代美術の今日的なあり方について考えさせられる展示でした。奈良美智の展示。よかった。奈良の強さをすごく感じた。美術史的文脈から自由に、躍動する子供たち。とくに今回は、音楽との関係が気になった。ギターを下げた子供の絵の下に「1.2.3.4」と数字が書いてある。どうみても、これは曲のはじまるときのかけ声だ。見ていると、かけ声が聞こえてくる。それはきっと「パンク」ミュージックを聞いたことのある者ならば誰の頭からも聞こえてくる声だろう。そこに理屈はない、誰もが感じられる躍動だけがある。あと、そうした情熱の絵画化と関連するのだけれど、奈良には宗教性がある(キェルケゴール曰く「信仰は人間にとって最高の情熱」)。村上隆には、こうした側面が希薄だ。奈良にしかできないこと。ここに、なにやら興味深い秘密が隠されているように思われる。
Iは「嵐を呼ぶ男」で、退院する日も、妻の実家から引っ越す日も嵐のような天気だったが、今回も1日目の夕方、突如、台風上陸のニュースが入って驚かされた。2日目の午前中、八甲田山を登って降りる間、嵐に見舞われた。
なんとかキェルケゴール論文脱稿。「國學院雑誌」に掲載予定。キェルケゴールのことを考える機会にはなったけれど、ドゥルーズのこと(主に「生成変化」や「シネマ」のミュージカル映画論)とミュージカル映画(ジーン・ケリー論)のことまで展開できなかった。そのあたりについて、もう一本、夏休み中に書きたい。
とかいって、目下のところ、課題は泉太郎論。秋に彼の個展があり、それに向けて書いてます。
それと、室伏鴻について論考を依頼されているので、それもやらねば(8月のsnacで突如上演された「常闇形」はよかったっすよ~~~)。
あと、アウトサイダーアートについても考えたくて、実は今一番勉強したいのがこれで、さてそんなあれこれ考えているとまたからだがあちこち凝ってきた、でも「アート・アフター・アート」(「アート」が終わった後のアート)について本気で考えなきゃな感じが益々高まっている、そんな気がしてしょうがないのですよ。