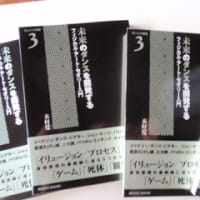昨日は、Iをお風呂に入れると、まずは原宿へ。蓮沼執太「ニューイヤーコンサート」。Iが生まれて間もない頃、妻は実家に戻っていて、車で毎日三十分かけて、実家に通っていた。その頃、よく聴いていたのが「wanna punch!」で、このアルバムからの曲がはじまると、あのときの生まれたての赤ん坊を湯浴みさせていたときの湯気の感じとか思い出してしまった。猛烈に明るく前向きな世界。新生児によく似合うなあとあらためて思う。今回、ユーフォニュームやビオラ、バイオリンが加わった演奏で、生音によって引き出されているのだろう生命感がいつもよりも輝いていた。蓮沼くんの音楽は、ぼくにとってはだから生まれたての生命みたいに感じるのだ。蓮沼くんが「さん、はい!」と演奏中に声をあげると、それはまるで、音楽という生き物がその瞬間だけ人間の口を宿して、声をもらしているみたいだ。フレーズがいいんだよなあ。キャッチーでポップで、けれども、初めて聴くフレーズ。絵画で言えば、線のかたちみたいなフレーズは、丹念に鍛え上げられた末に出てきたもののようにも、呼吸をするように自然に生まれたもののようにも思われる。
その後、まだ時間があるな(とはいえ、さすがに神村恵の昼の回は終わってるし)と思って、裏原宿を久しぶりにぶらぶらしている内に、ワタリウム美術館まで来てしまった。藤本壮介「山のような建築 雲のような建築 森のような建築」を見ることにした。ぼくは「山のような建築」よりも山が好きだな、と基本的には思う。都会でそういう建築でヴァーチャルに(理念的に)山を楽しむくらいなら、リアルな山に行って、登ったり下ったり、汗かいて、けがして、その多様性を堪能したい。ピュアな理念を夢想して、それを建築というかたちで具体化してゆくというのは、リアルな場所でもまれずしてイメージに耽溺する童貞性を感じる行為だなどと思いながら(2階の透明な円筒形のパーツを雲のように造形した建築は、こわれそうで、すわってもいいよ、ってなっているところはじっさいすわれない感じだったりした。なんて無知なまま書くと、建築の専門家に怒られそうだけれど。養老天命反転地はすきなんだけどな。あれは「山としての建築」というより、隠喩的ではなく山の建築だった。)、そういう理念を仮設してその仕組みを試演して行くというのがモダニズムだとすれば、それはそれでありなのかもしれないし、そんな風に思い返すと、ダンスと建築の近さなんてことに考えが及んで、いろいろと刺激を受けたりもする。ところで、ぼくには建築への憧れがほとんどない。10年くらい前に本郷の風呂・トイレなし3万のアパートも虫がわいて大変だったけれどそれはそれで楽しかったし、鶴川の2Kもいまに比べれば狭くてかなわなかったが、いろいろ工夫をする楽しさがあった。いまは広いところに住めているけれど、これが理想なのかは分からない、不便なことも多い。「自分の住み家」意識がそんなにないんだと思う。どこにいたって、どこも「仮の宿り」でしかない。
その後、荻窪へ。駅近くのまる福で中華麺を食べて、会場へ。着くと、解説を受けるが、数日前にもらったメールに書いたあった概要に変更があるという。リハもなく、本番へ。
ここからの内容は、お越しいただいた方々へ向けて書きます。本当は、本番直前の打ち合わせでは、パフォーマンス後にトークの予定がちゃんとあったのです。けれども、ご存じのように、調整に四苦八苦した結果、パフォーマンスだけで三時間近くかかってしまったので、そんな時間なくなってしまったわけです。けれども、泉太郎とまっとうにトークが出来るなどと思ってはいけない、ということも重々承知していました。ぼくは泉くんを「野生の小動物」と称することがありますが、そうしたとらえ難さというものについて考えると面白いと思うんです。作家の中には、ぼくのような批評の立場で話しやすい人と話しにくい人がいます。ダンサーや振付家の中にはそういうひとが多いです。「全身パフォーマー」のような人間は他人の目に触れている間は一秒たりともパフォーマーであることをやめません。延々と裏をかき、本心を悟らせるなんてことはしない。土方巽はそういうひとだった、といえるかもしれない。泉くんは、ちょっとそういうマジシャンなところがあると思うんです。美術作家は、自分の身体ではなく身体から切り離したキャンバスみたいなマテリアルで表現できるので、作品と自分を切り離し、批評家のように自分の作品を流暢に語ることが可能かもしれません。例えば、小林耕平さんとはぼくは会話が出来ます。小林さんの場合、禅問答のような謎をパフォーマンス空間に置き、その問いに応答するべく試行を繰りかえす作品が近年目立っていますが、ここでは、謎は小林さんの外部にあります(その謎をそこに置いたのはたしかに小林さんなのですが)。観客は小林さんと同じ立場にあるかのように、その謎を向き合います。泉くんの場合は、泉くんそのものが謎の発生源です。だから、泉くんが何かを話すとすれば、それはマジシャンが自分の種を明かすようなもので、それは基本的に聞かない方がいい、聞かなくていい、ことなのです。あるいは、マジシャンのいう種明かしなので、実はそこでは何も明かされないかもしれない、それもひとつのマジックなのかもしれない。そうであるべき、そうであってほしい、ものなのです。
だからぼくは内心、原宿でうろうろしながら「トークどうしよう」と思っていました。結果的に時間切れでトークがうやむやになった。それこそが、泉くんのトリックだったのかもしれません。(ぼくの泉太郎論は『こねる』展のカタログに書きましたので、これをご一読いただけたらと思います。Nadiffなどで販売しているはずです。)
それにしても、満員の大盛況。泉くん人気を再認識しました。あと、女子率の高さにも驚き、このあたりが泉太郎の本質かなとも思わされ。とはいえ、終演後見に来ていたKATのメンバーに「蓮沼さん行けばよかった、と思った時間があった、、、」といわれてしまいました。さすが身内は厳しい!
その後、まだ時間があるな(とはいえ、さすがに神村恵の昼の回は終わってるし)と思って、裏原宿を久しぶりにぶらぶらしている内に、ワタリウム美術館まで来てしまった。藤本壮介「山のような建築 雲のような建築 森のような建築」を見ることにした。ぼくは「山のような建築」よりも山が好きだな、と基本的には思う。都会でそういう建築でヴァーチャルに(理念的に)山を楽しむくらいなら、リアルな山に行って、登ったり下ったり、汗かいて、けがして、その多様性を堪能したい。ピュアな理念を夢想して、それを建築というかたちで具体化してゆくというのは、リアルな場所でもまれずしてイメージに耽溺する童貞性を感じる行為だなどと思いながら(2階の透明な円筒形のパーツを雲のように造形した建築は、こわれそうで、すわってもいいよ、ってなっているところはじっさいすわれない感じだったりした。なんて無知なまま書くと、建築の専門家に怒られそうだけれど。養老天命反転地はすきなんだけどな。あれは「山としての建築」というより、隠喩的ではなく山の建築だった。)、そういう理念を仮設してその仕組みを試演して行くというのがモダニズムだとすれば、それはそれでありなのかもしれないし、そんな風に思い返すと、ダンスと建築の近さなんてことに考えが及んで、いろいろと刺激を受けたりもする。ところで、ぼくには建築への憧れがほとんどない。10年くらい前に本郷の風呂・トイレなし3万のアパートも虫がわいて大変だったけれどそれはそれで楽しかったし、鶴川の2Kもいまに比べれば狭くてかなわなかったが、いろいろ工夫をする楽しさがあった。いまは広いところに住めているけれど、これが理想なのかは分からない、不便なことも多い。「自分の住み家」意識がそんなにないんだと思う。どこにいたって、どこも「仮の宿り」でしかない。
その後、荻窪へ。駅近くのまる福で中華麺を食べて、会場へ。着くと、解説を受けるが、数日前にもらったメールに書いたあった概要に変更があるという。リハもなく、本番へ。
ここからの内容は、お越しいただいた方々へ向けて書きます。本当は、本番直前の打ち合わせでは、パフォーマンス後にトークの予定がちゃんとあったのです。けれども、ご存じのように、調整に四苦八苦した結果、パフォーマンスだけで三時間近くかかってしまったので、そんな時間なくなってしまったわけです。けれども、泉太郎とまっとうにトークが出来るなどと思ってはいけない、ということも重々承知していました。ぼくは泉くんを「野生の小動物」と称することがありますが、そうしたとらえ難さというものについて考えると面白いと思うんです。作家の中には、ぼくのような批評の立場で話しやすい人と話しにくい人がいます。ダンサーや振付家の中にはそういうひとが多いです。「全身パフォーマー」のような人間は他人の目に触れている間は一秒たりともパフォーマーであることをやめません。延々と裏をかき、本心を悟らせるなんてことはしない。土方巽はそういうひとだった、といえるかもしれない。泉くんは、ちょっとそういうマジシャンなところがあると思うんです。美術作家は、自分の身体ではなく身体から切り離したキャンバスみたいなマテリアルで表現できるので、作品と自分を切り離し、批評家のように自分の作品を流暢に語ることが可能かもしれません。例えば、小林耕平さんとはぼくは会話が出来ます。小林さんの場合、禅問答のような謎をパフォーマンス空間に置き、その問いに応答するべく試行を繰りかえす作品が近年目立っていますが、ここでは、謎は小林さんの外部にあります(その謎をそこに置いたのはたしかに小林さんなのですが)。観客は小林さんと同じ立場にあるかのように、その謎を向き合います。泉くんの場合は、泉くんそのものが謎の発生源です。だから、泉くんが何かを話すとすれば、それはマジシャンが自分の種を明かすようなもので、それは基本的に聞かない方がいい、聞かなくていい、ことなのです。あるいは、マジシャンのいう種明かしなので、実はそこでは何も明かされないかもしれない、それもひとつのマジックなのかもしれない。そうであるべき、そうであってほしい、ものなのです。
だからぼくは内心、原宿でうろうろしながら「トークどうしよう」と思っていました。結果的に時間切れでトークがうやむやになった。それこそが、泉くんのトリックだったのかもしれません。(ぼくの泉太郎論は『こねる』展のカタログに書きましたので、これをご一読いただけたらと思います。Nadiffなどで販売しているはずです。)
それにしても、満員の大盛況。泉くん人気を再認識しました。あと、女子率の高さにも驚き、このあたりが泉太郎の本質かなとも思わされ。とはいえ、終演後見に来ていたKATのメンバーに「蓮沼さん行けばよかった、と思った時間があった、、、」といわれてしまいました。さすが身内は厳しい!