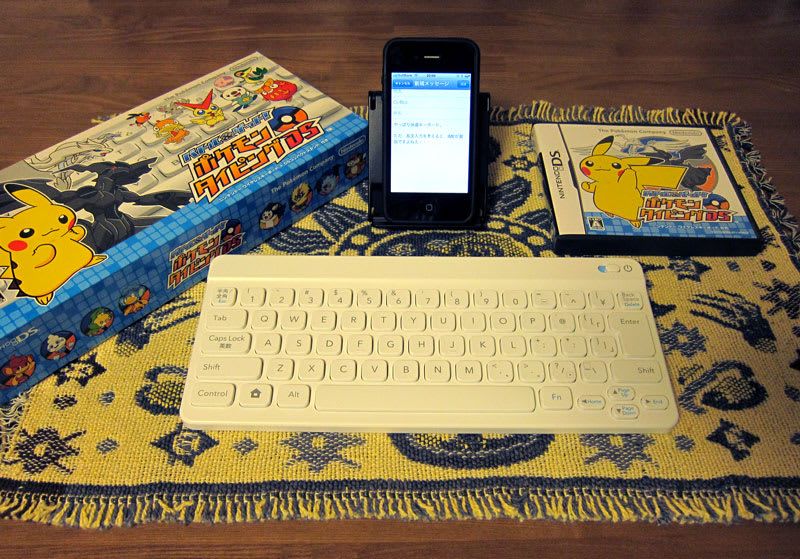携帯電話のパケット定額プラン、これが無いことには恐ろしくてスマホなんて使っていられません。「PCのモデムとして数時間使ったら、とんでもない額が請求された」なんて話はもはや「パケット通信は怖い」という話の定番ですが、そのPCと同じくらいのデータ量をやりとりするスマホは、正にパケット通信定額は必須です。
そのパケット通信定額プランですが、多くの場合上限と下限が設けられています。全然使わない月は下限で、徐々に使っていくと上がっていき、上限になったら加算が止まるというアレです。通常の携帯電話だと、ネットを使わないと本当に下限に納まることも少なくないため合理的なシステムに見えますが、実はiPhoneを初めとするスマートフォンでは意味が無かったという話が波紋を広げています。
未利用 iPhone のパケット問題、総務省実験では4台中3台が上限に到達 engadget
iPhoneがなにもせずともソフトバンクのパケット定額プラン下限を突破する件、事態はもっと深刻でした。NHKニュースによれば、総務省が用意した4台のiPhoneのうち、3台が「インターネットをまったく使っていないのに」パケット定額の「上限」にまで達したとのこと。
スマートフォンは、ユーザーが何もしなくても、OSが勝手にサーバーとやりとりをしているため、いつの間にかパケット通信量が上限まで達していることがあると言うことですが・・・
これって詐欺くさいとも思いますけれど、自分の使い方だとどう頑張っても上限に張り付いてしまうため、あんまり関係ないと言えばそれまで。そもそも、常に一定のプランに乗り換えましたし。
それ以前に、この事態は元々「使ったか、そうでないか」程度のしきい値でしかない上限・下限の設定方法に問題があるのではないですかねえ。他社の後追いでやってきた結果と言えばそれまでですが、通常の携帯電話とはパケット通信量が段違いのスマホにおいて、
ちなみに「パケットし放題 for スマートフォン / 標準プライスプラン」の上限である4410円に達するのは5万2500パケット利用時。ざっくり6.5MBぶんくらい。
高解像度の写真数枚を見たらおしまいくらいの通信量で上限に達してしまう料金体系なら、むしろ設定しない方が良いですよね・・・
これを見るに、これからは二段階性は段階的に廃止になっていくのではないでしょうか?とりあえず、スマホに関しては「よほど特殊な使い方をしない限り、意味無し」な訳ですしね。