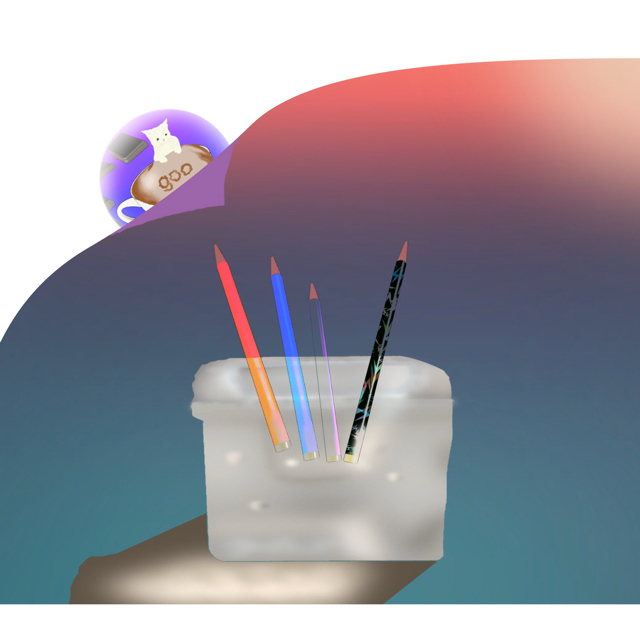「昨日はじめて宇宙人を見てね」
「へー」?
「よさげだったよ」?
「……」
「……」
その先があるのかと思いきや、
どうやら何もないようだ。
あなたはそれきり黙り込んでしまった。
私は相槌を間違えたようにも思う。
私たちはそれぞれに見えない台本を持ち合っている。
共通の台本を持てば、次がどちらの番かは互いにわかる。
それによって会話は円滑に進んでいく。
けれども、台本を読み誤れば台詞に穴が空く。
次の台詞が行方不明になり会話が終わってしまう。
「へー」そこが問題だ。
返しの達人は相手の警戒を解いて台本を膨らませる。
「へー」には少し情熱と真心が足りなかった。
言葉を引き出す力が不足していた。
あなたは宇宙人を見たとしか言わなかった。
本当はもっと言いたいことがあったのでは……。
「えーっ!」
まずは驚きをもっと示すべきだった。
そしてあなたの身を案じるべきだった。
あなたは既にあなたではなくなっているかもしれない。
「へー」?
「よさげだったよ」?
「……」
「……」
その先があるのかと思いきや、
どうやら何もないようだ。
あなたはそれきり黙り込んでしまった。
私は相槌を間違えたようにも思う。
私たちはそれぞれに見えない台本を持ち合っている。
共通の台本を持てば、次がどちらの番かは互いにわかる。
それによって会話は円滑に進んでいく。
けれども、台本を読み誤れば台詞に穴が空く。
次の台詞が行方不明になり会話が終わってしまう。
「へー」そこが問題だ。
返しの達人は相手の警戒を解いて台本を膨らませる。
「へー」には少し情熱と真心が足りなかった。
言葉を引き出す力が不足していた。
あなたは宇宙人を見たとしか言わなかった。
本当はもっと言いたいことがあったのでは……。
「えーっ!」
まずは驚きをもっと示すべきだった。
そしてあなたの身を案じるべきだった。
あなたは既にあなたではなくなっているかもしれない。