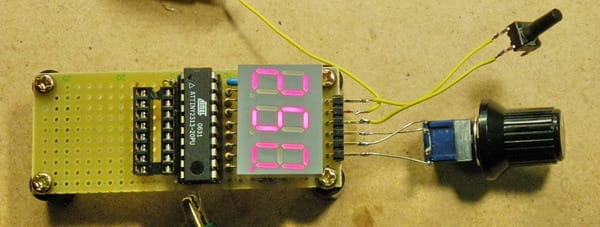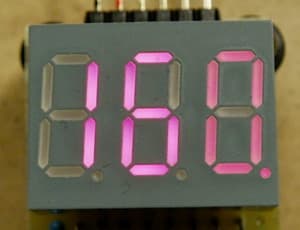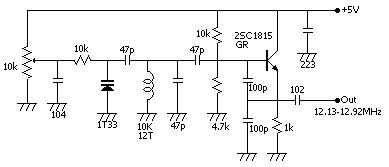その14です。
12MHzPLLVFOができたので、20MHzのVXOを作りました。
12MHz台と混合して32MHz台にするとともに、20MHzをVXOとして1kHzステップの間をカバーします。
混合はTA7310Pを活用することにしたので、TA7310Pの発振回路を利用しました。
基板です。
当初はTR2石でのVXOを試作したのですが、DBMでの混合も面倒なので、頂いたTA7310Pを使うことにしました。
コイルが2つ乗るので、この基板では小さいですね。

バリキャップは何種類かジャンク箱に常備してはいるのですが、通常のダイオードでもバリキャップの代わりになるものがある、とのことなので、バリキャップで動作確認した後で、取り替えて実験してみました。
1S1588っぽいシリコンダイオードの中にもバリキャップとして使えるものがありました。
整流用の大き目のダイオードもいいかんじで使えることが分かりました。
ゲルマダイオードは全滅でした。
色々試してみましたが、緑地に茶と黒のラインが入った謎のダイオードの可変範囲がバリキャップ並みだったので、これを使うことにしました。
このダイオードは沢山あるので、バリキャップの代わりにパラにしたりして使えそうです。
上から3番目です。

可変範囲は3.9μHのLを使用して2.9kHzほど確保できました。
上の方は詰まっているので、下の2kHzくらいがいいところです。
12MHzPLLVFOができたので、20MHzのVXOを作りました。
12MHz台と混合して32MHz台にするとともに、20MHzをVXOとして1kHzステップの間をカバーします。
混合はTA7310Pを活用することにしたので、TA7310Pの発振回路を利用しました。
基板です。
当初はTR2石でのVXOを試作したのですが、DBMでの混合も面倒なので、頂いたTA7310Pを使うことにしました。
コイルが2つ乗るので、この基板では小さいですね。

バリキャップは何種類かジャンク箱に常備してはいるのですが、通常のダイオードでもバリキャップの代わりになるものがある、とのことなので、バリキャップで動作確認した後で、取り替えて実験してみました。
1S1588っぽいシリコンダイオードの中にもバリキャップとして使えるものがありました。
整流用の大き目のダイオードもいいかんじで使えることが分かりました。
ゲルマダイオードは全滅でした。
色々試してみましたが、緑地に茶と黒のラインが入った謎のダイオードの可変範囲がバリキャップ並みだったので、これを使うことにしました。
このダイオードは沢山あるので、バリキャップの代わりにパラにしたりして使えそうです。
上から3番目です。

可変範囲は3.9μHのLを使用して2.9kHzほど確保できました。
上の方は詰まっているので、下の2kHzくらいがいいところです。