
私の最も尊敬する作家といえる石牟礼道子の本は、絶版本も多いので古書などで手に入り次第に次々と読んできましたが、この『西南役伝説』という著作のことはこのたび実際に読んでみるまではずっと誤解していました。
どこかで目にした解説文から、地元に伝わる西南役伝説を石牟礼道子が解説紹介したような本かの印象をもっていたのです。
それも、日本という国が近代の入り口に立った明治維新のころ、近代化にひたすら盲目的に邁進する明治政府に対して、ただひとり待ったをかけた西郷隆盛の言葉「草花の匂う国家」という表現に石牟礼道子が何か共鳴するところがあって書いたものかのようなイメージを勝手にもっていました。
ところが実際に読んでみたら、まったくそのような性格のものではないばかりか、代表作『苦界浄土』と双璧をなすといっても良いほど石牟礼道子の世界観が表現された大事な著作だったのです。
最初、朝日新聞社より上の写真のものが1980年に刊行され、のちに朝日選書に入りましたが、2009年に洋泉社新書にも加わりました。その後長い間品切れのままでした。それが、このたびNHK大河ドラマ「西郷どん」の放映に合わせてか、講談社文芸文庫で2018年に復刊されることになりました。
そもそも、この出会いのきっかけは、ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞して世界を驚かせたのに続いて、イギリス在住のカズオ・イシグロがノーベル文学賞を受賞したことでした。
そこで、他の文学賞と比べたり、過去の日本の受賞者やまたその受賞の噂のあった人びとなどを比べてみたとき、ノーベル文学賞って、いったい何を見ているのだろうかと思い、書店でフェアを企画してみたことにはじまります。

フェアでは、このパネルに掲げたような作家たちの本をまとめたのですが、並べてみるほどにやはり多くの他の文学賞とノーベル文学賞の違いを感じずにはいられませんでした。
端的に言えば、文学の枠内で表現の力を競うのではなく、文学という表現手段を通じてその時代固有の世界像なり歴史像が圧倒的に反映されたものであるかどうかということです。もちろん、いかなる作品であっても時代を反映していないものなどないのですが、その格闘次元の違いを如実に感じるのです。
そうした意味で、石牟礼道子はこれらの日本人作家と比べてみても、現代文明への深い眼差し、表現スタイルの独自性など、どこをとってみても圧倒的な差が感じられるのです。
結果、このフェアの主題も並べていくうちに石牟礼道子が中心に並べられるように変わっていきました。
そんな最中、2月10日、石牟礼道子の訃報が飛び込んできたのです。

急遽、この写真のPOPの「翻訳の壁さえなければノーベル文学賞の最有力候補!」の部分に「でした」と手書きで付け加え、訃報を伝える新聞の切り抜きを貼り、「追悼 石牟礼道子」の表示を加えました。
たしかに石牟礼道子のノーベル文学賞受賞の可能性といっても、現実には熊本方言などの翻訳の壁が立ちはだかり、海外に知られにくいことがノーベル文学賞への道を遠ざけているかと思われますが、受賞如何にかかわらず、その力の差は歴然としています。
裏を返すと、どんなに世界で人気があっても村上春樹が受賞されない理由も、自ずと浮き上がってくるような気もします。
そうした評価は、以前このブログでも書いた池澤夏樹責任編集の「日本文学全集」で、現代の女性作家では石牟礼道子と須賀敦子のみが取り上げられたこと。さらに同シリーズの「世界文学全集」の日本人作家では、石牟礼道子のみが取り上げられたことなどでも十分うかがい知ることができます。
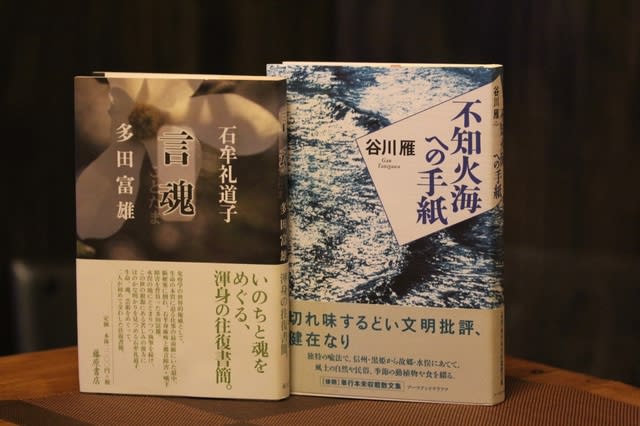
おそらく、 『西南役伝説』という著作への誤解は、私だけのことではないかと思われます。
つまり、「西南の役」を語るということ、さらにはそもそも歴史を語るということがどういうことなのか、石牟礼道子の表現に出会うまでは、大半の人たちは知らず、気づいていないからです。
舞台は確かに明治維新と西南の役のころの南九州です。
しかし、そこに官軍と西郷たちの戦闘や田原坂の様子などは、ほとんど出てきません。
明治政府と西郷との駆け引きなども一切語られません。
語られるのは、その戦乱の時代に翻弄されながらその地で生き抜くことだけに必死な農民や漁民たちの姿です。
また不知火海を挟んだ島原の地の過酷なばかりの歴史を背負った人たちの姿です。
後の東日本大震災以降の文章にはよりいっそう鮮明に語られるようになるのですが、そうした農漁民の姿と同等なものとして、その地に息づく草木やケモノや虫たちがあり、数多のただ生き延びることに必死なものたちの関係があります。
そして、そうしたその土地の中にある「日々の命の営み」にこそ、真の歴史の実態があるのだと。
そんな実像の描写がずっと続くのです。
「土地は海とともに、生命の母胎であると共に魂の依る所であり、いわば彼らの一切世界そのものであったろう。
ここでいう世界とは、下層農漁民たちが夢見うる至上の徳と情愛と、理(ことわり)とが渾然一体となった神仏の如きものが宿る深所、そこに魂をあずけて、共に統ベられると思える依り代として、経済基盤の今一つ奥に至る現世の足がかり、手がかりとして土地は観念されていたに違いない」

愛を語る、家族を語る、労働を語る、暮らしを語る、経済を語る、政治を語る、戦争を語る、自然・風土を語る、なんでも良いのですが、歴史や社会を語るというと、つい政治経済ばかりに目が行きがちですが、地球生命の歴史からすれば、人間の政治経済で担われている領域など生命の歴史では表面の薄い上澄みのなかのほんの一点に過ぎないものです。
そもそも私たちの存在は、天界宇宙の無限とも言える無機的自然の巨大な営みのなかにあります。
そのほんの奇跡の一点のなかで繰り広げられる、これまたその一点のなかの無限とも感じられる命の集積。
そうした人間の感覚ではおよそはかり知れない数多諸々の蓄積の上に私たちの生命の奇跡はあります。
近代社会は、そうした過去の生命の蓄積をほとんど顧みることなく、政治経済の都合を優先してあらゆるものを「ご一新」してきました。
歴史をつくり、またそれを目撃し、それを担ってきたのは、そうした「ご一新」を図ってきた一部の人たちの中にもあかるのかもしれませんが、圧倒的な部分はそれらに翻弄されながらも、生き抜くことを最優先にして生命の生産活動を続けてきた農民や漁民たち、さらには彼らの生活を無言で支えている草木や魚、鳥、ケモノたちなわけです。
ただ、その姿というのは、あまりにも過酷で悲しいものでもあります。
それは今日のビジネス書や自己啓発書で解決される「これをやればうまくいく」などといったようなものでは決してなく、そもそも人間のはかり知れない力のなかで、彷徨うことを運命づけられたような世界なのです。
東日本大震災の時、多くの人がそんな思いあらためてを感じました。
「花や何 ひとそれぞれの 涙のしずくに洗われて 咲きいずるなり」
お店のフェアのなかでも、東日本大震災の折に書いた詩「花を奉る」が載っている藤原新也との共著『なみだふるはな』(河出書房新社)は、本来たくさん売りたいところでしたが、残念ながら現在品切れで仕入れることができませんでした。追悼を機会に重版されることを期待します。
庶民のくらしを重視したヒューマニズムの世界観は、トルストイばかりでなく世界どこにも見られるものですが、農林漁業などの生産者が同時に草木や虫、魚、鳥、ケモノたちにまでつながった生命と魂の連環としてあるという世界観は、おそらく日本に際立たものがある気がします。
それを石牟礼道子は、自然史、人間史、さらには魂の歴史のようなものを区別することなく描ききっているのです。
たしかに石牟礼道子のどの著作を見ても、そうした世界観は一貫しています。
でも『西南役伝説』がそうした世界を如実に表現してものであるとは想像していませんでした。また実際、多くの石牟礼道子紹介文の中でも本書が重視されているものは、意外と少ないようです。
講談社文芸文庫より近日復刊されるこの機会に、『西南役伝説』が一人でも多くの方に読まれることを願います。

残念ながらお店にノーベル文学賞のコーナーを設けてから、石牟礼道子の本がそれほど売れているわけではありません。
訃報は悲しいしらせではありますが、近代の出口にあると言われる今、デジタル技術などによりさらに次の「ご一新」が始まり、暮らしのあらゆるものがまた変わろうとしています。
従来の価値観への疑問を東日本大震災の時に多くの人が感じたはずですが、その先に私たちが何を守り育てていかなければならないのか、石牟礼道子が私たちに遺してくれた遺産には、なおはかり知れないものがあります。
正林堂でのノーベル文学賞フェア「世界は日本の何を見ているのか」は、2月中旬までの予定ですが、石牟礼道子の追悼コーナーはしばらく継続します。
長野浩典著 『西南戦争 民衆の記』 弦書房 2376円も同様の視点で西南戦争をみつめた本と思われますが、まだ現物はみていません。
















