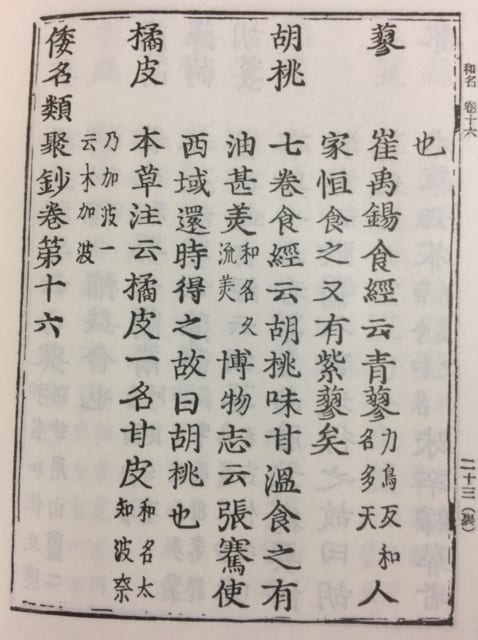宇根豊が、平均年齢72歳の百姓に、いつが一番楽しかったかと尋ねたところ、圧倒的に多くの百姓が昭和30年代の前半が一番充実していたと答えたそうです。
そのわけは「家族全員で仕事ができたから」
最近、何かにつけて私は、先の東京オリンピックの頃から日本中の風景(自然景観も人の心の風景も)が変わりだしたということを書いていますが、これほど本質をついた表現はありません。
最近、お店のパートさんと息子さんの進路の話をしていた時、長い目で見たら自営業、個人事業を立ち上げた方が、良い会社へ就職するよりもずっと良いと思うといったようなことを話したら、自分の子供は自営業には嫁には出したくない、と言われ改めてショックを受けました。
かつて国民の8割近くが農家であった時代、今思えばたしかに現金収入はサラリーマンに比べたら少ないので子育て養育費など不安は尽きなかったかもしれませんが、自営業が基本で成り立っていた社会であったことが、どれだけ強い地域を育てていたことかとつくづく感じます。
ところが先のパートさんに限らず、強い経済、強い地域社会をつくるためには、家族労働、自営・個人事業の比率を上げることこそが大事だ、などと言っても容易には受け入れられないことが多いので、とりあえず10年前に関わっていたNPOの場に出したレジュメを以下に転記しておきます。
8、9番目の項目は、今回書き加えたものです。
*** キーワード「家族」について ** *
映画や文芸作品などを通じてみる家族は、 もっぱら「家族愛」がその多くのテーマになっていますが、 地域社会の復興においても「家族」「家族労働」「個人事業」といったことがらは、極めて重要な意味を持つと感じます。
ここで家族というキーワードの「家族愛」以外の側面に注目して整理してみます。
1、高度な資本主義が発達した現代でも 、世界中の生産の基本的形態は、いまだに圧倒的多数が「家族労働」
・アジアに限らず、ヨーロッパの経営形態を見ても、 家族・血縁による経営形態は根強い。
人口構成比からみれば、世界の圧倒的多数が家族労働と個人事業。
巨大組織化した企業も、その実態の多くは膨大な下請け中小零細企業で成り立っている。
・家族・血縁にこだわらない組織形態が発展したのは 、
アメリカと日本が突出している
日本も血縁にこだわるが、養子という血縁を越えた組織が可能な稀な国
(企業社会につながる「家」、これは他に例がない)
最先端産業においても、時代のベクトルは「より小さく」の時代へ移ってきている。
今は過渡期:「一極集中の巨大化」と「分散化」の時代。
2、これまで企業に代表される大規規模生産こそが生産力発展の最大条件 とみられ、地域環境を支えていた個人事業、家族労働が限りなく企業に吸収されてきた歴史がある。
・初めに農業労働 → 都会の工業労働者へ
・地元の自営商業労働者→大型SCやスーパーマーケット、
チェーン店などの労働者(パート)へ
実際にこのことによって見かけの生産性は 飛躍的に増大してきた。
3、自然と社会の再生産を前提とした、膨大な量の無償の労働(自然からの贈与、人間による贈与)によって社会が成り立っていることを忘れて、 一次的な利益につながらないそうした労働をすべて切り捨て、疲弊した自然、地域社会や企業風土、家庭をつくってきてしまった。
・生産の基本部分は大自然からの贈与
この贈与に対して企業は対価を払っていない
略奪と破壊の繰り返しで、再生産の構造維持の費用負担をしてない)
電気・水道などの料金はもとより、化石燃料の消費は、大自然に対してその費用は払ってない。
これまで人類は、大自然の恩恵に対する尊敬、崇拝の念をもってその維持・再生産につとめてきた
この無償の労働の意義や価値を見失うことが 会社から帰ったら役に立たない多くの父親の姿を生んでいる。 会社の利益追求以外のたくさんの仕事が地域を支える。
4、安易な企業誘致や産業の育成よりも 、昔からその地に暮している人々による生業(なりわい) の復興支援の方が「強い地域」経済を育てることにつながる。 (大企業依存の地域経済が、いかに脆いものであるかは立証された)
個人事業・家族労働の生業(なりわい)は、もともと地域の再生産のために必要なことを不可分の業務として持っていた。 (国や行政にまかせることではなく、 自分たちのものとして必要とする作業)
企業誘致やベンチャー育成よりも、既存事業の復興、イノベーションの方が、決して簡単ではないが、はるかに容易い。 既存事業の復興の能力がないまま、新規事業に手を出しても成功しない。
5、家族労働、個人事業を中心にした経済構造のが、ワークシェアリングや地域福祉、高齢者の健康維持と生きがいのためにも効果が大きい。
ひとりの年収300万円、500万円で家庭を支える労働ではなく、 子どもからお祖父さんまでが、出来ることで支えあう構造 の意義。
福祉予算を増額することよりも、実際のメリットが多い。
生涯、自分が他人が喜んでくれることで、何をしてあげることができるのか。
持ち続けることが、生きがいになる。 (組織にうもれた肩書き人間が失ったもの)
6、単一労働の組み合わせによる分業化を推進する企業社会に対して、ひとりひとりが自分の作業を管理して「総合的」に生きていける姿は、人間の一生をみわたしたうえでも限りなく価値がある。
「製品開発」「製造」「営業」「販売」、「経理」は、個人事業において特別な意識を持つことなく 、一つの必要な一連の行程として行なっている。ここに本来の人間の営みの姿がある。
7、利害で結ばれた組織形態である企業にくらべて、地域コミュニティーや家族といった結びつきの関係は、たとえ条件の悪いことが多少あっても、「あきらめない」強さがあり、それが長い人間社会の歴史を築いてきたともいえます。
企業や団体などの組織 : 特定の利害で結びついた集団。 目的達成のための一定の資質や能力を要求する。
家族や地域 : 構成員の能力や資質にかかわりなく、 与えられた条件を天賦のものとして受け入れ、 多くの場合は、あきらめることのない関係を築きながら問題を解決していく。
8、「児童労働の禁止」は、労働環境の一般論としては正しいかもしれませんが、お父さん、お母さんと一緒に子どもが、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんが、家族として一緒に働けることは、限りなく尊い。
9、そもそも「生産」は、子供を産んで育てることを根幹とした「生命の再生産」の活動です。このことを忘れた「経済」が、生命の破壊をもたらす。
* 家族愛や文化、宗教などの精神活動も、この点から見ると、純粋なイデオロギー上の問題ではなく、地球と人類の再生産を維持するための生産活動の大事な一要素であることに気づきます。