数ヶ月前に購入したまま放ってあった、「茶の湯」入門という本に目を通した。 これまでは刀剣類の本ばかり読んでいたが、10年くらい前から茶器に興味あったので、何気なくこの本を購入した。 簡素で分かり易い本だが、その中の一部に興味をそそられた。
この本に一部掲載されていた「へうげもの」という漫画の数カットだ。 戦国時代末期~江戸時代初期頃まで、一世を風靡した茶人・古田織部正重然を主人公とした漫画で、数寄者をメインにした史実に基づいた素晴らしい作品に圧倒されてしまった。 「へうげもの」・剽げ者、茶のみならず、武士として人生の清濁を併せ飲みながら、数寄の道を究めていく。 一笑一笑、という笑いを求める姿に共感を持つ。
千利休、今井宗久、津田宗及を筆頭に、山上宗二、織田有楽斎や利休七哲・古田織部、蒲生氏郷、細川忠興、芝山監物、牧村兵部、高山右近、瀬田掃部や、荒木村重、有馬豊氏、上田主水正宗箇、小堀遠州らが活躍した、戦国時代における政の実態を感じ取る事のできる歴史教科書といっても過言ではない(一部創作有)。 面白い!の一言に尽きる。
従五位下織部正古田重然。 織部焼きは現在でも一般的に有名。 甲乙の「乙」を求める。

織田信長と豊臣秀吉の茶道頭を務めた千宗易。 「侘」を極めた。 シンプル&ブラック。
戦国末期の茶器トレンド図。
曜変天目の模様は、まるで宇宙の如し。 神宮神楽殿内にて別の曜変天目を拝観した時、心が吸い込まれそうになった。
高麗茶碗。 細川井戸は有名。
古田織部が美濃の窯で焼かせた、国産茶器。
典型的な織部焼き、茶器のみならず食器でも有名。 朝鮮の技術を取り入れたりして、唐津・上野・薩摩焼等が有名になる。
茶入れ。 一番有名な「九十九茄子」、足利義政から歴代の覇者が所有。 所有者は全員滅亡という不吉といえば不吉な茶器。
有名な三肩衝き「初花」、「新田」、「楢柴」の一つ「初花」。 美しい。
何はともあれ、漫画「へうげもの」は一読の価値有。
それでは、また。 ごきげんよう。











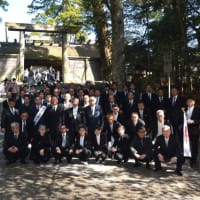















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます