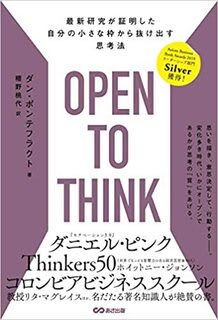
このダン・ポンテフラクトの本「OPEN TO THINK~最新研究が証明した 自分の小さな枠から抜け出す思考法 単行本」の原題は、Open to Think: Slow Down, Think Creatively and Make Better Decisions
OPEN TO THINK~ゆっくりと、クリエイティブ思考で、より良い決断を、と言ったところであろうか。
クリエイティブ(創造的)思考とクリティカル(批判的)思考とアプライド(実践的)思考を駆使してオープン思考に徹して、より良いディシジョンを目指すべき思考モデルを説いた非常に面白い本である。
この本では、新しい思考について、多くの興味深いケースが描かれているのだが、まず、興味を感じたのは、「眼前の現実を見誤ったディズニーのアニメ部門」についてのピクサーのジョン・ラセターの話である。
まず思い出したのは、日経出版のリチャード・S・テドロー著「なぜリーダーは「失敗」を認められないのか」という本である。
余談ながら、この本のタイトルの酷い誤訳から始めねばならないのだが、
この本の原題は、Denial: Why Business Leaders Fail to Look Facts in the Face---and What to Do About It で、”否認:何故ビジネス・リーダーは、眼前の現実を見誤るのか、そして、それに対処する方法”、と言うことである。
すなわち、「失敗」を認められないのではなくて、「眼前の現実・事実」を認知し誤ると言うこと、現実のみならず時代の潮流なり未来への展望が読めないと言うことなのであって、意味には雲泥の差がある。翻訳本のタイトルは、原題とは勿論、著者の意図とも中身とも全く違っていて、あのヘンリー・フォードでさえ、「眼前に展開していた経営環境の変化を直視せずに否認して経営を誤った」と言う論旨であって、失敗を認められないと言った次元のストーリーではないのである。
さて、ディズニーのプリンシパル・アドバイザーであったラセターが、ディズニーの未来について、何十年も前から変らない手書き一本での原画制作は、そろそろコンピュータで代替すべきではないかと考えて、コンピュータ・アニメ映画の最先端の発明について情報収拾して、上司に熱心に説明した。
しかし、経営陣は、ラセターの先見性あるビジョンを取り上げることなく、また、折角のアイデアを育み実現するための時間も与えずに、ラセターを解雇してしまった。デイズニーの経営者達は、硬直思考に嵌まり込んでいて、現実の世界やテクノロジーがどのように展開して行くのか、そして自分たちの将来を正しく見通すことが出来ずに、未来への行動を起こすチャンスを棒に振ったのである。
ラセターは、新設のピクサー・アニメーションで、キャトルマンやスティーブ・ジョブなどと肩を並べて、「ファインディング・ニモ」や「カーズ」や「トイ・ストーリー」などを監督・制作して名声を博し、ディズニーのピクサー買収とと同時に、チーフ・クリエイティブ・オフィサーとして古巣に戻った。
ここで、著者のポンテフラクトは、ディズニーの経営陣が、前述の正しい決断のために必要な「創造的思考」「批判的思考」「実践的思考」の対極にあるネガティブな「優柔不断思考」「無関心思考」「硬直思考」に陥って居たのであろうと言う。
ああでもない、こうでもないと、正しい意思決定に落ち着くまで時間を要して行動を起こせなかった「優柔不断思考」、
警鐘にも拘わらず、完全に無視して何もしなかった「無関心思考」、
あまりにも多忙すぎて、政策変更を考えるための十分な時間が取れなかった「硬直思考」
しかし、私は、デイズニーの経営者が、ICT革命、デジタル革命の潮流の早さと破壊的パワーの凄さを見通せなかった、すなわち、眼前に展開されている現実・事実・真実を見誤った、見通せなかったのだ思っている。
デジタル革命の凄さを見誤った最たる企業は、コダックであろうか。
同じフィルムメーカーでありながら、時代の潮流に上手く乗ってイノベーターとしてエクセレント・カンパニーに変身した富士フイルムとの差が興味深い。
フォードの敗因は、T型車に固守したことで、豊かになって行く顧客の嗜好の多様性に気づかなかったことであり、ディズニーやコダックの場合には、テクノロジーの激変であって、眼前の事実・現実の認識には違いがあるものの、今日のように時代の潮流が激しく激変すると、正しい判断など至難の業で、柔軟なオープン思考が、益々必要だと言うことであろうか。
OPEN TO THINK~ゆっくりと、クリエイティブ思考で、より良い決断を、と言ったところであろうか。
クリエイティブ(創造的)思考とクリティカル(批判的)思考とアプライド(実践的)思考を駆使してオープン思考に徹して、より良いディシジョンを目指すべき思考モデルを説いた非常に面白い本である。
この本では、新しい思考について、多くの興味深いケースが描かれているのだが、まず、興味を感じたのは、「眼前の現実を見誤ったディズニーのアニメ部門」についてのピクサーのジョン・ラセターの話である。
まず思い出したのは、日経出版のリチャード・S・テドロー著「なぜリーダーは「失敗」を認められないのか」という本である。
余談ながら、この本のタイトルの酷い誤訳から始めねばならないのだが、
この本の原題は、Denial: Why Business Leaders Fail to Look Facts in the Face---and What to Do About It で、”否認:何故ビジネス・リーダーは、眼前の現実を見誤るのか、そして、それに対処する方法”、と言うことである。
すなわち、「失敗」を認められないのではなくて、「眼前の現実・事実」を認知し誤ると言うこと、現実のみならず時代の潮流なり未来への展望が読めないと言うことなのであって、意味には雲泥の差がある。翻訳本のタイトルは、原題とは勿論、著者の意図とも中身とも全く違っていて、あのヘンリー・フォードでさえ、「眼前に展開していた経営環境の変化を直視せずに否認して経営を誤った」と言う論旨であって、失敗を認められないと言った次元のストーリーではないのである。
さて、ディズニーのプリンシパル・アドバイザーであったラセターが、ディズニーの未来について、何十年も前から変らない手書き一本での原画制作は、そろそろコンピュータで代替すべきではないかと考えて、コンピュータ・アニメ映画の最先端の発明について情報収拾して、上司に熱心に説明した。
しかし、経営陣は、ラセターの先見性あるビジョンを取り上げることなく、また、折角のアイデアを育み実現するための時間も与えずに、ラセターを解雇してしまった。デイズニーの経営者達は、硬直思考に嵌まり込んでいて、現実の世界やテクノロジーがどのように展開して行くのか、そして自分たちの将来を正しく見通すことが出来ずに、未来への行動を起こすチャンスを棒に振ったのである。
ラセターは、新設のピクサー・アニメーションで、キャトルマンやスティーブ・ジョブなどと肩を並べて、「ファインディング・ニモ」や「カーズ」や「トイ・ストーリー」などを監督・制作して名声を博し、ディズニーのピクサー買収とと同時に、チーフ・クリエイティブ・オフィサーとして古巣に戻った。
ここで、著者のポンテフラクトは、ディズニーの経営陣が、前述の正しい決断のために必要な「創造的思考」「批判的思考」「実践的思考」の対極にあるネガティブな「優柔不断思考」「無関心思考」「硬直思考」に陥って居たのであろうと言う。
ああでもない、こうでもないと、正しい意思決定に落ち着くまで時間を要して行動を起こせなかった「優柔不断思考」、
警鐘にも拘わらず、完全に無視して何もしなかった「無関心思考」、
あまりにも多忙すぎて、政策変更を考えるための十分な時間が取れなかった「硬直思考」
しかし、私は、デイズニーの経営者が、ICT革命、デジタル革命の潮流の早さと破壊的パワーの凄さを見通せなかった、すなわち、眼前に展開されている現実・事実・真実を見誤った、見通せなかったのだ思っている。
デジタル革命の凄さを見誤った最たる企業は、コダックであろうか。
同じフィルムメーカーでありながら、時代の潮流に上手く乗ってイノベーターとしてエクセレント・カンパニーに変身した富士フイルムとの差が興味深い。
フォードの敗因は、T型車に固守したことで、豊かになって行く顧客の嗜好の多様性に気づかなかったことであり、ディズニーやコダックの場合には、テクノロジーの激変であって、眼前の事実・現実の認識には違いがあるものの、今日のように時代の潮流が激しく激変すると、正しい判断など至難の業で、柔軟なオープン思考が、益々必要だと言うことであろうか。























