さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」からの転載です。天皇皇后両陛下が、いろんなところを訪問されてお声を掛けられる様子は、ほんとに思いやりの誠実さに富んでいいる気がします。相手のことを心から思われている気がします。だからお話しした人は涙を流しているのでしょう。公平とか無私とかいう言葉が、空論ではなく、ほんとに形に現れて実現した様を見るときには、感動が湧いてきます。天皇皇后両陛下は、そのようなお方である気がします。
転載開始



さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」からの転載です。天皇皇后両陛下が、いろんなところを訪問されてお声を掛けられる様子は、ほんとに思いやりの誠実さに富んでいいる気がします。相手のことを心から思われている気がします。だからお話しした人は涙を流しているのでしょう。公平とか無私とかいう言葉が、空論ではなく、ほんとに形に現れて実現した様を見るときには、感動が湧いてきます。天皇皇后両陛下は、そのようなお方である気がします。
転載開始



美しい国からの転載です。この記事は過去記事の投稿ということです。このブログでもその時に転載したかも知れませんが、このマレーシアの上院議員は戦前の日本を知っていて、その過去の日本と戦後の日本を比べて書いておられる詩ですから、私たちは謙虚に耳を傾けて、今の自分達の姿を反省するべきです。
この方はかつて日本は清らかで美しかったと言われています。自分たちの歴史と伝統に誇りをもって、そして亜細亜を何とかしたいと同じアジア人の意識を持って戦った日本人を美しいと言ってくださっています。
私たちの習った歴史と、こうした、東南アジアや南アジアの国々の方々の持つ日本のイメージがあまりに違うことに、日本人は気付こうとしません。侵略戦争と教えられて、信じ込んだままの日本が、ペコペコと謝る姿は、こうした国の方々には、何か見苦しく、堕ちた日本、経済繁栄のみ重視する我欲の塊のような情けない姿に映るようです。戦前の日本の美しさに憧れた人々には特にその思いが悔しさをもって感じられるのでしょう。
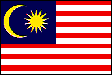

| ☆ 清らかで美しかった かつて 日本人は 親切でこころ豊かだった アジアのどの国の誰にでも 自分のことのように 一生懸命つくしてくれた * 何千万人もの 人のなかには
少しは 変な人もいたし
おこりんぼや わがままな人もいた
自分の考えを おしつけて
いばってばかりいる人だって
いなかったわけじゃない
*でも その頃の日本人は
そんな少しの いやなことや
不愉快さを越えて
おおらかで まじめで
希望に満ち明るかった
☆戦後の日本人は
自分たち日本人のことを
悪者だと思い込まされた
学校でも ジャーナリズムも
そうだとしか教えなかったから
まじめに
自分たちの父祖や先輩は
悪いことばかりした残虐無情な
ひどい人たちだったと 思っているようだ
*だからアジアの国に行ったら
ひたすら ペコペコあやまって
私たちはそんなことはいたしませんと
言えばよいと思っている
*そのくせ 経済力がついてきて
技術が向上してくると
自分の国や自分までが
えらいと思うようになってきて
うわべや 口先では
済まなかった悪かったと言いながら
ひとりよがりの
自分本位の えらそうな態度をする
そんな
今の日本人が 心配だ
☆本当に どうなっちまったんだろう
日本人は そんなはずじゃなかったのに
本当の日本人を知っているわたしたちは
今は いつも 歯がゆくて
くやしい思いがする
*自分のことや
自分の会社の利益ばかり考えて
こせこせと
身勝手な行動ばかりしている
ヒョロヒョロの日本人は
これが本当の日本人なのだろうか
*自分たちだけで 集まっては
自分たちだけの 楽しみや
ぜいたくに ふけりながら
自分がお世話になって住んでいる
自分の会社が仕事をしている
その国と 国民のことを
さげすんだ眼でみたり
バカにする
☆こんな ひとたちと
本当に仲よくしてゆけるだろうか
どうして
どうして日本人は
こんなになってしまったんだ
1989年
クアラルンプールにて
ラジャー・ダト・ノンチック
|
![]() 転載元: 美しい国
転載元: 美しい国
竹本忠雄先生の『パリ憂国忌』の文章から引用しました。三島由紀夫自刃から十年後くらいに出版された本です。一部、文章を書き直したり省略をしています。戦後の日本が進歩的文化人達によって、どういう姿勢で文化が発信されようとしていたかがよく分かります。
それにしても、この日本的なるものを、隠そうとする姿勢には驚くばかりです。敗戦による占領統治が、ここまで、日本人に日本的であることを嫌悪させるようになっていたことが、ショックですね。いまではこれほどではないでしょうが、武道も禅も、もうそれは古い日本で、そういう伝統的な文化は日本人の中の何かをよみがえらせるかもしれないと恐れたのでしょうか。そうしたものを切り捨てて、新しい日本は欧米的な文化のみを発展させようとしたのでしょう。自分の個性を否定する国民となった日本、何か痛ましい思いが強いですね。たしかに三島自刃があってから、このタブーが少しづつなくなってきた気がします。
一九七〇年十一月十二日、パリにいた私は一個の小包を受け取った。差出人は
三島由紀夫……
私は、三島由紀夫と出会ったことがなかった。いぶかしい思いで包みを解くと、華麗な箱入りの『豊饒の海』三冊が現れた。三冊とも「竹本忠雄様 三島由紀夫」と雄勁な筆致で献辞が入れられていた。
私は、感想でも書き送らねば申し訳ないと、一日延ばしに返事を怠っていたところ、二週間後に、日本大使館から電話がかかった。電話は三島由紀夫の自刃を知 らせてきて、フランスのジャーナリストが殺到して、大使館としては当事件にコメントする立場に無いので、竹本さんを紹介してもいいですかというのである。
私はフランスに住んで七年、常に日本の立場で、発言してきた。文化の「交流」なるものは、決して見かけほどには、優雅でも生やさしいものでもなく、時と場 合によっては「交戦」の様相をさえ呈しうるものである。事は、文化の優雅ではなく、武の果断に関わっている。事件の真相は窺うべくもなかったが、そこに 「暴力」を感じとったが最後呈されるであろうこの国の良識家の批難攻撃は、潮の遠鳴りにも似て、不安な矢ぶすまの音を遠く響かしめている。私は、自分が危 い一線に立っていると感じた。
しかし、ためらいはなかった。のみならず、昂揚の気持ちが涌然として身うちに興りつつあるのを感じた。
死を決した人が、その死の決行に先んじて、わざわざ航空便で畢生の大作を一面識もない異国の日本人に送りよこしたということは、なにごとかそこに託したい念願があったればこそではなかろうか?
「分かりました……」
と、思わず答えていた。
三島由紀夫の自決の知らせを聞いて、パリで見た反応の第一は日本人画家たちだった。その中の一人の言葉は、私の胸に太釘を打ち込んだようなショックを残した。
「なんという破廉恥なことをしてくれたもんだ!」と吐き出すように言った。
「これからは、もう恥ずかしくって、フランス人と顔を合わせる事もできやしない……『豊饒の海』なんか、ありがたがって読んでいたけど、今夜、セーヌ川に持っていって、どんぶりこと捨ててしまうんだ!」
その後、もっと知的なパリ派の日本人の何人かが、「三島」の名を聞くたびに露骨に示した嫌悪の情は、けっして、この「どんぶり氏」に劣るものでもなかった。
フランス側からの反応で最初に見たのは、「ル・モンド」紙のニュースだった。
「失敗したクーデター」という見方が大半だった。「これを機会に日本の右翼が台頭してくることが恐れられている」との結語は、おそらく日本のマスコミの反応をコピーしたものであろう。
「気でも狂ったか」という佐藤首相の言葉も引用され、以後、三島事件が論じられるたびに繰り返され、事件に対する日本の世俗的見方の代表格として印象づけられていった。
そのうち日本からの詳細が届くにつれ、予想された以上に批判、ときには悪態に近い批難が、いかに世上に満ちみちているかを知った。「平和日本」の「茶の間 の良識」なるものを否応なしに感じさせられた。切腹によって終結したクーデターなるものは、つまるところ「グロテスク」であり「アナクロニズムの極致」で あるというのが、要するにそれら石打つ人々の嘲笑の的であるように思われた。
まして、十分な事情を知らぬ一般のフランス人のあいだで、この出来事が、当初、なによりもまず「ファナティックな暴力」として受けとられたとしても、まっ たく致し方のない反応というべきであったろう。そして程無く、私は全フランス注視の公開テレビ番組で、真っ向からこうした反撃に立ち向う立場に置かれた。
事件後何日目かのことだった。フランス国営テレビから電話が鳴った。毎週のレギュラー番組「文芸討論会」でミシマを取り上げたいから出席してくれというのだった。
放送当夜、私は風邪で高熱を出し、参加は諦めることにしたが、スタジオ入り三〇分前になったとき、ゆえ知らぬ力に引っ張り上げられるかのように、ガバと跳 ね起きた。何のために三島由紀夫はあれほどの苦しみに耐えて死を選んだのか、との考えがよぎるや、ベッドの上に起き上がってしまっていた。そしてスタジオ に駆け込んだ。
「ユキオ・ミシマの死は、単に政治的なものとして捉えられるべきではなく、われわれの文明にとって聖なるものの中心がいかに必要であるかを伝統的死の儀式にのっとって主張したものと見てしかるべきでありましょう……」
すぐ真向かいで炯々と目を光らせていたエティアンブル氏が、待ってましたとばかり噛みついて来た。
「しかし、ミシマは、結局のところ、ヒトラーの礼賛者ではなかったんですか?」
「なるほど、『わが友ヒットラー』という作品を彼は書いていますからね」と応じ、「だが、この題名は逆説なんですよ!」
相手の目をじっと視つめながら、私は切り込んだ。
「それでは、あなた方の作家、ジャン・ジュネのナチズム礼讃のほうは、いったい、どうなんですか?……」
思いがけない反撃にエティアンブル氏は不敵な面魂をびくりとさせた。そしてなにごとか呪文のように早口で口のなかでつぶやくと、こう締めくくろうとした。
「まあ、ミシマは、才能(デュ・タラン)の持主ではあるけどもね……」
どっこい、逃がさじ、と私は意を決していた。
今宵、何百万人ものフランス人がこの光景を見守っているであろう。ましてテーマは、いま話題騒然たる日本の作家ミシマであり、「ハラキリ」であり、大多数 の彼らの目からすれば、さらにそれは「カミカゼ」というも同義語なのである。ただそれが、彼らの危惧する日本のファシズムの再来を意味するか否かの一点に かかっている。このままここで引き下がれば、「何だミシマとは要するにヒットラーの追随者にすぎなかったのか」との印象をもって落着してしまうだろう。
ともあれ、一歩も退かじとの決意を、そのとき私は固めていた。
そこで、こんなこともあろうかと懐に用意してきた“ウルトラC”――ただし一枚の紙片をおもむろに取り出すと、ずらりと一座を見まわして、こう言った。
「なにゆえの、このたびの、日本作家の不可解な挙であったか?
ここに、ミシマの高弟である詩人、ムツオ・タカハシ(高橋睦郎)が、本放送のため、フランスの心に宛てて書いてよこした証言があります……」
私は読んだ。
「詩人はこう言っております――
『ユキオ・ミシマの死の意義は、イエスの十字架上の死がその《受肉の完成》をもたらしたことを考えれば、おのずから明らかでありましょう……』」
一座は粛然とした。
「カトリックの国フランスの人々にはこの思想は分かってもらえるでしょう」と断って、私の畏友とする高橋氏が書き送ってきてくれた一言は、さすが有効なカウンターブローを相手にきめる上に決定的だったようである。
放送翌日に出た「パリ・テレ」紙に、次のような寸評があった。
「かんかんがくがくの、いつもの無意味な文芸討論会のなかで、昨夜、光っていたのは、あの日本人参加者のもたらした証言のみ……」
それまで7年間の滞欧生活を通じて、日本がヨーロッパと接触するその仕方について、時と共にある疑問を深めていた。
私は、接触の中心地パリにあって、ありとあらゆる祖国の文化流入と活動ぶりを見たが、そこでは「新しい日本」を打ちだそうとする外交姿勢と、文化的国際主 義を旗印とする「進歩的文化人」の欧米風エリート意識がつねに大勢を制しているために、われわれ日本人の血脈中にあって否定しようのない、ある本質的特異 性の面については、これを自覚し主張することを恐れ、ときにはこれを積極的に対決の白刃として繰り出すほどの勇気を欠いてきたのではないか――との疑問で ある。
交流の水路を往来する人士の言動を見ると、「われわれはこんなにも現代的です」と滑稽なほどにまで肩をいからせているようにさえみえる。在欧大使館が、「演武」などと聞くとアレルギー症状を起こしがちなのも、その一例である。
こんな事もあった。あるベルギー人が日本フェスティバルで武道を紹介したいから武道家を世話していただきたいと、在ベルギー大使館に頼んだところ、大使館文化部の外交官はこう答えたという「いまの日本に武道なんてありませんよ!」
こういった例は枚挙にいとまがない。
最近でこそややその風潮は改まってきたが、ヨーロッパで合気・空手・少林寺拳法などを教える日本の武芸家は、一般に、日本人側から冷飯を食わされてきたの が通例であって、彼の地の国々の大衆が三顧の礼をとってこれらの師範を奉迎する実態ときわだたしい明暗二相をなしてきたのである。ある意味で――文字通り 身を張って――日本文化の発揚に勤め、かつ最大多数の碧眼の弟子たちの尊敬を集めてきた在外日本人は武道家をもって筆頭格とすると私は信じてきたくらい で、こうした日本側からの不認識にはいつも大いに憤懣をかこってきたのであった。
禅、神道に関しても同様であった。
その後、あの達磨のごとき面魂を持った永平寺の弟子丸泰仙師が渡仏して禅の実体験をフランス人にほどこし、かつこれに大成功を収めるに至って、自分の敵はフランスではなく日本にあったと嘆じたときも、まことにむべなるかなと共感を禁じえなかった。
こうした面の日本が強調されるのは困ると感ずる人がいることは、したがって明らかである。しかもどこよりも、われわれ日本人自身のあいだにいるのである。 そのような反応が、終戦後、西欧的合理精神に学んだ日本の知識人の大半の姿勢を決してきた、と言っても過言ではないだろう。
こうまでしてわれわれが「古い日本」に目をつぶりたがっている謂れは何だろう。フランスの国営テレビが、制作した野心的フィルム「アンドレ・マルローとの 旅日記――日本篇」が1979年にパリで試写されたときの光景が、胸によみがえる。ジャン・マリー・ドロー監督によるこのフィルムは、京都・奈良をとおっ て熊野の那智滝、伊勢神宮にいたるまでのマルロー最後の来日時の足跡を着実にたどることによって、マルローのいうところの「永遠の日本」と西欧精神の対話 を忠実に再現せしめようとしている。

私は、このように深く高雅な意図をもったフランス国民の芸術的創造性なるものを永遠に讃美してやまない者 である。ちなみにこの作品は、フランスで全国放映され、三十数紙の新聞がこれに賛辞を呈するほどの注目の的となった。ところでこの試写を見終わった日本外 務省の文化担当官はなんと言ったか、「新しい日本が全然出て来ませんな。まあ、新幹線が、ちらりとは出てくるけれども、……」
この困惑、この激怒は、かりに口にこそ出さね、敗戦によって条件付けられた戦後日本のタブーの領域を犯すことを、誰もが大なり小なりおそれているという事実に、歴然と由来している。
三島由紀夫の自刃は、人がどのようにそれを受け取ろうと、私には、何よりもまず、このタブーの封印を一挙に切裂いた「侵犯」の行為と見えたのであった。そ してこの侵犯によって、そこの封じ込まれた日本の神聖なる恥部、もしくは恥部の神聖を白昼にさらけ出した行為という意味において、しかもこの行為の切っ先 を、自己の身肉をとおして日本のみならず現代的世界の喉元に扼したという意味において、まことにもって驚天動地の「荒ぶる神」の出来事と見えたのである。
最も密やかな心奥の疑問にこたえてくれた鬼神の行動としてそれは私を震撼せしめたが、同時に、剣尖を突きつけられたヨーロッパのエスプリの側も深くこれに 戦慄し、事件直後の皮相的一部の反撥をこえて、たちまちにして共感、礼讃の声々が広がっていく光景を見て、はたせるかなと感慨に打たれずにはいられなかっ た。
少なくとも、フランスにあっては、エティアンブル氏流の攻撃は、ほうはいとして興る讃嘆の念によって、たちどころに取って代わられていった。ときには同一 人物のなかで、当初その口からほとばしった「野蛮」を非難する声が、真相を知るや、実に驚くべきことに、感動の涙にまで変化していく光景を目にしたのであ る。三島氏の遺言的一作『憂国』に感じた詩人、エマニュエル・ローテンの反応がそうであったように。
『パリ憂国忌』竹本忠雄著から
サイタニのブログからの転載です。高橋史朗先生の講演の記録のようです。和文化が子供の感性を育てる力はいかにも有りそうですね。太鼓の音など、何か聞いていると胸の奥からわきあがってくるような気がしますものね。
そういえば今年の春の彼岸に私の家の菩提寺であるお寺の供養の行事に行った時に(これは檀家としての義務でもあるので、以前は義理で仕方なく行っていたのですが、最近はけっこう説教のお坊さんが上手なのでそういやではありません)、ちょうど東北の震災の直後だったので、その供養も兼ねて、お坊さんたちが特に念入りにお経を読みながら、鐘などを鳴らしておられました。その澄んだ響き渡る鐘の音がほんとうに美しくて、読経の声とともに、何かとても荘厳な響きが不思議な時空間を作っているような気がしました。鐘の音と言うかその空気の振動に自分の心が溶けこむような気がしました。そして、これこそほんとに供養というものだと思ったものです。これは不思議な体験でした。
転載開始
![]() 転載元: サイタニのブログ
転載元: サイタニのブログ