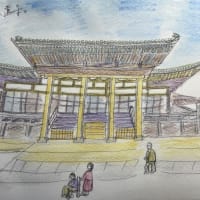何より大切にしていた馬にも召集が来た。
父は悲しみながらも馬草と握り飯を鞍に括り付け、名古屋の練兵場まで3,4日かけて行った。
長い道中、時には馬に乗り、時には馬を引き、他人の情けに触れながら、
馬の無事を祈り切ない別れをしてきたと父に聞いたが、当時の馬は家族と同じ、大切な大切な馬だった。
生糸も取引がなくなり、町でさえ食料がなくなり、配給制が敷かれ、芋の茎でさえ干して出してほしいとの通達が出され、買い物も
切符制になる。
昭和16年の春、次兄より満州の風景や暮らしをスケッチして是非一度見に来て欲しいとの便りが届いた。
しかし、世の情勢はそれを許さなかった。
村の半鐘も蚊屋帳の吊り手までもなくなり、金属という金属はどこの家庭からも無くなくなっていた。
昭和16年、祖父の植えた藤の花が瓦屋根に差し掛けた棚から香りを放ち、蜂達が飛び交う初夏、長兄にも召集令状が来た。
母は青ざめた面持ちで大急ぎで婦人会を頼って歩き回り、千人針を結んでもらい戻ってきた。
兄は髪を五分刈りにして遺髪を残し、結んでもらった千人針を大切に報公袋に詰め出兵して行った。
私が満州を志願したのはそれほど愛国心があったわけでもない。
私が行けば先に満州に渡った次兄がきっと喜ぶだろう、そしてどんなにか気強い事だろう。
いや、そんな綺麗事ではなかったかもしれない。
満州に行って次兄に会いたかった。
次兄が働いて貰ったお金の中から私は小遣いとしてどれほど貰ったか、その金で次兄と同じようにハーモニカを買った。
優しい兄だった。兄のぬくもりが欲しかっただけかもしれない。
急な畑の桑の葉を摘んだ後、見晴らしのいい垣根の外に出て恵那山の夕焼けが次第に消えゆく頃、
次兄が満州に渡った日の事を思い出し、たどたどしくも習い始めたハーモニカを吹いた。
その時既に兄の後を追って義勇軍として満州に渡る事を決めていた。