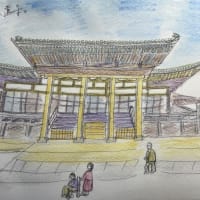昭和19年、大陸の湿原には名も知らぬ黄色い花や桔梗や女郎花が丘に咲き、故郷のお盆を遥かに思い東の空に
手を合わせた。
その頃までは次兄の手紙もいろいろ知らせてきていたが、最後の手紙は本人移動の赤いスタンプが押され返って来た。
それからというもの貨車に乗る兵隊たちの列の中に兄を探し、来る日も来る日もただ茫然と列車を見送っていた。
兄の懐に飛び込みたいと満州に渡るも、あの現実は会うことさえも許してはくれなかった。
17歳の夏だった。
(あとがき)
4人の男子は戦争に行き、昭和20年終戦を迎えた。
満州に渡った次男は戦火に倒れて戻らず。
長男がこの地で後を継ぎ、他の兄弟姉妹はそれぞれの道を歩むために故郷を後にした。
それから75年、山の中のこのの人々は皆この地を離れ、父達が育った家も取り壊され、
この地が人と共に生きた歴史も叢と木々の中で自然に還ってゆく。
この話の主人公である私の叔父もまた、引き上げ給付金を握りしめて渡った北海道の地で、
叔父の心の中に生きていたこの故郷の思い出の全てを言葉と文字でここに残して他界した。
7人いた兄弟姉妹も6人が亡くなり、今この地のこの家族の歴史を知る者は95歳の父が一人となった。

父はたまに天気のいい日にこの古里を訪れ茂った草を鎌で刈りながら先祖や両親、兄弟姉妹と対話する。
ぽつんぽつんと話す言葉の中に、昨年先に逝った弟の歴史が重なる。
同じ歴史の中で見た景色は同じ風景で、
同じ歴史の中で感じた心は同じ感情で、
叔父の遺した言葉に色を付けていく。
誰も住まない「古里」だけれど、もう少し草を刈り続けたいと思う心は、
歴史を残しておきたいという気持ちに他ならない。