黒岩先生は入門三日目にして『合気道の稽古ではウソを教えているんだ』と看破しました。
『え、じゃ、わたしたちはウソを習うために月謝を払っているの?』
はい、その通りです。
合気道の普段の稽古で、片手取りなどは、相手に手を掴んでもらって技をかけていきます。そのとき転換などの体捌きをすると、受けは掴んだ手が離れないように必死になってついてきます。手を離すと先生に注意されます。でも、普通の人は手を離しますよね、振り回されるのイヤだから。
これは、受けを導くというふうに説明されることが多いようですが、《⑪ 空間》の稿で言った通り、合気道の稽古は相手と同調しつつ武道的空間を共に創造する作業なのですから、双方の立場は平等で、一方が牽引するようなものではありません(端的に言えば、受けが拒否したら何もできません)。
転換で受けがついてくる必然性のひとつの解釈として、取りが抜刀しようと柄に右手をかけたところを受けが手首を掴んで阻止する場合があげられます。取りは転換することによって刀を抜こうとし、受けは抜かせまいとさらに回りこんでついて行くという筋書きです(最後は腰を切って抜刀し払い斬りします)。これは、やってみるとなかなかカッコいいのですが、あまりにも状況が限定され過ぎていて、重要な体捌きの存在理由としては弱いと言わざるを得ません。
もうひとつは、受けが取りの手を離したら、取りがその手で打ってくるから離せないという考え方もありますが、これは受けが離そうと思うのと、取りが離れたと感じるのと、どちらが早いかを考えれば成り立たない理屈であることは明白です。手を離して打たれるくらいなら自分から先に打っていけばいいわけですから。
そもそも、片手を取りにいくのは、相手の動きを制した上でもう一方の手で打ち込むためだというのが伝統的解釈です。だから掴まれたほうは転換して攻撃を避けるわけです。しかも、掴まれた手を切り離す技術、いわゆる手解き(てほどき)をするのです。したがって、掴んだほうがついて行くということはありません。
さて、それでは転換で受けがついて行く本当の理由は何でしょう。まず、本来の動きはずっと小さいものです。たがいの前腕が近付く程度、移動距離も数十cmです。二人の腕をつないだ長さが回転半径になるような、あんな大きな動きではありません(あれは演武用です。足腰の鍛錬にはいいでしょう)。そして、これが一番肝心なところですが、相手の手首を掴むのは、本当は受けではなく取りなのです。取りが受けの手首を掴んで転換しながら、相手を前方に押し出し、バランスを崩してやるのです(相撲の出し投げをイメージしてください)。この場合、受けは取りについて行ってるわけではなく、前に押し出されて崩れた体勢を立て直しているのです。まあ、掴まれているんだからしょうがないわけですが。
ここまで説明したところで、合気道を虚実(辞書では《うそとまこと》と書いてあるものもありますね)で表現します。受けに手を掴んでもらい、そこから押さえたり投げたりする稽古は《虚》の稽古で、取りが自分から相手を掴みにいって技をしかけていくのが《実》の稽古です。
黒岩先生は、戦前に陸軍戸山学校で大先生の指導を受けた方に、当時の様子を尋ねたことがありました。そのころの大先生は、自分から前に出て、掴んでは投げ掴んでは投げというやり方をしておられたと聞いて、やっぱり予想していた通りだと納得したそうです。これが実の稽古です。一部の達人志向の方のように、腕に氣が通っていれば手は離れないなどとは指導しておられなかったのです。
一方、普段わたしたちがしているのは、虚の稽古ということになります。虚という表現はネガティブな印象を与えますが、もちろん虚の稽古にも利点があります。そうでなければいくらなんでも淘汰されてしまいますから。受けに手を掴んでもらってする稽古は、余計な力みがなく、正しい動きを身に付けるのに有効です。また、武術本来のありかたとしては、外部の人に本当の姿を見せないで済むという理由があります。他人には虚の技を見せておくのです(弟子にさえ)。少なくとも大先生の時代までは、これは切実なことでした。
そういうわけで、《ウソ》とは虚の稽古のことです。ただしそれは真実にたどり着くための方便としてのウソです。それと表裏一体に実の稽古というものがあるのです(実際にやらなくてもいいですから、せめて知っているだけでも意味があります)。
そういえば、《虚》の稽古を口先だけで正当化しようとすると《嘘》になるのですねぇ(わたしのことか?)。












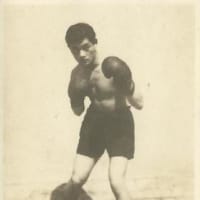
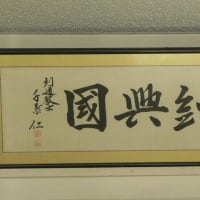
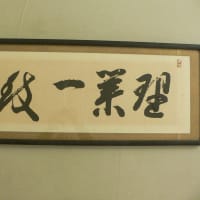





というよりも、お久しぶりです、というのが正しいのかも知れませんが…何度か浅草橋の練習にて、付かせていただいた者です。
毎回楽しみに拝読させていただいております。いつも黒岩先生がコーヒーを飲みながら、話されていることばかりで、懐かしいばかりです。
今でも、練習に行けるときには、練習にお邪魔させていただいているので、もし、お会いすることがあれば、改めて挨拶させていただきます。(次は6月の講習会かもしれませんが…)
これからもよろしくお願いいたします。
こんにちわ。
「大先生」「力持ち」「黒岩学校」「うそ」ブログ拝読いたしました。
コメントを投稿いたします。
ブログの量が多く、まだ追いつけませんが、腰をすえて貴兄の考えを理解すべく読ませていただいております。
エピソードが書かれていましたので、私が聞いていた話とあわせながら、それぞれのブログについて感想を書かせていただきます。
前回の投稿では、「黒岩先生の生計は」などとお聞きしてしまいましたが、斉藤先生から開祖が亡くなられた後、勤めを止め岩間の合気道修練道場を引き継がれた頃、ご苦労があったとお聞きし、合気道で身を立てる大変さを伺って言いましたので、つい、関心が行きました。
「大先生」の呼称について書かれていましたが、小生、入部した頃も、すでに大先生と呼んでいました。
黒岩先生が「植芝先生」と呼ばれるお気持ち、分かるような気がします。
戦後直ぐの入門と思われますが、組織もまだ大きくなく、我々より開祖を身近な存在と感じられる面があったのではないかと思います。
タクシーでの話も面白く読ませ頂きました。
勘が鋭い方と伝記、伝聞などで知っていました。
養生館の望月稔先生が書かれたご本にそんな記述がありました。望月先生の家に泊まられた時のお話で、翌朝、大先生曰く「オイ!この家、川の上に建っとると違うか、枕の下、水が流れとるでぇ」。後日道場の下、地下1メートルのところに下水道があったのです。
他にエピソードとして勘のよさを示すこと書かれていました。
「用心深くなる」のは職業病ではないかと思うほど、当時の武道家はそれでないと通用しなかったのでしょうね。
大先生のパフォーマンスで数人のお弟子さんが額を押えても動かなかった話、
黒岩先生曰く「自分の先生に、わしゃ押されても倒れないぞ、って言われたらねぇ、押せるもんじゃありませんよ弟子は」
貴兄 「・・・・」
このくだり、思わず笑いがこぼれました。
「力持ち」のお話、戦前戦後に入門された方には、すでにひとかどの武道家で居られた方がいました。身体能力においても一流の方です。
すでに力量は持ち合わせえていたのでしょう。
大先生にいたっては、開拓時代、毎日4キロほどのマサカリで巨木を倒しています。相当なものなのでしょう。
私、20数年ほど前に、金属加工用の材料だった鉄の丸棒を貰い受け、振り棒にしていた事がありましたが、5キロあります。
今でも手元においてありますが、たやすく振れるものではありません。
大先生の凄さが分かりました。
「黒岩学校」では、食料事情がよくなく、お金もない様子が見て取れました。
稽古し腹をすかせてたある方が独り占めした話、気持ち分かります。
若い頃、直ぐ腹が空きますから。
黒岩先生の見取り稽古の能力についての記述がありましたが、なるほどと思わされました。
ボクシング、剣道をなさっていた由。
そんな経験と、洞察力が備わっていたので、合気道の稽古方法が本質的に、「自由攻防」を行う他の武道と違うと見抜いたからこそ「ウソ」を教えていると言ったのでないでしょうか。
「ウソ」ここに書かれているお話は驚きました。
私など、学生時代、考えもしなかったです。
取り、受けと分担して交互に技の掛け合いから覚えるとものとの認識だけ、武道的空間を共に創造する作業とは考えられませんでした。
ここに至って、<虚と実>の稽古を理解できたような気がします。
引き続きブログを読ませていただき、感想を投稿させて頂きます。
T.U
名だたる先生方が若手の門弟であった当時のお話を伺うにつけ、桁外れともいうべき大先生のもとで、皆さん普通の物差しでは計れない考えや行動をなさっていたことに驚かされます。
本部道場やその後の各先生の道場が荒稽古で名を馳せたのもむべなるかなと思います。合気道が最強の武道だと言えた時代ではないでしょうか。
ちなみに、ご飯を全部食べてしまったA先生とは、実はT.U様がよくご存知の方です(Aとは某という意味ではなくイニシャルです)。先年ご逝去の際、黒岩先生は『細かいことにこだわらない豪快な人で、若手の弟子たちの番長みたいな人だった』と述懐しておられたのを覚えています。
紳士的な合気道や合気道家ももちろん結構ですが、枠に納まりきらない人物にも大いに惹きつけられます。皆さん、一冊の小説になりそうなご生涯ですね。