10月25日(火)の昼に国立中劇場で、「レオポルドシュタット」を見る。1時開演で、休憩なしの2時間20分。高校の団体が入っていたが、サイドには空席があり、7~8割の入り。
イギリスの劇作家トム・ストッパードの最新作の劇で、もしかするとこれが最後の作品かもしれないとも言われている。題名のレオポルドシュタットとはウィーンのユダヤ人ゲットー地区の名称だが、物語はそこから抜け出るために、キリスト教に改宗して金持ちの工場経営者になった男とその一族の話。
1899年から始まり、1924年、1938年、1955年と移っていく。この時代設定が大きな意味を持っているので、この年代からピンと来るように事前にウィーンの歴史を読んでおかないと、事前知識なしの日本人にはちょっとわかりにくいかもしれない。
1899年は、ハプスブルグ王朝最後の黄金時代で、支配地域からウィーンを目指して多くの才能ある人々が集まってきた時代だ。フロイトの「夢判断」、クリムトの絵画、数学者リーマンの予想、シュニッツラーの小説、マーラーの話などが話題に登場する。主人公のヘルマンはユダヤ人だが改宗してキリスト教徒となり、キリスト教徒の妻と結婚するが、その妻が非ユダヤの軍人将校と浮気するので、ユダヤ人であることを思い知らされる。一家の子供たちは過ぎ越しの祭りの種無しパンに夢中になったりしている。ユダヤの風俗習慣が丹念に描かれている。
1924年になると第一次世界大戦の結果、王朝はなくなり、若い娘はチャールストンを踊り、共和国では社会党が政権を取り、労働運動も盛んになっている。一家の話題は、新しく誕生した男の子に割礼をすることだ。ここでもユダヤの慣習が続いている。
1938年になると、ナチスドイツはオーストリアを併合して、ユダヤ人を迫害する「水晶の夜」の事件が起き、一家も住居を強制退去させられて、チリジリとなってしまう。
最後の1955年の場面では、第二次世界大戦後、やっと独立したオーストリアの時代だ。一族では大半の人が亡くなり、残った3人が再会するが、8歳でイギリスに渡って育った青年は、ウィーン出身のユダヤ人であることをすっかりと忘れて、現在の自分の生活を築いている。しかし、3人が衝突して、昔の家系図を確認する中で、そのルーツを思い起こす。
1899年部分が1時間で、その後の時代は20~30分ずつという構成。さすがにトム・ストッパードだと思わせる魅力的な芝居で、何となく感動した。
美術や演出も的確だが、主演のヘルマンを演じた浜中文一の演技が際立ってお粗末。どうしてこういうキャスティングをするのか疑問だ。もっとうまい役者はいくらでもいるだろう。あと、場面転換時に流れる音楽の音量が妙に大きすぎて耳が痛くなる。普通の音量にしてほしい。
まあ、久しぶりに面白い芝居を見て、家に帰って食事。かぼちゃのスープ、ほうれん草のクリーム・ソテー、サルティンボッカなど。飲み物はイタリア南部の赤。
イギリスの劇作家トム・ストッパードの最新作の劇で、もしかするとこれが最後の作品かもしれないとも言われている。題名のレオポルドシュタットとはウィーンのユダヤ人ゲットー地区の名称だが、物語はそこから抜け出るために、キリスト教に改宗して金持ちの工場経営者になった男とその一族の話。
1899年から始まり、1924年、1938年、1955年と移っていく。この時代設定が大きな意味を持っているので、この年代からピンと来るように事前にウィーンの歴史を読んでおかないと、事前知識なしの日本人にはちょっとわかりにくいかもしれない。
1899年は、ハプスブルグ王朝最後の黄金時代で、支配地域からウィーンを目指して多くの才能ある人々が集まってきた時代だ。フロイトの「夢判断」、クリムトの絵画、数学者リーマンの予想、シュニッツラーの小説、マーラーの話などが話題に登場する。主人公のヘルマンはユダヤ人だが改宗してキリスト教徒となり、キリスト教徒の妻と結婚するが、その妻が非ユダヤの軍人将校と浮気するので、ユダヤ人であることを思い知らされる。一家の子供たちは過ぎ越しの祭りの種無しパンに夢中になったりしている。ユダヤの風俗習慣が丹念に描かれている。
1924年になると第一次世界大戦の結果、王朝はなくなり、若い娘はチャールストンを踊り、共和国では社会党が政権を取り、労働運動も盛んになっている。一家の話題は、新しく誕生した男の子に割礼をすることだ。ここでもユダヤの慣習が続いている。
1938年になると、ナチスドイツはオーストリアを併合して、ユダヤ人を迫害する「水晶の夜」の事件が起き、一家も住居を強制退去させられて、チリジリとなってしまう。
最後の1955年の場面では、第二次世界大戦後、やっと独立したオーストリアの時代だ。一族では大半の人が亡くなり、残った3人が再会するが、8歳でイギリスに渡って育った青年は、ウィーン出身のユダヤ人であることをすっかりと忘れて、現在の自分の生活を築いている。しかし、3人が衝突して、昔の家系図を確認する中で、そのルーツを思い起こす。
1899年部分が1時間で、その後の時代は20~30分ずつという構成。さすがにトム・ストッパードだと思わせる魅力的な芝居で、何となく感動した。
美術や演出も的確だが、主演のヘルマンを演じた浜中文一の演技が際立ってお粗末。どうしてこういうキャスティングをするのか疑問だ。もっとうまい役者はいくらでもいるだろう。あと、場面転換時に流れる音楽の音量が妙に大きすぎて耳が痛くなる。普通の音量にしてほしい。
まあ、久しぶりに面白い芝居を見て、家に帰って食事。かぼちゃのスープ、ほうれん草のクリーム・ソテー、サルティンボッカなど。飲み物はイタリア南部の赤。










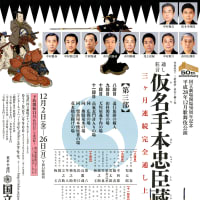
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます