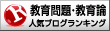ちょいと大げさな題を付けておいたが。
吉田秀和さんがどこかで書いていた。
ある演奏家を褒める。その人がいつの間にか精彩を欠くようになることもある。それを批評家の耳の悪さにするのはお門違いだ。残念ながらそういう演奏家がいることは本当だが、自分はこう考える。
人間には、芸術家にはいろんなタイプがあり、ある人は年老いてもなお輝きを保ち、他の人は一時期まばゆく輝くが後に色褪せる。そういう人々がいるのだ。我々はその人が一時期大きな輝きを放ったことを喜ばしく思った方がよいではないか。
大体このような趣旨の文章である。
これはまさしくその通りだ。
ウェーバーなどがその代表だろう。彼は「魔弾の射手」を書くために生まれてきた人だ。このすばらしい作品以外の彼の作品は青白い影でしかない。
このオペラの中で、ウェーバーはメンデルスゾーンのような精妙さ、ワーグナーのような声と器楽の一体化(たとえばアガーテのアリアを、マックスのアリアを見よ)を具現化している。この作品なしにワーグナーは「さまよえるオランダ人」を創り得ただろうか?と思わず問いかけたいほどだ。
「ドイツの森の神秘」とはさるドイツ人音楽評論家がブルックナーの作品について述べた言葉である。じつに言いえて妙である。これをそっくり「魔弾の射手」に当てはめても良いだろう。ここではその上、森人の息吹までもがある。
その輝きに比べると、彼の他の作品が何と貧弱なことだろう。たとえ「オベロン序曲」や「オイリアンテ序曲」が一定の出来栄えを保っているにせよ。
一瞬の輝き、まばゆい輝きを放った後、二度と再びその輝きが戻ってこなかった芸術家として詩人のランボーや小説家のラディゲを考えてもよい。もっともランボーは自ら詩を捨てて砂漠へ去っていったのであるが。
また、音楽家の中でも演奏家と呼ばれる人たちに目を向けても、やはりそういった特殊な例が無いわけではないだろう。
僕はそれが誰と、具体的に名前を挙げない。いつの間にか聞かれなくなった名前でよいならばたちどころに数十人は挙げられる。いや、控えめにいってももっと多いだろう。
それでも吉田さんの言葉には素直にうなずけない。むしろ体のよい自己弁護と言ったら言い過ぎだろうか。どうもこういった立派な人の立派な意見はたちが悪い。反論しようにもぬえのようにすり抜けていく。
しかし吉田さんも耳の悪い批評家はいる、と書く。どこかでは「批評の混乱ここに極まれり」とまで書いていた。そこで遠慮なく言えば、僕には吉田さんの耳は悪いと思われる。
いやそれは正確な言い方ではないようだ。彼は耳を疑う頭の方が強い人物なのである。聴いたものを聴いたものとして扱わず、理解しようとしてしまう。
耳は考えるきっかけに過ぎず、そこからあれこれ考えを巡らせる。もちろん文学者は対象をきっかけに考えを巡らせる。
しかし演奏評の場合、まずはそれが音として成り立つかがまず大切だ。簡単に言えば、ドラ聲で歌われたシューベルトを批評するならば、その声の悪さを一刀両断するしかない。
考えを巡らせるとしたら、この場合、その悪声にもかかわらず人前で歌う心理以外あるまい。そしてそんな考察は演奏評ではなく、社会時評に近くなるだろう。
どのように受け取られるか分からないが、耳は非常に原始的なものだ。長年音と暮らした僕の唯一の実感である。インテリには絶対分からぬ世界だ。
吉田秀和さんがどこかで書いていた。
ある演奏家を褒める。その人がいつの間にか精彩を欠くようになることもある。それを批評家の耳の悪さにするのはお門違いだ。残念ながらそういう演奏家がいることは本当だが、自分はこう考える。
人間には、芸術家にはいろんなタイプがあり、ある人は年老いてもなお輝きを保ち、他の人は一時期まばゆく輝くが後に色褪せる。そういう人々がいるのだ。我々はその人が一時期大きな輝きを放ったことを喜ばしく思った方がよいではないか。
大体このような趣旨の文章である。
これはまさしくその通りだ。
ウェーバーなどがその代表だろう。彼は「魔弾の射手」を書くために生まれてきた人だ。このすばらしい作品以外の彼の作品は青白い影でしかない。
このオペラの中で、ウェーバーはメンデルスゾーンのような精妙さ、ワーグナーのような声と器楽の一体化(たとえばアガーテのアリアを、マックスのアリアを見よ)を具現化している。この作品なしにワーグナーは「さまよえるオランダ人」を創り得ただろうか?と思わず問いかけたいほどだ。
「ドイツの森の神秘」とはさるドイツ人音楽評論家がブルックナーの作品について述べた言葉である。じつに言いえて妙である。これをそっくり「魔弾の射手」に当てはめても良いだろう。ここではその上、森人の息吹までもがある。
その輝きに比べると、彼の他の作品が何と貧弱なことだろう。たとえ「オベロン序曲」や「オイリアンテ序曲」が一定の出来栄えを保っているにせよ。
一瞬の輝き、まばゆい輝きを放った後、二度と再びその輝きが戻ってこなかった芸術家として詩人のランボーや小説家のラディゲを考えてもよい。もっともランボーは自ら詩を捨てて砂漠へ去っていったのであるが。
また、音楽家の中でも演奏家と呼ばれる人たちに目を向けても、やはりそういった特殊な例が無いわけではないだろう。
僕はそれが誰と、具体的に名前を挙げない。いつの間にか聞かれなくなった名前でよいならばたちどころに数十人は挙げられる。いや、控えめにいってももっと多いだろう。
それでも吉田さんの言葉には素直にうなずけない。むしろ体のよい自己弁護と言ったら言い過ぎだろうか。どうもこういった立派な人の立派な意見はたちが悪い。反論しようにもぬえのようにすり抜けていく。
しかし吉田さんも耳の悪い批評家はいる、と書く。どこかでは「批評の混乱ここに極まれり」とまで書いていた。そこで遠慮なく言えば、僕には吉田さんの耳は悪いと思われる。
いやそれは正確な言い方ではないようだ。彼は耳を疑う頭の方が強い人物なのである。聴いたものを聴いたものとして扱わず、理解しようとしてしまう。
耳は考えるきっかけに過ぎず、そこからあれこれ考えを巡らせる。もちろん文学者は対象をきっかけに考えを巡らせる。
しかし演奏評の場合、まずはそれが音として成り立つかがまず大切だ。簡単に言えば、ドラ聲で歌われたシューベルトを批評するならば、その声の悪さを一刀両断するしかない。
考えを巡らせるとしたら、この場合、その悪声にもかかわらず人前で歌う心理以外あるまい。そしてそんな考察は演奏評ではなく、社会時評に近くなるだろう。
どのように受け取られるか分からないが、耳は非常に原始的なものだ。長年音と暮らした僕の唯一の実感である。インテリには絶対分からぬ世界だ。