2015年3月24日に起きたルフトハンザ系格安航空会社「ジャーマンウィングス」(本社:ケルン)の9525便(A320型機)墜落事故は、機体整備不良や天候不順、あるいはテロ攻撃によるものではなく、副操縦士が墜落させたとの見方に収斂しつつある。
この旅客機は、スペイン・バルセロナ空港を出発して、独デュッセルドルフ空港へ向かう途中、ニース近郊のアルプス山中に激突した。乗客・乗員合計150名は全員即死であった。中には、デュッセルドルフ在住の邦人2名が含まれる。独、スペイン国籍の乗客が多く、乳児を抱えた英国のオペラ歌手もいたという。謹んで、亡くなられた方々へ心から哀悼の意を捧げます。
この悲惨な航空事故は、心身共に健全と判断された副操縦士(27)が故意に犯した墜落事案として、航空業界に激震を与えている。9.11同時多発テロ(2001)以来、旅客機の操縦室出入りは、安全管理のため扉の材質強化、鍵のディジタル化などが行われた。今回は、主操縦士が一時操縦席を離れて室外に出た時、再入室不可能となった。操縦室に残った副操縦士が施錠したまま、勝手な操縦をして墜落させたのである。
訓練中断時「落ち込んでいた」=副操縦士関係先捜索、本格化―独機墜落
2015年3月27日(金)10:11 (時事通信)
【パリ、ベルリン時事】フランス南東部で起きたドイツ旅客機墜落をめぐり、仏独の捜査当局は26日、飛行機を意図的に墜落させたとみられるアンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)の行動の解明に向け本格捜査を開始した。副操縦士が過去に訓練を一時中断していたことに関して「燃え尽き症候群というか、落ち込んでいたようだ」と元同級生の母親の話も伝えられている。
燃え尽き症候群は、強い意欲を持ち集中的な努力で前向きな生き方を実現していた人物が突如、極度の疲労や達成感の低さを感じる現象で、うつ病の一種と捉える見方もある。副操縦士は生前「(仕事に)夢中だった」という証言もある。
独当局は26日、西部モンタバウアーの副操縦士自宅など複数の関係先を捜索した。副操縦士の知人らは独メディアに「テロや自殺の兆候はみられなかった」と証言しているが、当局は親族らの聴取などを通じ副操縦士の言動に不自然な点がなかったかを調べる。
メルケル独首相は26日の記者会見で、副操縦士の意図的な犯行だったとみられることについて「信じられず、理解の限度を超えている」と非難。その上で「さまざまな観点から徹底的に捜査する」と真相解明に全力を挙げる意向を強調した。
墜落をめぐっては操縦室の厳重な入室管理の問題点も浮かび上がった。一般的な旅客機の操縦室ではハイジャック犯などの侵入を防ぐため、中の操縦士の承認がなければ扉が開かないシステムを採用。墜落機では操縦室を出た機長が副操縦士に入室を拒まれ、機体の降下を阻止できなかった。このため、航空各社は26日、相次いで防止策を発表し、安全性をアピールした。
AFP通信によると、カナダやノルウェーなどの航空会社が発表した対策はいずれも、2人の操縦士のうち1人が操縦室を退出する場合は他の乗員が代わりに入室するルールを設ける内容。ドイツ航空協会(BDL)も、操縦室内の常時2人体制義務化を要求している。操縦士を常にもう1人の監視下に置くことで異常な行動を起こしにくくするのが狙いだ。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/world/jiji-150327X881.html
確かに、操縦室に3人いると今回のような問題は発生確率が低くなる。以前は、50人定員以上の旅客機の場合、操縦室に主操縦士、副操縦士に加えて、機関士 or 無線通信士がいたのだが、機材のコンピューター制御化が急速に進んで現在のような運行体制が常態化した。正または副操縦士が、コックピットを離れる時は、客室乗務員をあらかじめ呼んで、操縦室2人体制を維持するのは結構なことだ。
旅客機パイロットは、一般のサラリーマンよりも待遇は良いし、社会的にも評価が高い職業であると思う。それでも、人間の悩みは尽きることが無いから、せめてパイロットは勤務中(飛行中)は懊悩を忘れ、操縦に専念出来るような人材であって欲しい。それは、航空会社と乗客の信頼関係を担保する重要な条件でもある。
機材のコンピューター制御技術は、今後益々進み、安全性とフライトコスト低下に寄与すると想像するが、一方ではこんなこともあるようだ。
ブログ<ウィーン発コンフィデンシャル>で、ブログ主が独シュピーゲル誌の記事を読み、昨年11月に起きた事故寸前の事態が今回の事故に似ているとして、以下のような紹介をしている。
コンピューターが操縦桿を握る時
http://blog.livedoor.jp/wien2006/archives/52099428.html
(部分引用始め)
同記事の概要を紹介する。昨年11月5日、ルフトハンザ機が今回と同じようにスペインの Bilbao 発でドイツのミュンヘンに向かっていた。離陸して約15分後、飛行機は上空9500メートルから突然降下を始めた。毎分1000メートルの速さでどんどん下がっていく。パイロットは慌てて飛行機を再度上昇させるためにフライト・ジョイスティック(操縦桿)を後ろに引いたが、機体は反応しない。飛行機はパイロットの意向を無視して降下を続けている。シュピーゲル記者は、「飛行機はコクピットのパイロットの手を離れ、さらに強い力、人間の命令に従わないコンピューターによって操縦されている」とドラマチックに記述している。
幸い、パイロットは最後の手段としてコンピューターのスイッチを切り、手動操縦に切り替え、飛行機を上昇させることに成功したというのだ。危機一髪だったという。飛行機は何もなかったように無事にミュンヘンに到着した。
シュピーゲル誌によると、飛行中の迎角を測量するため飛行機外板に設置されたセンサー(3本)のうち2本が凍り、正常だったセンサーが出すデーターをコンピューターが無視した結果、飛行機は急降下したのではないかと受け取られている。チェコのプラハで4月、航空会社の専門家会議が開催され、そこで11月のエアバスの件について協議されることになっている。
(引用終わり)
コンピューターと共に生きる現代人には、改めて考えさせられる話題である。
この旅客機は、スペイン・バルセロナ空港を出発して、独デュッセルドルフ空港へ向かう途中、ニース近郊のアルプス山中に激突した。乗客・乗員合計150名は全員即死であった。中には、デュッセルドルフ在住の邦人2名が含まれる。独、スペイン国籍の乗客が多く、乳児を抱えた英国のオペラ歌手もいたという。謹んで、亡くなられた方々へ心から哀悼の意を捧げます。
この悲惨な航空事故は、心身共に健全と判断された副操縦士(27)が故意に犯した墜落事案として、航空業界に激震を与えている。9.11同時多発テロ(2001)以来、旅客機の操縦室出入りは、安全管理のため扉の材質強化、鍵のディジタル化などが行われた。今回は、主操縦士が一時操縦席を離れて室外に出た時、再入室不可能となった。操縦室に残った副操縦士が施錠したまま、勝手な操縦をして墜落させたのである。
訓練中断時「落ち込んでいた」=副操縦士関係先捜索、本格化―独機墜落
2015年3月27日(金)10:11 (時事通信)
【パリ、ベルリン時事】フランス南東部で起きたドイツ旅客機墜落をめぐり、仏独の捜査当局は26日、飛行機を意図的に墜落させたとみられるアンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)の行動の解明に向け本格捜査を開始した。副操縦士が過去に訓練を一時中断していたことに関して「燃え尽き症候群というか、落ち込んでいたようだ」と元同級生の母親の話も伝えられている。
燃え尽き症候群は、強い意欲を持ち集中的な努力で前向きな生き方を実現していた人物が突如、極度の疲労や達成感の低さを感じる現象で、うつ病の一種と捉える見方もある。副操縦士は生前「(仕事に)夢中だった」という証言もある。
独当局は26日、西部モンタバウアーの副操縦士自宅など複数の関係先を捜索した。副操縦士の知人らは独メディアに「テロや自殺の兆候はみられなかった」と証言しているが、当局は親族らの聴取などを通じ副操縦士の言動に不自然な点がなかったかを調べる。
メルケル独首相は26日の記者会見で、副操縦士の意図的な犯行だったとみられることについて「信じられず、理解の限度を超えている」と非難。その上で「さまざまな観点から徹底的に捜査する」と真相解明に全力を挙げる意向を強調した。
墜落をめぐっては操縦室の厳重な入室管理の問題点も浮かび上がった。一般的な旅客機の操縦室ではハイジャック犯などの侵入を防ぐため、中の操縦士の承認がなければ扉が開かないシステムを採用。墜落機では操縦室を出た機長が副操縦士に入室を拒まれ、機体の降下を阻止できなかった。このため、航空各社は26日、相次いで防止策を発表し、安全性をアピールした。
AFP通信によると、カナダやノルウェーなどの航空会社が発表した対策はいずれも、2人の操縦士のうち1人が操縦室を退出する場合は他の乗員が代わりに入室するルールを設ける内容。ドイツ航空協会(BDL)も、操縦室内の常時2人体制義務化を要求している。操縦士を常にもう1人の監視下に置くことで異常な行動を起こしにくくするのが狙いだ。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/world/jiji-150327X881.html
確かに、操縦室に3人いると今回のような問題は発生確率が低くなる。以前は、50人定員以上の旅客機の場合、操縦室に主操縦士、副操縦士に加えて、機関士 or 無線通信士がいたのだが、機材のコンピューター制御化が急速に進んで現在のような運行体制が常態化した。正または副操縦士が、コックピットを離れる時は、客室乗務員をあらかじめ呼んで、操縦室2人体制を維持するのは結構なことだ。
旅客機パイロットは、一般のサラリーマンよりも待遇は良いし、社会的にも評価が高い職業であると思う。それでも、人間の悩みは尽きることが無いから、せめてパイロットは勤務中(飛行中)は懊悩を忘れ、操縦に専念出来るような人材であって欲しい。それは、航空会社と乗客の信頼関係を担保する重要な条件でもある。
機材のコンピューター制御技術は、今後益々進み、安全性とフライトコスト低下に寄与すると想像するが、一方ではこんなこともあるようだ。
ブログ<ウィーン発コンフィデンシャル>で、ブログ主が独シュピーゲル誌の記事を読み、昨年11月に起きた事故寸前の事態が今回の事故に似ているとして、以下のような紹介をしている。
コンピューターが操縦桿を握る時
http://blog.livedoor.jp/wien2006/archives/52099428.html
(部分引用始め)
同記事の概要を紹介する。昨年11月5日、ルフトハンザ機が今回と同じようにスペインの Bilbao 発でドイツのミュンヘンに向かっていた。離陸して約15分後、飛行機は上空9500メートルから突然降下を始めた。毎分1000メートルの速さでどんどん下がっていく。パイロットは慌てて飛行機を再度上昇させるためにフライト・ジョイスティック(操縦桿)を後ろに引いたが、機体は反応しない。飛行機はパイロットの意向を無視して降下を続けている。シュピーゲル記者は、「飛行機はコクピットのパイロットの手を離れ、さらに強い力、人間の命令に従わないコンピューターによって操縦されている」とドラマチックに記述している。
幸い、パイロットは最後の手段としてコンピューターのスイッチを切り、手動操縦に切り替え、飛行機を上昇させることに成功したというのだ。危機一髪だったという。飛行機は何もなかったように無事にミュンヘンに到着した。
シュピーゲル誌によると、飛行中の迎角を測量するため飛行機外板に設置されたセンサー(3本)のうち2本が凍り、正常だったセンサーが出すデーターをコンピューターが無視した結果、飛行機は急降下したのではないかと受け取られている。チェコのプラハで4月、航空会社の専門家会議が開催され、そこで11月のエアバスの件について協議されることになっている。
(引用終わり)
コンピューターと共に生きる現代人には、改めて考えさせられる話題である。











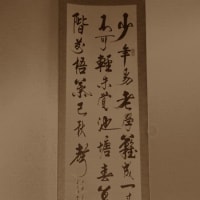













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます