ちょっと、1週間ほど“ほっとらかして”おりました。が、また、お尻のほうがむずかゆく、ほっておくのもと、再びわたしのブログを再開します。
まあ、今更ら言っても仕方がないのですが、本論はどこにあるのが迷路のような不思議な、本当に出鱈目なブロになってしまいました。これも、また、おもしろいのではないかと勝手に解釈して、「私の町 吉備津」を続けます。
さて、又、今日ですが、朝日新聞に、中西進先生の「万葉こども塾」が出ています。(毎週日曜日に掲載されるのですから当り前の話ですが)
三輪山を しかも隠すか 雲だにも 情(こころ)あらなむ 隠さうべしや
667年の天智天皇が都を、飛鳥から近江の国に移されます。その時に額田王が詠んだ歌です。中大兄が吉備の穴海で「わたつみの 豊旗雲に・・・・」と詠われた次の日に詠われた「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮も適ひぬ 今は漕ぎ出な」の作者なのです。
この背景は、斎明天皇が、百済再興の為に朝鮮半島に挙兵しようと一大船団を組んで瀬戸内海を下って、九州の娜津に入らますれたます。しかし、天皇は、そこで崩御され(661年)、皇太子の中大兄が天皇になられ(天智天皇)ます。その後、この天智帝は、母斎明天皇の御遺志をついで朝鮮に出兵され、新羅と唐の連合軍に、白村江の戦いで、完完膚無きまでに敗れます(663年)。
日本に逃げ帰った天智天皇は、その新羅・唐の連合軍が、今度は逆に日本を襲ってくるのではと思われ、その防塞のための城を瀬戸内各所に作らせます。当然、吉備の国にも設置させたものと思われるのですが、その記録がありません。大和朝廷が出費して作らせた出城は、日本書紀にその記録があるのですが、吉備の国にある、その時設置させたと思われる城については記録が有りません。吉備は、当時、まだ、それだけの国力を備えていたため、朝廷からの特別な援助無しで、独自で、その防御用の施設を作ったのだろうと云われています。
それがあの「鬼城」なのです。
その新羅・唐軍の襲撃を考えられ、万が一の備えの為ではないかと思われる遷都を天智帝は実行なさいます。飛鳥から都を滋賀に移されるのでした。その遷都の時に詠われたのが、今日出ている額田王の「三輪山を・・・」という歌なのです。だから、この歌も、また、吉備の国と幾分かは関係のある歌だと思えます。
そんなんことを思い浮かべながら、当時の日本の人々の思いは、いや、吉備の国の人の思いはいかばかりならんと、今朝の新聞を読みました。恐ろしい外国の兵隊が近いうちに押し寄せてくる、みんな警戒しなくてはならない、うかうかすると日本人は皆殺しになるのではないかという噂も、当然、人々の間には広まっていたと思われます。その未知なる恐ろしい外国人の襲来、それが温羅の鬼と結びついて後世になって、この物語は作られたのだと思われます。なお、この温羅の活躍する時代は紀元前220年ごろですから、二つの間には1000年程度の時間の差があります。
なお、これも私の勝手なる思いですが、あの中大兄の「わだつみの 豊旗雲に 入り日射し 今夜の月夜 さやかけりこそ」と詠まれた時に見られた吉備の新山辺りの地形に留意なさった天皇があの場所に出城を設置するよう要望を出されたのではないかとも思っています。
そんなんことを考えても吉備って面白い処だと思われませんか?????















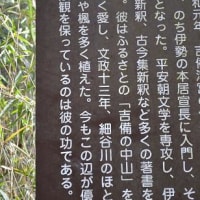



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます