
何をしているかわかりますか。
白いものはお餅。鍋で煮たお餅を冷水でしめているのです。
作っているのは前任校の女子生徒。料理の名前は「なべっこ団子」。
直径3〜4cmの丸いお餅の真ん中を、指で押しておへそのように
へこませるので「へっちょこ団子」とも呼ばれている郷土料理です。
お汁粉とほぼ同じですが、冷水でしめた歯ごたえのあるお餅が特徴です。
この写真は学校設定科目として立ち上げた「食農科学」の一コマです。
田舎といえども、どんどん郷土料理が消えています。
祖父母と暮らさなくなったため、祖母から母へ、母から子へという
伝承の仕組みが途絶えているのが原因といわれています。
この地域はヤマセが吹くため、かつてはお米が採れない地域でした。
したがって様々な雑穀料理が伝統料理として誕生しています。
なんとか伝承したい。そこで男である農業教員たちと連携して作った科目です。
指導されるのは地域のおばあさんたち。孫に教えるようで楽しいと
喜んで来校してくださいました。伝授される料理は年間6品目ぐらい。
おばあさんのお話や使われる食材の栽培や料理の仕方を通して
先人の自給自足の暮らしが見えてきて、とても有意義でした。
さてアワとヒエが主食の先人。どうしてお米を使うなべっこ団子を作るのでしょう。
理由はお供え。貴重なお米を使う料理は、すべて神様への供物なのです。
私たちの年越し(こちらでは年取り)は12月31日。しかしお世話になった
神様に年越し料理をお供えする前に人が食べるわけにはいきません。
先人の時代は神様が家にたくさんいたので、日をかえて順番にお祝いしていきました。
その期間はなんと1ケ月。毎日のようにそれぞれの神様の料理を作ったのです。
このなべっこ団子は大師講様(弘法大師)の年取り料理。
数ある料理の中、最初に作られるものです。その日が旧暦の11月23日。
数ある郷土料理の中でもなべっこ団子の美味しさはNo.1。
当時も子供もみんな楽しみにしていたようです。
この「食農科学」は地域を巻き込んだユニークな科目として全国誌でも紹介されるなど
人気科目でしたが、学科再編でこの学科はすでに募集停止。
教科書は今も手元に残っていますが、幻の科目となってしまいました。
先人の知恵を伝承するすべも失しなわれ、今後が心配です。
冬が近づいています。ぜひお子さんと作ってみてはいかがですか。
なおそんな食農科学の取り組みのブログは今も閉じずに残っています。
機会があったらぜひご覧ください。
白いものはお餅。鍋で煮たお餅を冷水でしめているのです。
作っているのは前任校の女子生徒。料理の名前は「なべっこ団子」。
直径3〜4cmの丸いお餅の真ん中を、指で押しておへそのように
へこませるので「へっちょこ団子」とも呼ばれている郷土料理です。
お汁粉とほぼ同じですが、冷水でしめた歯ごたえのあるお餅が特徴です。
この写真は学校設定科目として立ち上げた「食農科学」の一コマです。
田舎といえども、どんどん郷土料理が消えています。
祖父母と暮らさなくなったため、祖母から母へ、母から子へという
伝承の仕組みが途絶えているのが原因といわれています。
この地域はヤマセが吹くため、かつてはお米が採れない地域でした。
したがって様々な雑穀料理が伝統料理として誕生しています。
なんとか伝承したい。そこで男である農業教員たちと連携して作った科目です。
指導されるのは地域のおばあさんたち。孫に教えるようで楽しいと
喜んで来校してくださいました。伝授される料理は年間6品目ぐらい。
おばあさんのお話や使われる食材の栽培や料理の仕方を通して
先人の自給自足の暮らしが見えてきて、とても有意義でした。
さてアワとヒエが主食の先人。どうしてお米を使うなべっこ団子を作るのでしょう。
理由はお供え。貴重なお米を使う料理は、すべて神様への供物なのです。
私たちの年越し(こちらでは年取り)は12月31日。しかしお世話になった
神様に年越し料理をお供えする前に人が食べるわけにはいきません。
先人の時代は神様が家にたくさんいたので、日をかえて順番にお祝いしていきました。
その期間はなんと1ケ月。毎日のようにそれぞれの神様の料理を作ったのです。
このなべっこ団子は大師講様(弘法大師)の年取り料理。
数ある料理の中、最初に作られるものです。その日が旧暦の11月23日。
数ある郷土料理の中でもなべっこ団子の美味しさはNo.1。
当時も子供もみんな楽しみにしていたようです。
この「食農科学」は地域を巻き込んだユニークな科目として全国誌でも紹介されるなど
人気科目でしたが、学科再編でこの学科はすでに募集停止。
教科書は今も手元に残っていますが、幻の科目となってしまいました。
先人の知恵を伝承するすべも失しなわれ、今後が心配です。
冬が近づいています。ぜひお子さんと作ってみてはいかがですか。
なおそんな食農科学の取り組みのブログは今も閉じずに残っています。
機会があったらぜひご覧ください。










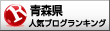
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます