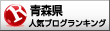ここは生物工学研究班の本拠地である生物工学実験室。
理系である農業高校には、さまざまな実験室がありますが
ここは大きく、設備も整っているのでとても使いやすい実験室です。
さて培養室を覗いてみると試験管内に植物が育っています。
おそらくコチョウランかシラン。
無菌播種を学ぶのに最適なラン科の植物です。
でも嬉しかったのは赤と青のLEDランプ。
これはTEAM FLORA PHOTONICSが
1年ぐらい前に生物工学研究班に貸し出したものです。
このランプは波長がちゃんとわかっている実験用のもので
なんと1個16,000円もします。FLORAが10年かけて購入したものと
かつて一緒にLEDを使って活動していた野菜班が実験を終えたことから、
くださったものと合わせて10個ぐらいあるうちの2つです。
草花班から環境班になってLED研究を行う機会が減った現在のフローラ。
他の班に使ってもらうことで宝の持ち腐れにならずに済んでいます。
LEDも頑張っています。
理系である農業高校には、さまざまな実験室がありますが
ここは大きく、設備も整っているのでとても使いやすい実験室です。
さて培養室を覗いてみると試験管内に植物が育っています。
おそらくコチョウランかシラン。
無菌播種を学ぶのに最適なラン科の植物です。
でも嬉しかったのは赤と青のLEDランプ。
これはTEAM FLORA PHOTONICSが
1年ぐらい前に生物工学研究班に貸し出したものです。
このランプは波長がちゃんとわかっている実験用のもので
なんと1個16,000円もします。FLORAが10年かけて購入したものと
かつて一緒にLEDを使って活動していた野菜班が実験を終えたことから、
くださったものと合わせて10個ぐらいあるうちの2つです。
草花班から環境班になってLED研究を行う機会が減った現在のフローラ。
他の班に使ってもらうことで宝の持ち腐れにならずに済んでいます。
LEDも頑張っています。