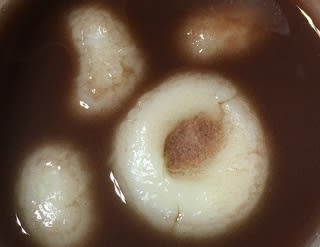ここに「食農科学」というテキストがあります。
でも文科省にはこのような科目はありません。つまりこれは学校設定科目。
2000年、今から20年前に前任校で仲間と手作りした科目でありテキストなのです。
この科目は昭和初期ごろまで続いていたこの地域の食や風習を体験することで
その背景にある地域の暮らしや文化を学ぼうという
かなりチャレンジした内容でした。ところが生徒には大評判。
手植えの田植えはもちろん、大根を栽培しては寒い中、洗って干したり。
さらにその食材を使ってさまざまな郷土料理を再現して行く学習は
自然の移り変わりを肌で感じられとてもダイナミックでした。
人気の秘密はまだあります。郷土料理を指導してくれるのは、なんと地元のおばあさん。
なべっこだんご、豆しとぎ、そばもち、漬物などの作り方を
手取り足取り教えてくれるのです。学習は秋になるとさらに展開します。
現在の地域特産の食材を使って新しい創作郷土料理を作り
たくさんの先生方を審査員として招き、コンテストを開催するのです。
確か、その時使ったお皿も地元の陶芸家の協力で自分たちで作ったもの。
選択した食材の理由、料理の名前などを女子ならではの
明るく楽しいプレゼンテーションが大会を盛り上げたものです。
そして最後は1年間、郷土料理を指導された地域の皆さんを招き
教わった料理を自力で披露する「披露宴」を開催し、食や文化の伝承を誓ったものでした。
最近は家におばあさんがいない家庭も多いので、この食と農を通したふれあいは
生徒もおばあさんにとっても、とても楽しいものだったようです。
農業経営シミュレーション、起業チャレンジなど
いろいろな学校設定科目を作ってきましたが、この科目は地元メディアはもちろん
全国版の雑誌でも紹介されるなど大きな反響を呼びました。
しかしこの学科はすでに閉科。したがってこの科目も消えてしまいました。
数年前、当時の教科書がないかと家庭科の先生から問い合わせがありましたが
なぜか現物もデータもみつからず、要望に応えられずにいました。
そころが先日、なんときれいな状態の幻のテキストが2冊も発見されました。
あれから20年、地域の風習が消えかけている今こそ、復活させたい科目です。
でも文科省にはこのような科目はありません。つまりこれは学校設定科目。
2000年、今から20年前に前任校で仲間と手作りした科目でありテキストなのです。
この科目は昭和初期ごろまで続いていたこの地域の食や風習を体験することで
その背景にある地域の暮らしや文化を学ぼうという
かなりチャレンジした内容でした。ところが生徒には大評判。
手植えの田植えはもちろん、大根を栽培しては寒い中、洗って干したり。
さらにその食材を使ってさまざまな郷土料理を再現して行く学習は
自然の移り変わりを肌で感じられとてもダイナミックでした。
人気の秘密はまだあります。郷土料理を指導してくれるのは、なんと地元のおばあさん。
なべっこだんご、豆しとぎ、そばもち、漬物などの作り方を
手取り足取り教えてくれるのです。学習は秋になるとさらに展開します。
現在の地域特産の食材を使って新しい創作郷土料理を作り
たくさんの先生方を審査員として招き、コンテストを開催するのです。
確か、その時使ったお皿も地元の陶芸家の協力で自分たちで作ったもの。
選択した食材の理由、料理の名前などを女子ならではの
明るく楽しいプレゼンテーションが大会を盛り上げたものです。
そして最後は1年間、郷土料理を指導された地域の皆さんを招き
教わった料理を自力で披露する「披露宴」を開催し、食や文化の伝承を誓ったものでした。
最近は家におばあさんがいない家庭も多いので、この食と農を通したふれあいは
生徒もおばあさんにとっても、とても楽しいものだったようです。
農業経営シミュレーション、起業チャレンジなど
いろいろな学校設定科目を作ってきましたが、この科目は地元メディアはもちろん
全国版の雑誌でも紹介されるなど大きな反響を呼びました。
しかしこの学科はすでに閉科。したがってこの科目も消えてしまいました。
数年前、当時の教科書がないかと家庭科の先生から問い合わせがありましたが
なぜか現物もデータもみつからず、要望に応えられずにいました。
そころが先日、なんときれいな状態の幻のテキストが2冊も発見されました。
あれから20年、地域の風習が消えかけている今こそ、復活させたい科目です。