世銀、南米諸国を評価/貧困層を支援/地域局長 “国家の役割回復”
現在1998年に、ベネズエラでチャベスが大統領になってから南米諸国では、変革の嵐が吹き荒れています。わが党は、前世紀の末から、21世紀を、資本主義の是非が正面から問われる世紀になると展望していました。そして、現在の南米諸国の状況は、我が日本共産党の情勢認識と展望の大筋が的を得た者であることを裏付けています。
南米大陸を形容する言葉といえば、元朝日新聞社の記者だった伊藤千尋さんの言葉を借りて言えば「反米大陸」という状況があります。もっとも、かつてのキューバと違ってアメリカは南米諸国を経済封鎖するというわけには行かないようでありますし、あのキューバ相手でも一方で経済封鎖をしておきながら貿易が2002年以降再開しているというように南米諸国とアメリカとの関係が変化しています。その、変化の方向性はアメリカ覇権主義の破綻、新自由主義の破綻を示すものです。現在、南米諸国で親米といえるのは、コロンビアだけです。1823年来アメリカの裏庭と言われ続けてきた南米諸国では、左派政権が選挙で成立し、対米自立の道を歩んでいます。
ベネズエラとボリビアにおいては、世界の貧困や環境問題などを資本主義そのものに本質的な原因があるとして、これらの国の大統領は、社会主義をめざそうとしています。日本共産党はこれらの国々を社会主義をめざす国とはみていません。というのは、まだ、ベネズエラにしてもボリビアにしても大統領が社会主義をめざそうとしていても、これが人民的合意となるにいたっていないからです。それにしても、まともな科学的社会主義の政党がない国々において社会主義をめざす流れが強まっていることは興味深いことです。
党中央委員会の記事によると世界銀行は、南米諸国において国家の役割を強化して貧困層を支援していることを高く評価している人のことです。世界銀行いわゆるIMFは、アメリカ流新自由主義を世界に押し付け、経済覇権主義の道具とされてきました。この問題について、ここでは詳論しませんが、かつてIMFを発足当初からチェ・ゲバラが南米諸国に破滅的な害悪を及ぼすと糾弾していたのです。実際にチェ・ゲバラが懸念していたことが1990年代の南米諸国で新自由主義の害悪が極限にまで達していったのです。ごく一部の富裕層と圧倒的多数の貧困層が渦まき、ラテンアメリカは世界で最も不公平な地域と見られてきました。これをもたらすのに、きわめて有害な役割を世界銀行は、果たしました。ボリビアでの水戦争が物語るように、世界銀行は公共部門の民営化などを融資の条件にして、これを飲んだ国々では貧困と格差が広がっていったのです。そういった時代があったことを考えると、新自由主義から決別した道を歩み、経済不況に対する打開の仕方を新自由主義とはちがった道で打開しようとし、貧困層を守っていったことを世界銀行が評価の対象にしているのは、世界の情勢の変化を如実に物語っています。
世界銀行が新自由主義を共用してきたことについて「(融資の際の)条件付けは過去の問題だ」とエクアドル国営アンデス通信のインタビューに語ったことは、新自由主義の破綻とアメリカの覇権主義の破綻を経済の土台から裏付けています。
世界の流れと、日本でも小泉構造改革によって見られた新自由主義の害悪を考えれば、対米自立と新自由主義からの決別こそが、本当の意味での国民が主人公の日本を築き上げ、貧困を無くす方向で不況を打開する道筋であることは、いよいよはっきりしてきました。
昨年の総選挙に続いて、今年の参議院選挙でも当然対米自立と新自由主義から決別するのかどうかが正面から問われます。また、構成的にこれを争点として押し上げて全人民に提起するべきことです。
本当に政治を変革するのは、大企業とアメリカに正面からものをいえる日本共産党です。
南米大陸に続いて日本でも対米自立と新自由主義からの決別をしていこうではありませんか。

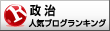
現在1998年に、ベネズエラでチャベスが大統領になってから南米諸国では、変革の嵐が吹き荒れています。わが党は、前世紀の末から、21世紀を、資本主義の是非が正面から問われる世紀になると展望していました。そして、現在の南米諸国の状況は、我が日本共産党の情勢認識と展望の大筋が的を得た者であることを裏付けています。
南米大陸を形容する言葉といえば、元朝日新聞社の記者だった伊藤千尋さんの言葉を借りて言えば「反米大陸」という状況があります。もっとも、かつてのキューバと違ってアメリカは南米諸国を経済封鎖するというわけには行かないようでありますし、あのキューバ相手でも一方で経済封鎖をしておきながら貿易が2002年以降再開しているというように南米諸国とアメリカとの関係が変化しています。その、変化の方向性はアメリカ覇権主義の破綻、新自由主義の破綻を示すものです。現在、南米諸国で親米といえるのは、コロンビアだけです。1823年来アメリカの裏庭と言われ続けてきた南米諸国では、左派政権が選挙で成立し、対米自立の道を歩んでいます。
ベネズエラとボリビアにおいては、世界の貧困や環境問題などを資本主義そのものに本質的な原因があるとして、これらの国の大統領は、社会主義をめざそうとしています。日本共産党はこれらの国々を社会主義をめざす国とはみていません。というのは、まだ、ベネズエラにしてもボリビアにしても大統領が社会主義をめざそうとしていても、これが人民的合意となるにいたっていないからです。それにしても、まともな科学的社会主義の政党がない国々において社会主義をめざす流れが強まっていることは興味深いことです。
党中央委員会の記事によると世界銀行は、南米諸国において国家の役割を強化して貧困層を支援していることを高く評価している人のことです。世界銀行いわゆるIMFは、アメリカ流新自由主義を世界に押し付け、経済覇権主義の道具とされてきました。この問題について、ここでは詳論しませんが、かつてIMFを発足当初からチェ・ゲバラが南米諸国に破滅的な害悪を及ぼすと糾弾していたのです。実際にチェ・ゲバラが懸念していたことが1990年代の南米諸国で新自由主義の害悪が極限にまで達していったのです。ごく一部の富裕層と圧倒的多数の貧困層が渦まき、ラテンアメリカは世界で最も不公平な地域と見られてきました。これをもたらすのに、きわめて有害な役割を世界銀行は、果たしました。ボリビアでの水戦争が物語るように、世界銀行は公共部門の民営化などを融資の条件にして、これを飲んだ国々では貧困と格差が広がっていったのです。そういった時代があったことを考えると、新自由主義から決別した道を歩み、経済不況に対する打開の仕方を新自由主義とはちがった道で打開しようとし、貧困層を守っていったことを世界銀行が評価の対象にしているのは、世界の情勢の変化を如実に物語っています。
世界銀行が新自由主義を共用してきたことについて「(融資の際の)条件付けは過去の問題だ」とエクアドル国営アンデス通信のインタビューに語ったことは、新自由主義の破綻とアメリカの覇権主義の破綻を経済の土台から裏付けています。
世界の流れと、日本でも小泉構造改革によって見られた新自由主義の害悪を考えれば、対米自立と新自由主義からの決別こそが、本当の意味での国民が主人公の日本を築き上げ、貧困を無くす方向で不況を打開する道筋であることは、いよいよはっきりしてきました。
昨年の総選挙に続いて、今年の参議院選挙でも当然対米自立と新自由主義から決別するのかどうかが正面から問われます。また、構成的にこれを争点として押し上げて全人民に提起するべきことです。
本当に政治を変革するのは、大企業とアメリカに正面からものをいえる日本共産党です。
南米大陸に続いて日本でも対米自立と新自由主義からの決別をしていこうではありませんか。




















