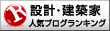注文住宅で考える
ファミリークローゼットのある暮らし。

※ハンガーパイプをメインにしたファミリークローゼット
注文住宅で
ファミリークローゼットを
計画する間取り計画。

※棚をメインにしたファミリークローゼット
家族で共有できる
ファミリークローゼットが一つあると、
生活動線が楽になる、
より便利に生活できるなど
多くのメリットがあります。
しかし、
そのメリットを生かすためには、
目的に合わせた配置やm取りを
知っておくことが大切です。
ファミリークローゼットとは何か、
メリットやおすすめの間取り、
注意点について。
ファミリークローゼットとは、
家族の衣服などを
全員分まとめて収納できる
クローゼットの事です。
家事を行う際などの
間取りと家事作業をよくするために
採用する場合があります。
洗濯物を全てまとめて片付けられる、
外のホコリや菌を
持ち込ませないなどの
メリットがあります。
家族の動線や設置目的によって
どのように配置されるかは
大きく変わります。
ファミリークローゼットの
メリットとして
近年人気が高まっている
ファミリークローゼットですが、
なぜファミリークローゼットを
採用するケースが多いのか?。
洗濯動線が改善されるという事。
ファミリークローゼットがあると、
洗濯物を一つの部屋で収納できるため、
洗濯動線の改善に効果的です。
ファミリークローゼットがない場合、
家族の部屋ごとに
洗濯物を収納することになり、
手間がかかります。
ファミリークローゼットがあれば、
家族の洗濯物を
まとめて全て収納できるため、
手間がかかりにくくなります。
整理整頓しやすくなる。
ファミリークローゼットは
家族の多くのものを収納できます。
服だけではなく、
コートやカバン、
帽子など、
外出用のものを
まとめて収納することで、
ものがスッキリと
片付きやすくなる点がメリットです。
玄関のそばに配置すると、
外から帰って
すぐ片付ける習慣にもつながり、
物が散らかりにくくなります。
外の汚れや菌を
部屋に持ち込みにくくなる。
玄関の近くに
ファミリークローゼットを設置すると、
外の汚れや菌を
部屋に持ち込みにくくなります。
外から帰ってきたらまず、
コートや帽子など
外で着たものを脱ぎ、
そのままリビングに入れば
菌や汚れを持ち込みません。
玄関の近くに洗面や浴室を設置すると、
より衛生的な状態を
保てるようになります。
間取りによっては
スペースの節約になる。
ファミリークローゼットがあると、
家族の個室ごとの
クローゼットをなくせたり、
クローゼットを小さくできたりします。
部屋を広くできるため、
逆にスペースの節約になる事もあります。
ファミリークローゼットは
いくつかの配置パターンがあります。
目的に合わせて適切に配置することで、
よりファミリークローゼットを
有効活用できるようになります。
廊下からつながるように
配置するケースは
特に階段のそばにあると、
家族が共有して使いやすく、
洗濯物の片付けや
整理整頓もしやすくなります。
また、洗濯物などが多いご家庭では
脱衣室近くに1~2畳脱衣室の近くに
ファミリークローゼットを配置すると
便利になる事も多いです。
クローゼットに普段着る
洋服を入れておくと
朝の着替えがしやすく、
帰ってきてからも
お風呂に入って
すぐ着替えられるため、
比較的動線に無駄がありません。
玄関のそばに配置するケースであれば、
シューズクロークにつなげて
配置することができ、
外出で使う小物などもまとめて
収納できます。
また、外の汚れを中に持ち込まずに
済むため、
家の中をきれいな状態で
維持するのにも効果的です。
ファミリークローゼットを
設置する時には、
間取りのコツがあります。
配置する目的を明確にする事。
ファミリークローゼットは
設置する目的によって
配置が大きく変わります。
そのため、
目的を十分に考えずに
間取りを決めてしまうと
失敗しやすくなります。
大まかに分けると収納を重視するか、
実際の使い方を重視するかで
配置するべき場所が変わります。
なぜファミリークローゼットを
計画したいのか、
どのように使っていきたいのかを
シミュレーションした上で
間取りを検討する事が重要です。
リビングや和室の近くには
配置しない方が良いです。
来客が多い家の場合、
リビングや和室など、
お客様がいる部屋の近くに
ファミリークローゼットを配置すると、
使いにくさを感じる場合があります。
ファミリークローゼットは、
目的に応じて適切な
配置が変わるため、
設置を検討する場合は
家族で目的をよく確認し、
配置を考えることが大切です。
自分たちが暮らすために大切なことを
どのように考えていらっしゃいますか?
過ごす空間の意味を丁寧に
デザインを大切にしたいと思います。
住まいの新築・リフォーム
整理収納・模様替え等
ご相談・ご面談・ご依頼等
■やまぐち建築設計室■
ホームページContact/お問い合わせフォームから
気軽にご連絡ください。
--------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
--------------------------------------