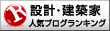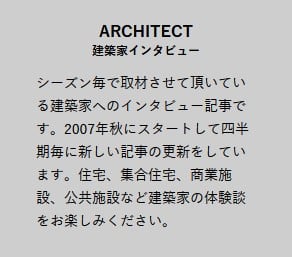家づくりでよくある失敗。

土地探しから家造りの場合に
建築の計画を視野に入れずに
先に土地を購入してしまって
昨今の物価高騰もあり
建物にあてる予算が足らず
予定していた家を
建てることが出来ない・・・・・。
そんな事態にならないように
家造りでは
総額との割合を
注意する事が大切です。
土地価格には
表記されていない事が多いですが、
不動産会社の
取引の手数料や
土地の売買に関する諸費用、
土地そのものを
使える状態にするための費用や
土地取得後の
税金関係や地域による
額面の差など、
様々な見えない
「不動産」だけではない
費用面にも注意が必要です。
勿論本来の目的である
「建築計画」にも
土地の状態や地域によって
法律上の制限も異なりますから
「計画」には「土地」と
「家」と「庭」と「資金」を
連動させることが重要です。
土地探しから始める場合には
土地を先に買わない。
家を建てるためには
土地を買わないと・・・・・と
先走ってしまうと
大失敗します。
家づくりの順番は、
まずは資金計画です。
普段スーパー等で
買い物する際に、
財布に幾らお金があるかどうか
把握していないと
買い物はできません。
買いたいものを
カゴに入れていって
レジでお金が足りない
なんて経験したくないですよね。
土地の購入も同じです。
建てたい家にかかる費用を
概算でも把握してから、
予算の中で残ったお金で
土地を検討する。
土地を先に買ってしまう人は、
土地が無くなってしまうことを
不安視する方が多いです。
しかし、
実際に不動産会社に
土地の買付証明を出す際に
大きな違いが出ます。
既に資金計画済みで
住宅ローンの目途も立って
準備が整っている人と、
資金計画をせず
住宅ローンも通るかどうか
定かではない人が
同時にいた場合
不動産会社は
準備が整っている人を優先します。
不動産屋会社の立場では、
支払い能力が証明されて
滞りなく払える人が優先です。
なので、
まずは資金計画を行うように。
土地のエリアに
こだわりを持つ方は多いです。
ある程度の「こだわりは必要」で、
職場の通勤や
親の実家との距離などは
問題ありません。
しかし
子供の為だけに
駅チカの土地を選ぶ事は
オススメしません。
駅チカの土地は皆が欲しがるため、
単価が高い上に
物件も限られています。
その場合は、
実際のところ一戸建てよりも
マンションを考えた方が
よいかも知れません。
勿論、
移動に便利な場所を
選ぶことは大事です。
そのうえで、
子供の為の期間を
リアルに考える事も重要です。
現金の方も
住宅ローンの方も
資金計画は色々ですが、
駅以外の要素も含めて
家族の変化と
家に住む期間の事も
長期的視野で
考える事が重要です。
一生住む家なのに、
数年間の為だけに
立地を選ぶことが
本当に求めているものか
考えておくこと。
子供のことを考えるのは
大切なことです。
過去の話しですが、
子育て住宅の専門店に
ご相談に行かれていた
住まい手さんも
いらっしゃいました。
子育て中の親からすると、
すごく魅力的だと思います。
延々と子供の為の
家づくりをしましょうと
アプローチされたようですが、
でも住むのは「家族」です。
自分たちの趣味を楽しんだり
思い描く家で
新しい生活を
楽しみたいといったご意見は
反映出来ない家に
なったそうです。
その住まい手さんは
たった3年で
その家の「リノベーションしたい」との
ホームページをご覧になり
僕のもとへご相談に来られました。
子供のことを考えていない
悪い親なのではないかと
悩んだりもしたそうです。
子供だけではなく、
住む人、
ご家族の意見を大切に
考えることで
「家」もよりよくなりますから、
考え方のふり幅は重要です。
誰が暮らす家なのか?
という「本分」を
紐解く事が大切です。
計画に対してのバランス。
広すぎる土地は要検討・・・・・。
広い土地は羨ましいけれど
外構費用も
考える必要があります。
新築の家なのに
外構に手が付けれていない姿を
よく目にします。
余分な範囲は
すべて外構費になって
予算オーバーのもとに
なりかねません。
土地の形状等にもよりますが、
最近は外構費も「材料価格」で
予算がどんどん
必要になっています。
広い土地では、
外構費だけで700万以上に
跳ね上がることもあります。
本当にどのように
暮らすことが最適なのかを
土地と家のバランスを
イメージしながら
考えてみてください。
高低差のある土地の検討。
道路からフラットで
段差のない土地は、
外構費でも
少し余裕が生まれます。
しかし段差が大きくなると
道路と土地の高低差を
解消したり
段差対策の為の工事が
必要になったり、
通常よりも高い場所に
建築資材を積むために
荷揚げ作業が必要となります。
高低差のある土地は
比較的安価ですが、
その分外構費が割高になります。
また、
足腰が弱くなったときに
階段が負担にならないか等も
考える必要があります。
良い土地は様々。
エリアと予算を絞って
良い土地が見つかるまで
何年も待つ方がいますが、
平均的に条件の良い土地は
皆が欲しがっている土地です。
勿論価格も高めです。
何年も待っている間に
資材の価格高騰や、
住宅ローンの金利が
高くなっていきます。
価格の価値も変わっていきます。
土地だけを見るのではなくて、
少し先の生活全般を
イメージして、
家族間でこれだけは
譲れない条件を決めてください。
学校の通学路や、
スーパーとコンビニまでの
距離など。
土地に点数をつけて比較し、
自分たちの
ライフプランにあった
土地の目標値を
考える事も重要です。
理想から考える事も
重要ですが
許せる範囲を
決めることが大切です。
よく家を建てるのは
いつがいいのか?
という事を
聞かれることがありますが、
家が必要になったタイミングが
それですよ。
という風に
お返事をさせていただいています。
待てば待つほど
物価や金利が
下がっていくような
ご時世ではありません。
自分たちの意思で
タイミングをつかんでください。
ハザードマップを確認する。
最近はゲリラ豪雨や
川の氾濫など、
自然災害が多発しています。
開発許可では奈良県の場合、
土地面積が1000㎡基準で
個人の住宅であっても
「貯水池」が必要ですし
土地面積が500㎡を基準にして
開発許可の対象になります。
※色々な土地仕様制限による工事が必要。
※但し、条件によっては更地判定が可能。
周辺状況については
家の周りはもちろん、
子供の通学路などは
必ずチェックしたほうが
良いです。
生活エリアが
自然災害に対して
強いのか弱いのか、
避難所がどこにあるのか、
避難所のルート等。
しっかり確認しておくべきです。
土地を見に行く。
紙媒体やGoogleMapなどで
土地を見て決めてしまう方が
いらっしゃいます。
しかし環境は
実際に見てみないと
わかりません。
現場が大事ということ。
土地の周辺環境は
なかなか分からないものです。
雰囲気を確認するために、
平日と休日の
昼夜等天候の事も含めて
「条件の良い時間帯」だけではなく
「観察」するように
実際に何度か
見に行ったほうが良いです。
昼夜の雰囲気は
結構変わります。
昼はとても良いけれど、
夜は街灯が少なくて危ない等。
静かなところ、
賑やかなところ。
どういった雰囲気が
好みかは人によりますが、
事前にある程度は
「意識」しておくことを
オススメします。
家造りの際には
実際に土地視察を
行っていますが、
ご希望していただければ
一緒に土地を見に行きます。
その場でざっくりとした
外構の費用感などの
会話をさせていただいたり、
住まい手さんの
気づいていない
「建築」と「造成」を
視野に入れた
考え方の工夫も
お話しをします。
不動産会社は
土地を売るための
目線ですが、
僕自身は
土地がどこであろうと
家と暮らしを
着地に据えた目線です。
予算も暮らしも
実情を考えて、
暮らしの着地点に
どの程度あった土地なのかを
大切にと思います。
住まいの新築・リフォーム
リノベーションのご相談・ご質問・ご依頼は
■やまぐち建築設計室■
ホームぺージ・Contact/お問い合わせフォームから
気軽にご連絡ください。
-------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
https://www.y-kenchiku.jp/
-------------------------------------