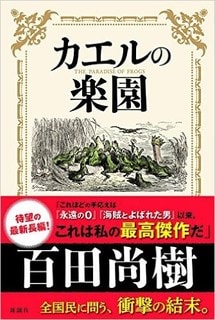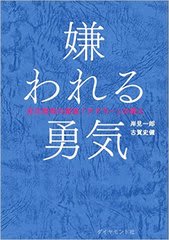「嫌われる勇気」を書いた、岸見一郎さんの講演会に参加してきました。
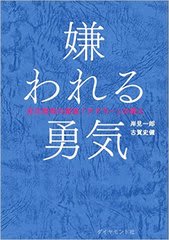
ユング、フロイトと並ぶ、三大巨匠の一人であるアドラー心理学を日本に広めた人として
一躍有名になった人です。
心理学者、哲学者=気難しそう というイメージを持っていたのですが、もちろん普通の人ではないことは
間違いないですが、学校の先生をやっている奥さんの代わりに、子育てをやってきたというキャリアの方で、
ちょっと尾木ママのような、主婦の気持ちにも寄り添えるような、不思議な雰囲気の人でした。
今回は人事系の、「いくら変革を掲げても、組織・人が変われないワケ」というテーマだったのですが、
岸見先生の話で、印象的だったのは、「ほめてはいけない」ということ。
この考え方は、アドラー心理学の特徴で、アドラーだけが唯一「ほめるな」と言っているようですが、
褒めるだけでなく叱ってもいけないという考えです。
なぜかというと、「あらゆる対人関係は、対等の横の関係」でなければいけないという考えに基づいているからです。
人間関係に上下関係を持ち込んではいけないという考え方。
これは夫婦関係、親子関係、教師と生徒、上司と部下、すべての関係において言えることで、上下ではなく
役割分担が違うと考えるようです。
面白いなと思ったのは、子供との関係において。
子どもがミルクをこぼした時:
普通の親 「何やってるの!だから気をつけなさいって言ったじゃない(怒)」
岸見先生 「どうすれば失敗しないと思うの?」
子どもが欲しいものがあってデパートで泣き叫んでいる時:
普通の親 「いいかげんにしなさい!(怒)」
岸見先生 「そんなに泣かなくていいから、言葉でお願いしてください」
子どもがなかなか起きてこなくて、9時過ぎに起きてきた時:
普通の親 「何時だと思っているの(怒)」
岸見先生 「生きていてくれてありがとう」
子どもが勉強しない時:
普通の親 「いい加減に、勉強しなさい(怒)」
岸見先生 「事態はあなたが考えているほど楽観的ではないので、一度話しませんか?」
実際に激昂しているときに、こういう会話が成立するのかどうか、やったことも、やられたこともないので、
イメージがつかないのですが、確かに子どもに勉強しろと言うのは、他人の課題に土足で踏み込んでいることであるという
アドラーの考え方は共感できます。
そして褒めてはいけないということの例
2歳の子どもがカウンセリングを行っている間、1時間おとなしく待っていた時:
普通の親 「良く待ったね~、えらかったね」(褒めてはいけない)
岸見先生 「ありがとう、助かったよ」
褒めるということは対等な関係ではないので、アドラー的には、2歳の子どもに対しても、対等に接することが大事だと
する考え方です。
褒めるということを完全否定するのは、どうかなと思うのですが、2歳の子どもでも人格を尊重して対等な気持ちを持つ
ということは、私も常にそのように考えているので、納得しました。
さてこの考えを組織改革に持ち込んだらどうなるか?
褒めない、叱らない、他人の課題に土足で入り込まない
これじゃ、全く無責任な上司になってしまいますが、そうではなく、他人を変えようとするのではなく、
自分が自分の人生や仕事の課題から逃げないで、挑戦し、取り組んでいくという姿勢を見せるということが大事であり
その勇気が周りに伝染して、組織が変わる。
下町ロケットのごとく、がんばりま~す。