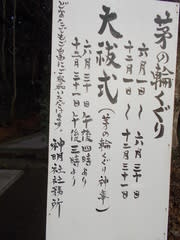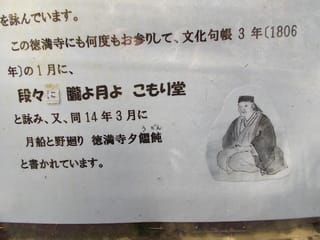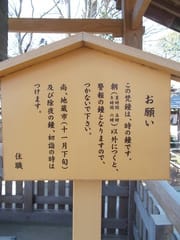1 月 12 日(月) 京王線改札口を出て新宿御苑に行きました。初めてのコースなので、見るものがみな珍しく、キョロキョロしてしまいました。


(駅前のビルは工事中)


(この改札口は初めて)





そして、道端に発見した雷電稲荷神社。




(なぜか狐に金網がかぶせてある)

帰って blog “猫の足あと”で調べてみると、この神社について次のような解説がありました。
「創建年代は不詳ですが、源義家が奥州征伐途中雷雨にあい、小祠前で休んでいる時、一匹の白狐が現れ、義家の前で三回頭を下げたところ雷雨がたちまち止んだことから雷電神社と呼ばれるようになったと伝えられています。
昭和 3 年に花園神社に合祀され、宗教法人としては消滅しましたが、現在も鳥居と祠が残されています。」