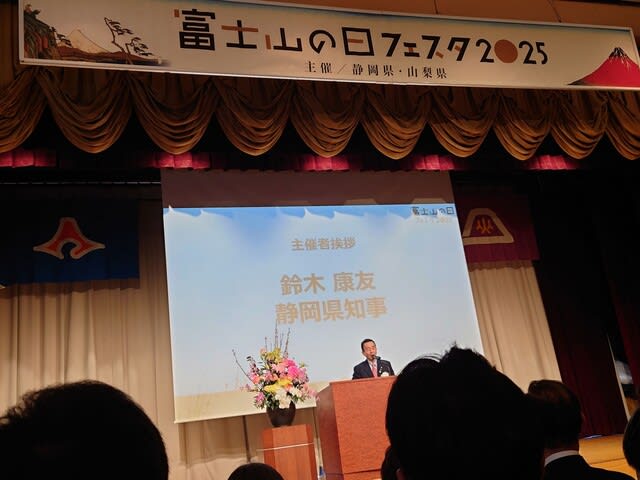令和7年2月28日(金)
能登半島地震は、静岡県にも伊豆半島を抱え、多くの類似点があり教訓を残しました。現在開会中の県議会2月定例会でも半島防災に関する取組について、2月補正予算及び令和7年度当初予算案に盛り込まれ、南海トラフ巨大地震に対する備えも進んでいます。
しかし、能登半島地震後の現地の復興状況は依然として進んでいる状況とはいえず、特に人口が急激に減少するなど、本当の意味での復興につながっていくのか課題も見えています。本県の場合も、同様な状況があり得るのではとの想定を含め、更なる状況分析とそれに対応した体制を整えることが重要と考えます。
2月定例会で知事が触れた半島地震対策は、能登半島地震では、土砂崩落等により交通網が寸断し、半島という地理的特性などから、孤立集落の発生や避難所生活の長期化、多数の住宅被害といった課題が顕在化した。昨年11 月、国が能登半島地震を踏まえた今後の災害対応について、報告書を取りまとめたところである。この分析も踏まえ、伊豆半島を有する本県において、速やかに各種の対策を講じる。
孤立を防ぐためのインフラ整備については、災害発生時にも円滑な物資調達や輸送が行えるよう、伊豆縦貫自動車道の早期全線開通など道路ネットワークの整備・強靱化を、引き続き国に強く働きかけていく。あわせて陸海空から被災地へ円滑に進入できるよう、緊急輸送路沿道の空き家の除却や、着実な港湾整備、拠点ヘリポートの資機材整備の支援等を行っていく。孤立予想集落においては、必要な物資等の備蓄支援を拡充する。
また、各市町が水道施設等を耐震化し、自給可能な水源等を確保できるよう、特に耐震化率が低い賀茂地域の水インフラ広域防災計画を策定する。
さらに、情報収集体制を強化するため、県災害対策本部や各地域局のほか、災害拠点警察署などに計20 台の衛星通信設備を整備する。
避難生活の長期化への対応については、能登半島地震において、トイレが不足する課題等が生じたことから、市町と役割分担しながら県内外の災害派遣時に活用するトイレカー等を整備する。また、要配慮者への支援のため、福祉避難所や救護病院等への調査結果を踏まえ、不足する非常用電源を確保するなど、地震・津波対策等減災交付金も活用し、総合的に支援していく。
報道によると能登半島地震では、避難先からの人口回復が遅い理由として、災害公営住宅の建設の遅れや、特に現役世代が戻るための暮らしや雇用の確保と子育て環境の整備について整っていないことを上げています。
本県の防災対策は前進していると考えますが、特に伊豆半島では復興時における人口回復が速やかに進むのか、能登半島の現状を検証し、対策を講じていく必要があります。