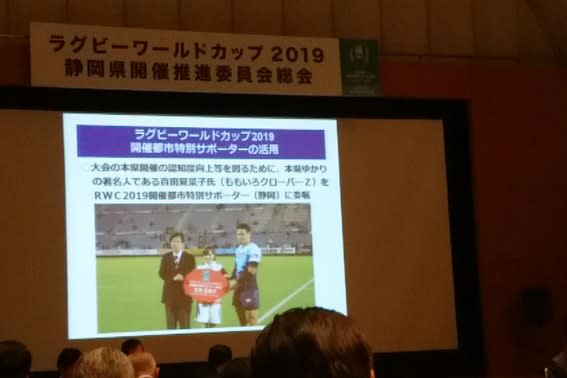平成30年3月30日(金)
静岡県が取り組む産業人材確保・育成プランの資料が県庁から送られてきました。人材育成は最重要課題の一つで、私が県議会産業委員会に所属していたこの1年間の審議には、毎回、出てきた課題でもあります。来年度から10年後を見据え始まる総合計画ではさらに取り組みが強化され、その元になるのがこのプランです。
人材確保には、進学等で首都圏に出て行った学生が卒業後にU・I・Jターンすることや、転職などで本県に移住していただくことが一つの解決方法でもあります。
届いた資料に目を通しながら、首都圏における人材確保がどのように展開されているか、直接現場に出向き確認することが必要と考え、県が首都圏に開設している「静岡U・Iターン就職サポートセンター」ならびに、「静岡県移住相談センター」を視察しました。
通常、視察の際には所管部署を通じて訪問先との調整を図ることが多いなか、今回は事前の調整を図ることなく突然の訪問で、現状をストレートに見ることができました。
最初に、就職サポートセンターは、首都圏の学生を対象に、個別の就職相談や企業紹介、就職応援セミナー等を実施し、県内企業の持つ高い技術力や将来性、職場環境などの企業情報とともに、県の施策により県内に就職された方の協力を得るなどして、本県の暮らしやすさや地域の魅力を効果的に発信し、県内への就職を促進する機能を果たしています。
今日訪問したのは、3月1日から31日までを実施期間とする「日替わり静岡県内企業説明会」です。東京駅八重洲口から徒歩で10分ほどのところに開設され、企画名の通り、毎日日替わりで、一日最大4社の県内企業が説明会を開催するもので、明日が最終日であることから、この事業の総括的な情報を得ることができることも期待して訪問したものです。
今日午後の予定では、県内から2社がブースを開く計画でしたが1社のみが実施ており、応対中でないことを確認し担当者にお話を伺いました。この企業は朝から開設しているものの、来訪者は1名で主催者が紹介した学生のみでした。状況は昨年よりも厳しいといいます。会社の所在地である浜松市も、東京、名古屋、大阪の大都市で開催しましたが状況は変わらなかったといいます。このところ好景気が続き、学生にとっては売り手市場で、中小企業の苦戦が伝わってきます。また、3月期はまだ大手中心に就活が展開され、それが落ち着く6月頃から中小企業にチャンスが巡ってくるともいい、このような支援事業は、この時期でなく6月頃に実施することが良いのではという感想をいただきました。

(説明会場入り口にて)
次に訪問したのは、県移住相談センターで、有楽町にあるこの施設は、全国の移住相談を扱い、ブースは県ごとに独立しており、運営は認定NPO法人ふるさと回帰支援センターです。静岡県を受け持つのは2名の女性で、設置から3年経過した「“ふじのくににすみかえる”静岡県移住相談センター」という名称です。
本県の次年度事業では、「転職」を考える時期となる25歳~34歳位の県外在住の若い社会人に、努力をすれば自らの夢を実現し、幸福を実感できる舞台としての本県の大きな「魅力(暮らしやすさや生涯収支モデルプランなど)」や「場の力(ポテンシャル)」をSNSなどの情報媒体や同窓会のネットワーク等を通じて届け、若者の『30歳になったら静岡県!』の第一歩を応援するとしています。
この取り組みが、移住相談センターの窓口を担う方々の認識としてどうなのかが視察のポイントでした。窓口を訪れる人達の年齢は、年々若くなる印象があり20歳代~40歳代が多いといいます。彼らは新卒として就職し、現在の仕事の様子が見え始め、次のステップを考える時期にさしかかる頃で、職種はIT企業が多いということでした。しかし、中小企業は新卒に目が向きがちで、優秀な中途採用に目が向かないようで改善の余地がありそうです。
この年代は家族持ちも多く、子どもの保育や教育環境が整っていなければ転職による移住はできません。本県の場合は、東海道線沿いに期待される企業が多い反面、保育や教育環境が整っていない、待機児が多い都市ばかりといいます。これらの改善は急務なのかも知れません。さらに、女性の再就職は厳しく、転職でしかも地方に移ると、これまでよりも所得が減少することもあり、共働きが必要になる可能性が高まるなか、これもマイナス要因となっています。
相談センターはNOPが運営しているので、職員間での連携がしやすいことから各県の情報交換がしやすいといいます。これが、各都道府県の職員が担っているとすれば、柔軟な対応ができるか疑問という見方もあるようでした。
そのほか、県内では磐田市の積極的な取り組みが注目されていることや、農業への就労希望者が増えているといい、JAなどの支援機関の取り組みが評価されているようです。

(全国のふるさと回帰支援センター)

(対応いただいた、県移住相談センターの相談員の皆さん)
2カ所の視察先は突然の訪問であったにもかかわらず、熱心に対応していただき感謝申し上げます。同時に、貴重な情報から厳しい現実を突きつけられ、それを解消する施策として見直しが必要なことが分かりました。