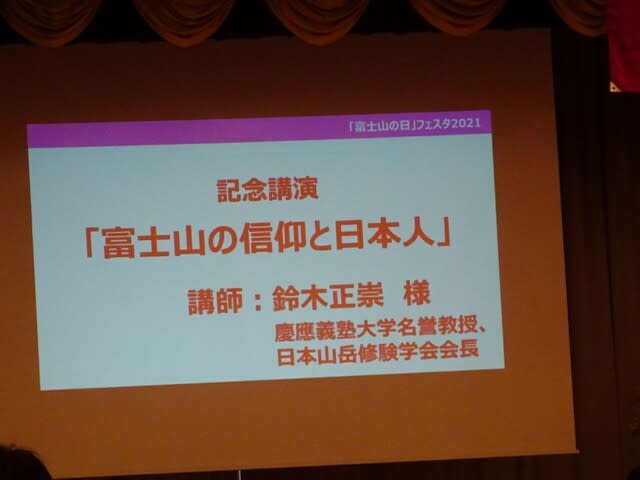令和3年2月28日(日)
私の代表質問に対する知事答弁の概要を報告します。今日は令和3年度当初予算編成要望に、県がどのように取り組んだかです。

(代表質問に登壇)
私からの質問は、2月1日に知事から説明を受けた予算要望への回答の評価について、我が会派が約半年をかけて県民から聞き取った要望を踏まえ取りまとめた令和3年度当初予算は、概ね要望どおりの結果と受け止めている。
県内をくまなく回り寄せられた、政党支部や業界団体、自治体からの貴重な要望は、私たち会派の政務調査会で整理し分析され、既存事業の拡充や新規事業等、230項目の要望として取りまとめ、昨年12月16日に知事に提出し、実現に向けて働きかけてきたものである。また、新型コロナウイルス感染症に関する要望も多く、それらも別枠として要望してきた。
要望内容のうち、さらに57項目を重点要望として抽出し折衝を続けてきた結果、関連事業は100を超える事業に上り、その中では新規事業のほか、多くの既存事業で予算の増額が図られている。
新型コロナウイルス感染症の影響による税収減など、来年度当初予算の編成は、例年になく厳しい環境であるが、私たちと当局とで議論を交わしながら、効果的な事業内容への工夫などを重ね、県民の要望ができる限り実現できる策を練ってきた結果と受け止めている。
そこで、今回の予算編成に関し、会派の要望がどのように反映されたのかを伺う。
知事からは、県税収入が前年度を400億円下回る大変厳しい状況下での編成となった。その中において、自民改革会議から要望あるいは意見をいただいた件について、真摯に受け止め、当初予算案に可能な限り盛り込んだ。
また、別枠で要望した感染症対策については、感染患者の病床確保、PCR検査・抗原検査の実施、軽症者の療養施設の確保等々、医療供給体制の維持に万全を期していく。今後本格化する、ワクチン接種においては、市町と十分連携し、速やかで円滑に実施できる体制を構築する。
また、保育所職員等への慰労金の支給について、2月補正予算に計上し、先議していただいた。
社会経済活動の再生については、ウイズコロナ・アフターコロナ時代を見据え、中小・小規模企業者の資金繰り、ビジネスモデルの転換、デジタル化等々、年度を超えて切れ目なく支援していく。
また、深刻な打撃を受けている観光事業者、鉄道・バス等の公共事業者に対しても、しっかり支えていく。
さらに、県民の生活に身近な道路や河川等のインフラ整備を図るために、県単独事業として400億円を計上した。激甚化する風水害に対応するとともに、コロナ禍においても暮らしやすい県土づくりを進めていく。
このほか、私立高等学校等における教育費負担の軽減を図るため、授業料の減免支援の対象世帯を年収700万円から750万円まで引き上げるほか、ドクターヘリを運航する病院への補助金の増額や、地域包括ケアシステムの拡充などに要する経費も盛り込んだ。と答弁いただきました。